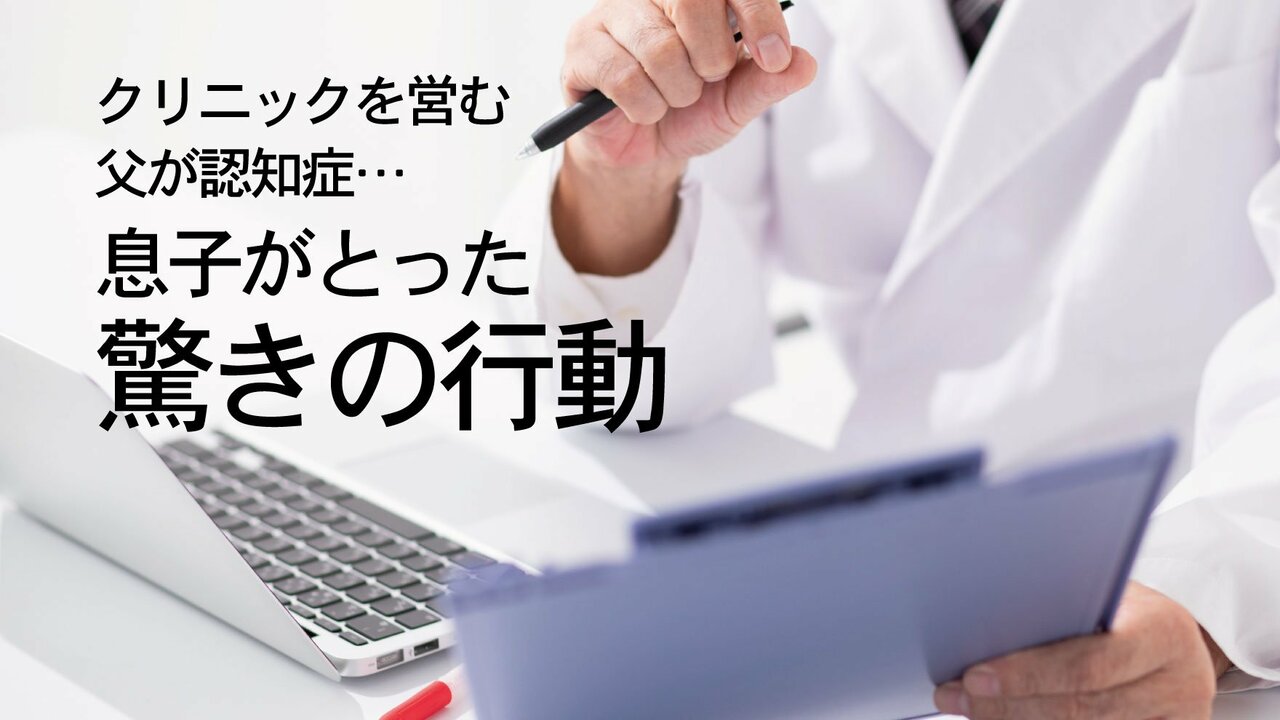「俺のせいなんだ」
「よう、諌。久しぶりだな」
果てしなく続くと思われた外来診察が終わり、院内食堂でだるい首を揉みほぐしていると、背後から声を掛けられた。そこには緑の手術着によれよれの白衣を羽織った旧友の優介(ゆうすけ)が立っていた。
「おお。優介、久しぶり」
「対面を借りるぞ」
力ない笑みを浮かべると、優介はどかっと腰を落ち着けた。こいつは医学部生時代からの悪友で、おなじ大学附属病院に心臓外科医として勤務している。しかしながら違う病棟で接点がなく、こうして話すこと自体、かなり久しぶりだ。
「最近は顔も見かけなかったな。元気にしていたか」
「元気なもんかよ。これから大動脈置換術だ。これで三日連続、一〇時間越えの大手術だよ」
激務が祟ってか顔色は冴えず、髭も伸びたい放題だ。もともと頬骨が張っていたが以前よりもさらにほりが深くなり、睡眠もろくに取れていないのか、目元に覇気がない。
「心臓外科医の大変さは、群を抜いているよな。よくやるよ」
「自分でも感心しているくらいさ。だがそれも、あとすこしになる」
優介の声の調子があきらかに落ち、どこか寂しさが滲んでいた。ふきんで机を拭いていたわたしは首をかしげる。
「ん、どういう意味だ」
「俺さ。今年いっぱいで医局を辞めて、実家のクリニックを継ぐことにしたんだ」
「え。う、嘘だろう」
わたしは驚きのあまり声が裏返ってしまった。オペの搬入時間が迫っているのだろう、優介はいただきますも言わずに丼を搔きこんでいく。
優介の実家は地元で評判の内科クリニックで、こいつはそのひとり息子だった。跡取りとしての将来を嘱望(しょくぼう)されたものの、こいつは用意された椅子を蹴り、心臓外科医としての道を選んだ。そのことで両親とは揉めに揉め、勘当寸前だったと聞く。だが今になって、どういう風の吹き回しだろう。