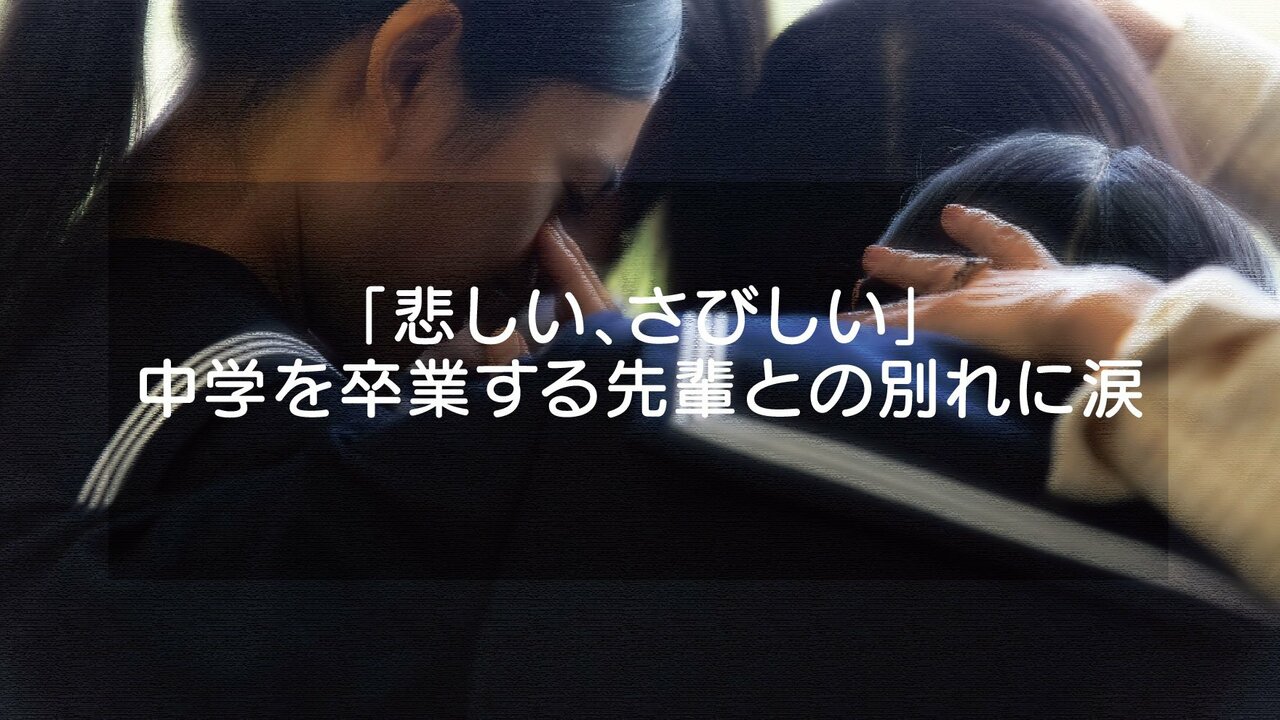六月二十二日 金曜日
「ああ、ヒナ」どこかしらほっとしたような声があがる。ヒナと呼ばれた少女―日奈邑六花(ひなむらりつか)。
吸いこまれるような黒い瞳。上品に整った顔だち。ビスクドールみたいにきれいな肌。お嬢さま然とした雰囲気に、肩から背中へさらさらと流れる長い髪が似あいすぎるほど似あう。しかも、成績は常に学年のトップクラス。振るまいのひとつひとつが大人びていて、先生たちでさえ、彼女には一目置いている節があった。
かといって、べつに高飛車なところはなく、テスト前ともなれば、気軽にアドバイス役を買って出たりする。クラスで揉もめごとじみたことが起こったとき、最後にそれをとりなしてまとめるのも彼女だった。
新学年がスタートしてまだ三カ月だが、彼女は、ごく自然に、多くのクラスメイトたちからの特別な信望を集めていた。美しい人形になりたい―穂波がそう願うとき、思い描く理想の人形があるとすれば、それは日奈邑六花だった。
同時に彼女は、穂波がどんなにがんばろうと、永遠にそんな人形にはなれないという現実を教えてくれる残酷な存在でもあった。
そして―穂波は、かなり前に気づいてしまった。六花が、クラスメイトたちをバカにしきっていることを。というより、たぶん六花は、自分のまわりの人間すべて(そこにはクラスメイトのみならず、三年生や先生も含まれる)を、はなからバカにしていた。
たしかに穂波には、他人と比べ、人の感情に対してやや敏感すぎるところがあった。気がつかなくてもいいことに気づき、読まなくてもいい空気を読んで、結局ひとり疲れきってしまう。それを気けどられないよう、いかにもおおらかにふるまって、そんな自分にまたうんざりする。
その無限ループみたいな毎日。今日の雨と同じ―どこまで行っても出口がない、合わせ鏡の国。穂波の心は、いつもそんな世界に閉じこめられていた。
ただ、少し注意して観察すれば、人を小バカにするような態度を、六花が周囲に対して特に隠しているわけではないことくらいすぐにわかる。ほかの生徒がそのことにあまり気づいていないようなのが、穂波にはかえって不思議だった。にこやかに微笑んでい
ても、その目に宿る氷のかけらのような光は、常に周囲との距離をおしはかっている。けっして他人に心をゆるしたりはしない、孤高の人形―。