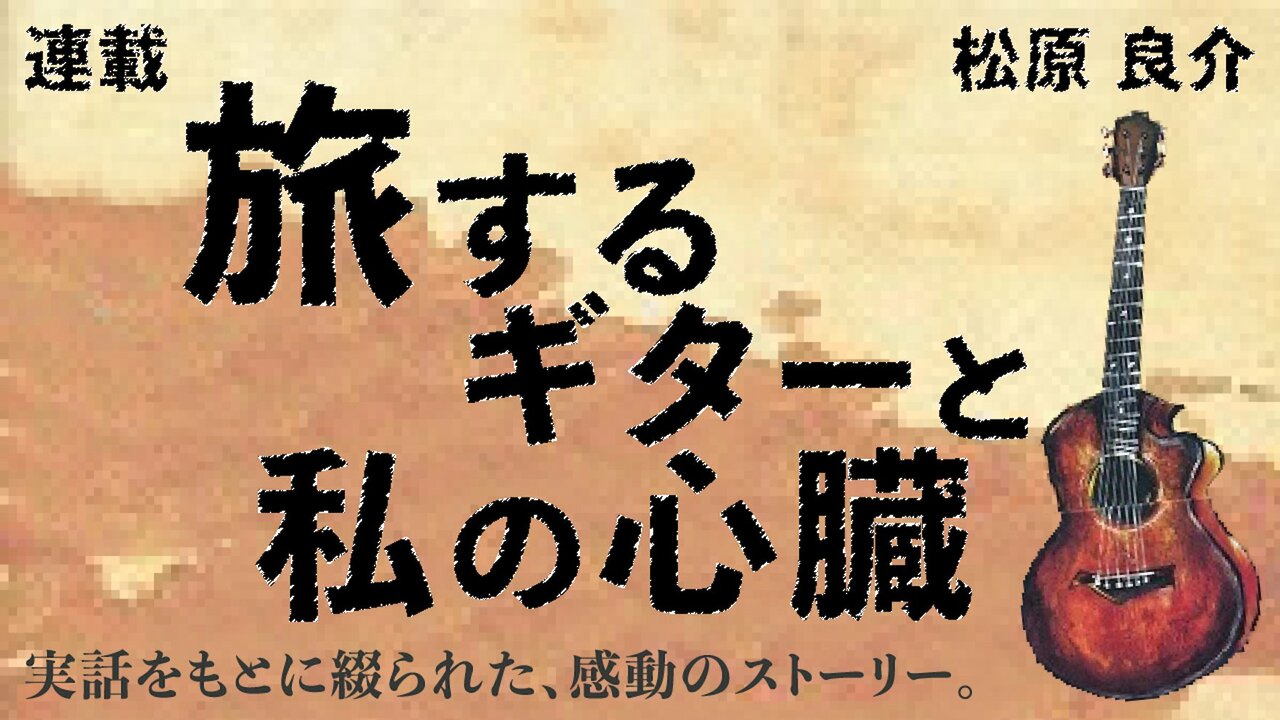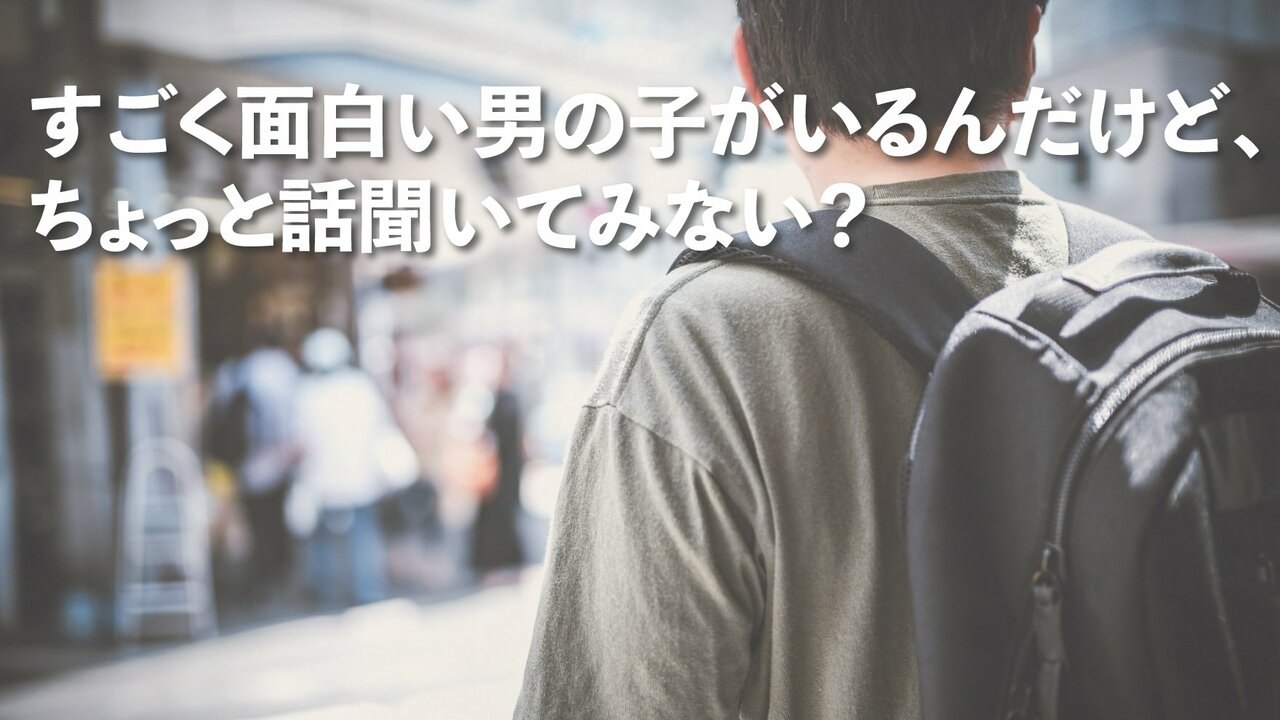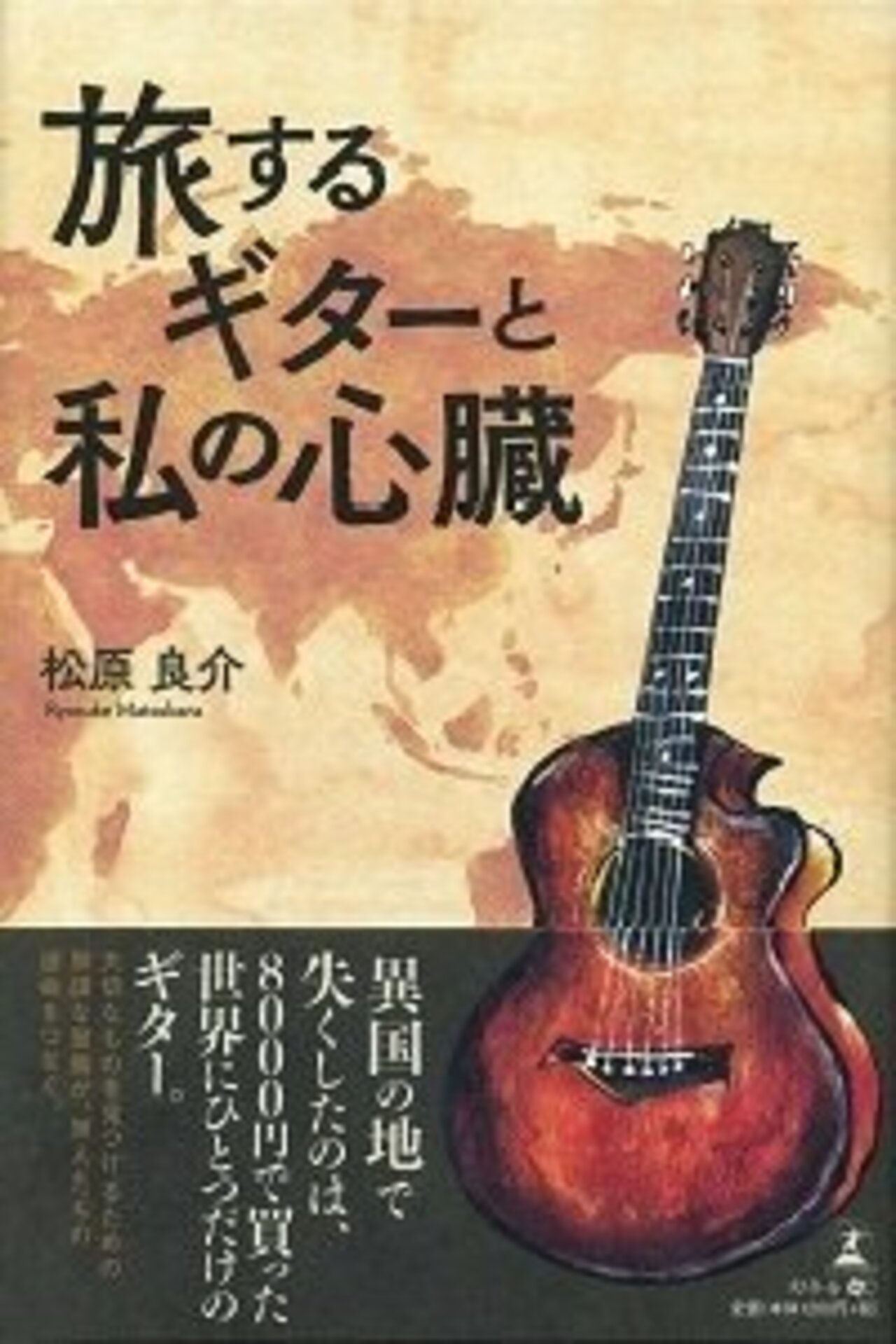インタビュー1(塩見麻里)
2018年10月12日。
エスペランサ出版の編集部に勤める塩見麻里は、バンコクに住む従妹の板垣夏美から「面白い話があるんだけど」という連絡を受けた。
「麻里ってまだ出版社に勤めているんでしょ? すごく面白い男の子がいるんだけど、ちょっと話聞いてみない?」
夏美は30代半ばになってタイ人と結婚し、そのままバンコクでマッサージサロンを始めた変わり者だ。塩見は夏美のほうがよっぽど面白いネタだと思っていたが、話の内容を聞くうちに、すっかり夏美の話にのめりこんでしまった。
夏美のいう面白い男の子というのは宇山祐介という100ヵ国以上を旅したバックパッカーだった。バックパッカーの珍道中ならよくある話だが、興味を引いたのは彼が旅をしていた理由だった。
彼は現在アメリカに滞在していて、来週日本に帰国するという。
塩見は彼に直接会って詳しい話を聞きたくなった。
「じゃあ、彼に話してみるわ、期待して待っていてね」
夏美はそう言って電話を切った。
塩見の勤める出版社に電話があったのは翌朝、宇山のほうからだった。
都内の大手出版社に勤めて4年。本に囲まれた生活に憧れていた塩見にとって、出版社に入社したのは自然な流れだった。
塩見は子どものころから、この世のどこかに陽の目をみないままどこかに眠っている、読んだ人の人生を変えてしまうような物語があると信じて、自分がそれを見つけることを夢見ていた。だが、期待に胸を膨らませて飛び込んだ業界は思い描いていたものとは程遠く、売上至上主義に徹した経営方針や作者の無理な要望に振り回され、気がつけば夢物語どころか過酷な現実を突きつけられる毎日を悶々と過ごしていた。どうにか一人で仕事を任されるようになった頃には、すっかり夢物語のことは頭の片隅に追いやられていた。
これといったやりがいも感じなくなっていた塩見のデスクの引き出しには、決心が固まらないまま置かれた辞表がひっそりと眠っていた。やがて秋も深まり始めた頃、まるで塩見を引き留めるかのように、宇山祐介の物語が出現したのである。
2018年10月28日。インタビュー当日。塩見は宇山祐介と待ち合わせをしているカフェに向かっていた。待ち合わせの時間は15時。この日は朝から陽が陰っていたので、塩見はいつもよりも秋を深く感じた。
クローゼットから引っ張り出した秋物のコートは、昨年のセールでなんとなく衝動買いしたせいか、すでに塩見の気分に合うものではなくなっていた。そのせいなのか、今履いているお気に入りのチャコールグレーのパンプスとも抜群に相性が悪く思えた。
時間よりも30分早く待ち合わせのカフェに着いた塩見は、カウンターでホットコーヒーを注文してから、店内を一通り見渡して、落ち着いて話ができる席を探した。かなり広々とした店内だったが、都内のお洒落なカフェを特集する雑誌の企画にたびたび登場していることもあってか、平日にもかかわらず少し混みあっていた。
塩見は、喫煙席を通り過ぎた先にある窓際に、二人用の席が空いているのを見つけた。両手を広げたほどの大きな窓からは渋谷のスクランブル交差点が一望できた。上から見ると通行人が不思議なほど規則的に動いているのがよくわかり、交差点の信号機が変わるたびに人の動きに見入ってしまった。
大型ビジョンで流れているHARTSのPVは、人気ドラマ『ぼくの細道』の主題歌だ。HARTSは何年か前にYouTubeから登場したロックバンドで、当時塩見が付き合っていた彼と観に行ったフェス以来、塩見はすっかりHARTSにハマっていた。
ちなみに塩見の一番のお気に入りはヴォーカルのWalkyだ。整ったかわいらしい顔立ちとは対照的に熱い志を持った青年で、コンサートやアルバムの収益の一部を被災地に寄付したり、孤児院などのために基金を募ったりと、慈善活動を率先して行っている。
塩見がスマホでメールをチェックしていると、注文したホットコーヒーが運ばれてきた。その香りに少しほっとした気分になった。冷えた手をそっとカップに添えると、少しずつ身体にその温かさが染み渡っていく。
「塩見さんですか?」
隣の席から、チラチラとこちらの様子をうかがっていた男性が立ち上がって話しかけてきた。ほっそりとした端正な顔立ちの男性だった。男は宇山祐介を名乗った。
不意を突かれた塩見は、慌てて飲みかけたコーヒーカップをテーブルに戻した。夏美から「3年間世界を旅してきた37歳の男の子」、と聞いていた塩見は、てっきり体格の良いワイルドな風貌の男が現れるとばかり思っていたが、目の前に現れた男は想像と違っていた。
一見、旅などとは無縁に感じるようなひょろりとした風貌の宇山は、
「すみません、少し早く着いてしまって……」
と困った顔をしながら会釈した。
その姿を見た塩見は、すっかり気が抜けてしまった。ただ、年齢よりもずっと若く見える宇山を見て、夏美が37歳の男性に対して“男の子”と言っていた意味はなんとなく理解できた。
「よく私が塩見だとわかりましたね?」
と塩見が尋ねると、
「なんとなくそうじゃないかと……」
と宇山は頼りない笑顔を作ってみせた。
宇山は線が細く、黒のハイネックセーターが似合う男だった。猫背で弱々しい風貌だが、真っ直ぐな眼差しが誠実さを感じさせた。
塩見が「どうぞ」と、前の席を進めると、宇山は軽く会釈してから自分の席に置いてあったジャケットと少なくなったアイスコーヒーのグラスをこちらに運んできた。
塩見が「改めまして」と自己紹介をして名刺を渡すと、宇山は、自分が名刺を持っていないことを申しわけなさそうに言ってから、改めて宇山祐介を名乗った。
「お忙しいところ時間を作ってくださってありがとうございます。宇山さんは昨日帰国されたんですよね?」
「はい、昨日の午後帰国しました。久しぶりに東京に来ましたが相変わらず人が多いですね」
宇山は小さくため息をつきながら言った。
「こちらから伺うつもりだったのですが、わざわざ渋谷まで出てきていただいてすみません」
「いえいえ、大丈夫ですよ。このあと渋谷で人と会う約束をしているので、ちょうど良かったです」
「宇山さん、今はアメリカにお住まいなんですよね?」
「あ、はい、えーっと、昨年旅を終えて一度帰国したんですが…ええっと、はい、そうです」
宇山は緊張しているせいなのか、少し落ち着かない様子で訥々と話した。
塩見はもう少し世間話を続けることにした。仕事は何をしていただとか、お互いの家族構成とか、どこの国が一番印象深かったかとか、たわいもない話をした。
宇山は細身の風貌のせいもあってか、どこか弱々しく、話をしていても時折自信のない困惑したような作り笑いを見せた。5分ほど話して話題が従妹の夏美の話になると、宇山は急に改まって話し始めた。
「夏美さんにはバンコクで本当にお世話になりました。何とお礼を言っていいものか。今回も帰国する直前に夏美さんから連絡があって、この話ができる機会を作っていただいて本当に感謝しています」
宇山は真剣な顔つきで言った。その様子を見た塩見は、ここぞとばかりに編集者のスイッチを入れた。
「先日、夏美から宇山さんのお話を聞いて、ぜひともご本人から直接お話をお聞きしたいと思いまして──」
夏美から聞いた話が本当ならば、目の前にいる男がこれから話すことは、かつて塩見が探し求めていた夢物語そのものといえた。塩見はコップの水を口に含んで気持ちを落ち着かせてから、ゆっくりと口を開いた。
「宇山さんは“探し物”を見つけるために世界を旅していたとか?」
「はい」
宇山は軽く頷いて答えた。
「詳しくお聞かせ願えますか?」
塩見が尋ねると、宇山は少し上のほうを向いて何かを思い出すような顔をしてみせた。
「少し複雑で、順を追って話したいのですが……。長くなりますけどいいですか?」
「はい、もちろんです」
宇山は目を細めて少し考え込んでから、氷が解けて色の薄くなったアイスコーヒーを横に寄せた。そして姿勢を正してから、ゆっくりとした口調で話し始めた。
「5年ほど前のことです。当時、私は東京都内の音楽教室でギターを教えていました。小さな個人経営の音楽教室です。もともと私は広告代理店で働いていたのですが、経営がうまくいかなくなってきて……何というか社内のごたごたというか……。
まあ、いろいろと困っていたところに昔の友人から連絡が来て、教室を手伝ってくれないかと言われたんです。昔やっていたギターが役に立つとは思ってなかったので、声をかけてもらったときはありがたかったです。
頃の私は、まだ海外を旅するなんて考えたこともなくて、ハワイに一度行ったことがあるくらいだし、英語もまったく話せませんでした」
恥ずかしそうに笑いながらそう話す宇山の姿をみて、塩見はまだ目の前の男が世界を旅していたことにピンとこないでいた。
塩見は早く話を進めたかったが、とりあえず宇山祐介の人となりを理解するため、話の進行を任せることにした。宇山は少し照れくさそうにしながら、ギターを教えていたという当時の音楽教室での出来事を話し始めた。