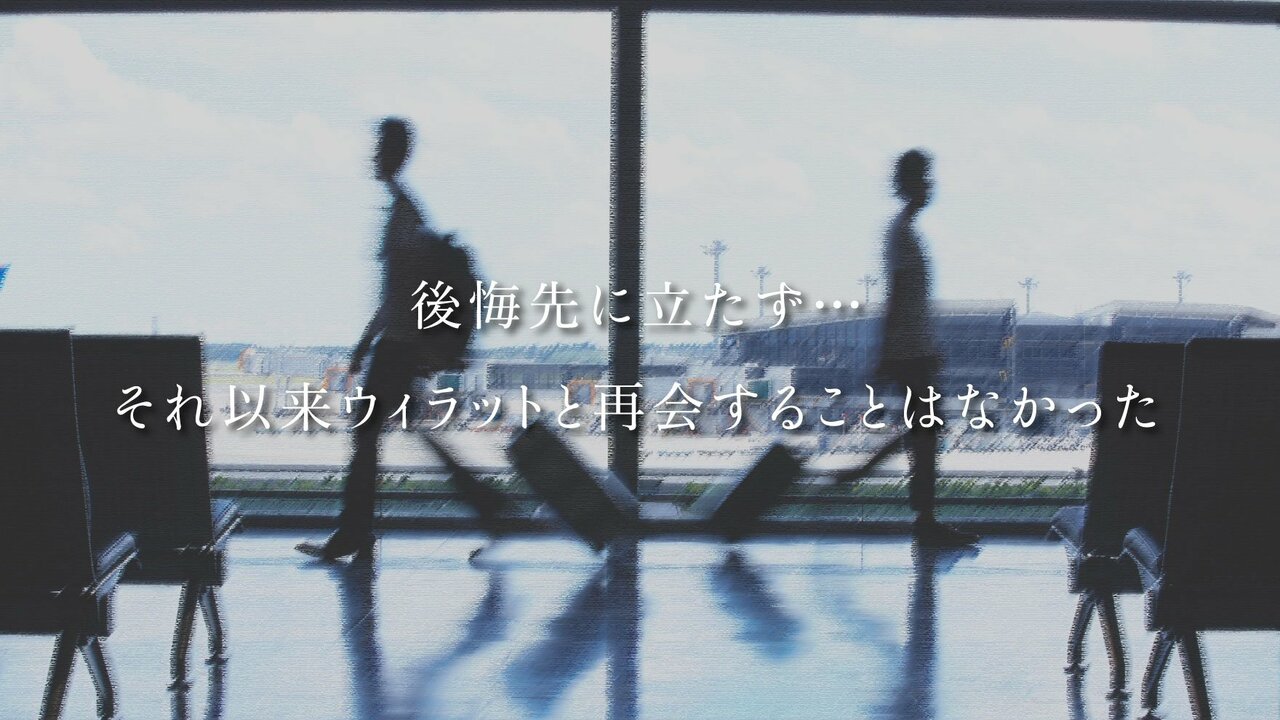ウィラットを尋ねて
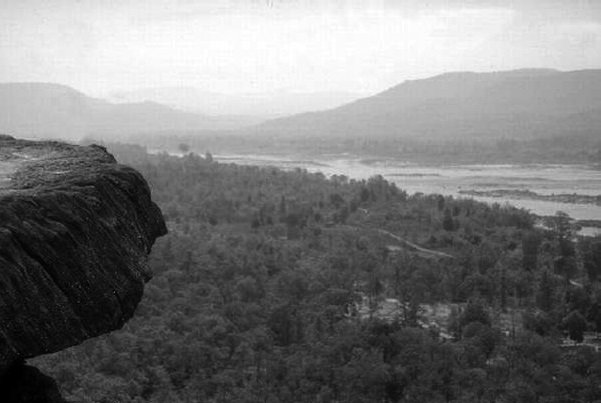
期待していなかったと言えば噓になるだろう。
でも、ひょっとしたらとの期待感は確かにあった。そして、多分その期待が大きかったぶん、期待が外れてしまった時の寂寥感はあまりにも大き過ぎた。
一九九七年二月末、ノンカーイ県、ナコンパノム県及びムクダハーン県とタイ・ラオス国境三県への出張を無事に終え、足を延ばしたのは、長い間音信の途絶えている旧友ウィラットの街、ウボンラーチャターニーであった。
ウィラット、君を訪ねてウボンの街に初めて足を踏み入れたのは、確か一九八一年だったと記憶している。
バンコクから夜行バスに乗り、約十時間かけて終点ウボンのバス停留所に着き、君の書いてくれた住所をもとに、サムロー(三輪車)でやっと君の家を探しだしたのだった。
故郷にいる君は、多くの気の置けない友人達に囲まれていたせいか、バンコクにいる時よりも遥かに元気で、そして輝いて見えた。
近くのホテルにチェックイン後、僕達は、街の前を流れるムン河の橋の横にある小さな波止場より小舟に乗り、少し離れた下流の中洲に無数に作られた小さなサーラー(東屋)の一つに入った。
東北タイの暮れなずむ黄昏時、ゆったりとした時間が流れる中、君はガイ・ヤーン(焼き鳥)やソムタム(パパイヤのなます)を肴にシンハー・ビールを飲みながら、バンコクではめったに語ることのなかった少年時代のことやウボンに住むベトナム人のこと等を語り始めた。
星降る夜の野外劇場で見た宍戸錠の演じる日本映画、実家の隣にあったキリスト教会の倉庫に忍び入りワインを盗んで友達と飲み回しぐでんぐでんに酔っ払って前後不覚となってしまったこと等、その思い出話は尽きなかった。
君がベトナム難民の子供だということは、君と知り合って少し経ってから君の方から話してくれたことだった。
それは多分、僕がタイ人ではなく、日本人であったせいなのかも知れない。ムン河の川面に夜の帳が下りる頃、僕たちは再び小舟に乗り、街に戻った。
その日の夕食は、ウィラットの家のすぐ側にあったウィラットの親類の家で、山と盛られたハーブを真ん中にしたベトナム料理のご馳走だった。
それまでにもベトナム料理を食べる機会はあったが、その時はハーブの種類の多さに圧倒させられたことを覚えている。
翌日は、ウィラットの友人の調達したピック・アップ・トラックの荷台に大勢が相乗りし、近くのゲーン(早瀬)まで水遊びに行った。ナム・トック(滝)もあるとの話に期待したが、何のことはない、浅瀬の河を横切るように高さ五十センチ程度の段差が、ナム・トックと呼ばれているだけのことであった。
ゲーンでは水浴びしたり、川魚料理を食べたりして大変楽しい夢の様な一時を過ごすことが出来た。研修先のチュラロンコーン大学における受講を無事修了し、大使館での仕事に就き始めたある日の早朝、突然ウィラットから電話があった。