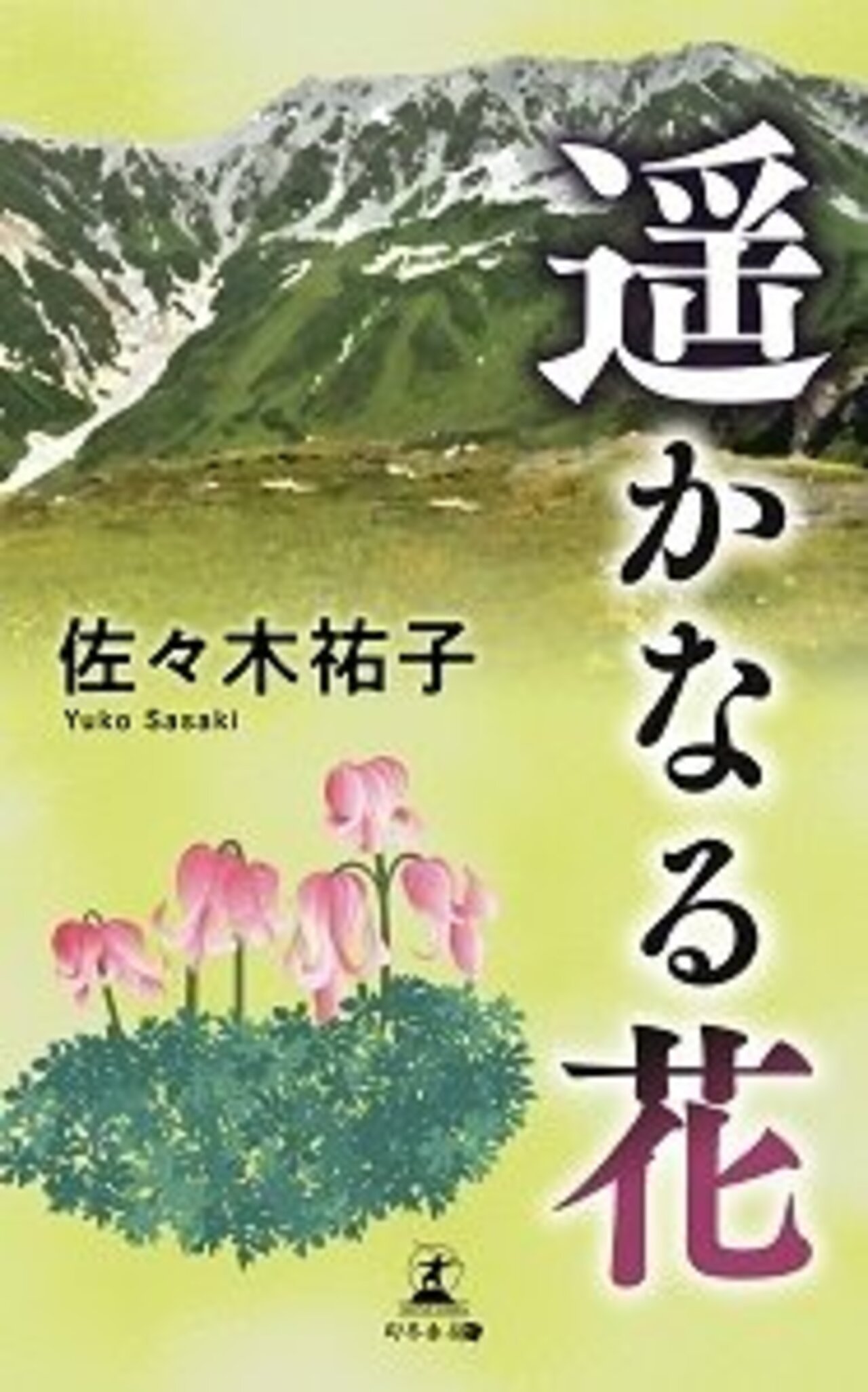深雪の返事はまたまた聡順を驚かせた。
「きっとあの子は私に似たのでございましょう」
「えっ」
聡順は思わず深雪の顔を見つめなおした。深雪は袖で恥ずかしそうに赤らんだ顔を隠しながら、
「あの、お笑いにならないで下さいませ。私小さい頃は大層なお転婆で、父も母もほとほと手を焼いたそうにございます」
「ほう…… それは初耳だな。ではいつの頃からこのように変わったのだ」
聡順は驚いて訊ねる。
「好きで変わったわけではございません。変わらざるを得なかったからでございます」
深雪の表情は、また遠い思い出をたどるような表情になった。現在の百合のように、思い切り飛び跳ねていた深雪が変わったのは、七つの頃の出来事がきっかけであった。空き屋敷に悪戯で忍び込む計画を立てた兄たちにこっそり付いて行って、そこに隠れていた二人組の盗賊に見つかって追いかけられ、兄たちと必死に屋敷に駆け戻ったのち発作で気を失った苦い経験が、深雪の脳裏に蘇った。後に医師である父に、もう少しで命を失うところであったのだと言われ、心の臓が弱いので、もう決してこのようなお転婆をしてはいけないと懇懇と諭されたのだった。そして何より気を失う前のかきむしられるような胸の苦しさを、深雪は決して忘れることはなかった。
その時の様子を話しながら、深雪は百合のお転婆を、実は自分は心の中では応援していたのではないかとふと思った。深雪には決して出来なかった子供の頃の願望を、娘にはかなえてもらいたいという思いがどこかにあったのだ。
聡順は不思議なものでも眺めるように、一時この新しい側面を吐露した妻を眺めていたが、再度うなずいて立ち上がった。
「分かった、とにかく考えてみよう」