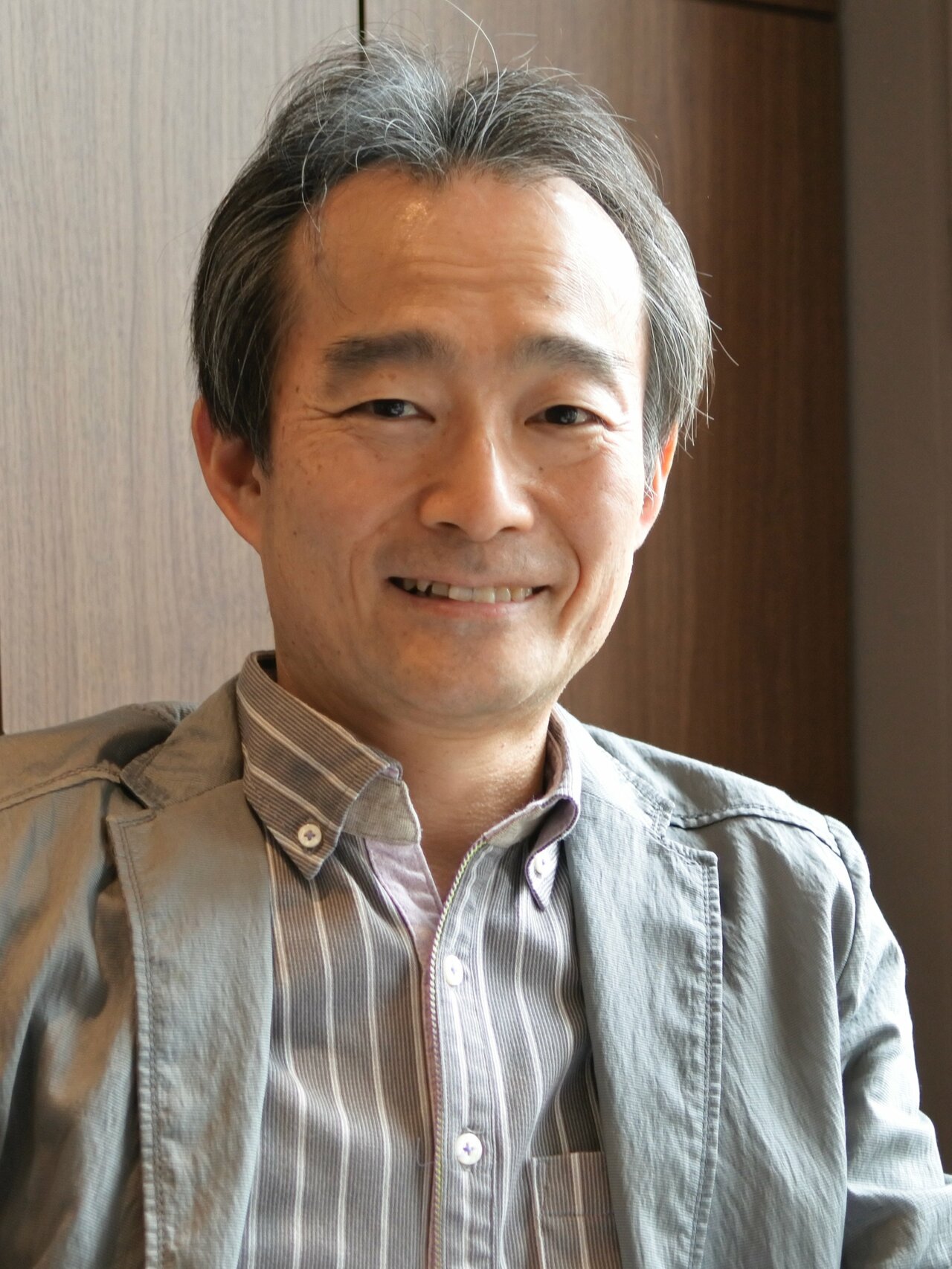なかなか古い建物で、そのうちここも解体されて新しい建物になるのだろうが、大学の財政状況によってはいつになるか分からない。旧棟の三階には他にも研究室などがあるが、使われていない部屋もいくつかあって寂れた雰囲気だ。
廊下ですれ違う人もいない。新棟から離れているため大学の喧噪とも隔絶されている。こんなところに珍しい擬態のコレクションが眠っているとすれば、少し薄気味悪いと感じる向きもあるだろう。
しかし僕にとっては涎が出るような宝の山に向かっている気分なのだ。「生物学教授室」という室名札が掛けられた、薄緑色のペンキも部分的に剥がれているような古い木の扉の中が綾子先生の部屋である。
カーテンが閉められているので、電気のスイッチを入れるまで薄暗い。すぐに電灯が点けられた。部屋に入ったところに古びたテーブルとソファがあり、そこに座るよう促された。天井まで届くほどの棚が部屋の壁一面を覆っている。
その中に標本箱らしきものや、写真などがびっしりと並べられている。
「お茶でも入れるわね」
「あ、ありがとうございます」
僕はお茶をすすった。燻したような不思議な香りの中国茶のようだった。何だか気分が落ち着く。
「ところで先生。早速ですが、棚の中にあるものは擬態昆虫の標本ですか?」
「そう。それをご覧になりに来たんですものね」
先生はそう言うといくつかの箱を取り出してきた。それらは、コノハチョウをはじめとする、見事な擬態生物の標本の数々だった。図鑑やインターネットですら、見たことも聞いたこともないような擬態生物もあった。
「先生、これも昆虫ですか? どう見てもリンゴにしか見えないのですが」
「そうね、昆虫ではないけど擬態生物よ。リンゴじゃないから食べないでね」
綾子先生でも冗談を言うんだ、と意外な気がした。もちろんそれは本当にリンゴではなく擬態生物の標本なんだろうけど。それにしてもこの部屋に入ってからの先生は、普段の冷たい雰囲気からは想像できないような優しい声で話している。
それに距離が近い。ソファの僕の隣に座って耳元で囁くように話すので、僕の耳たぶに今にも先生の唇が触れそうだ。