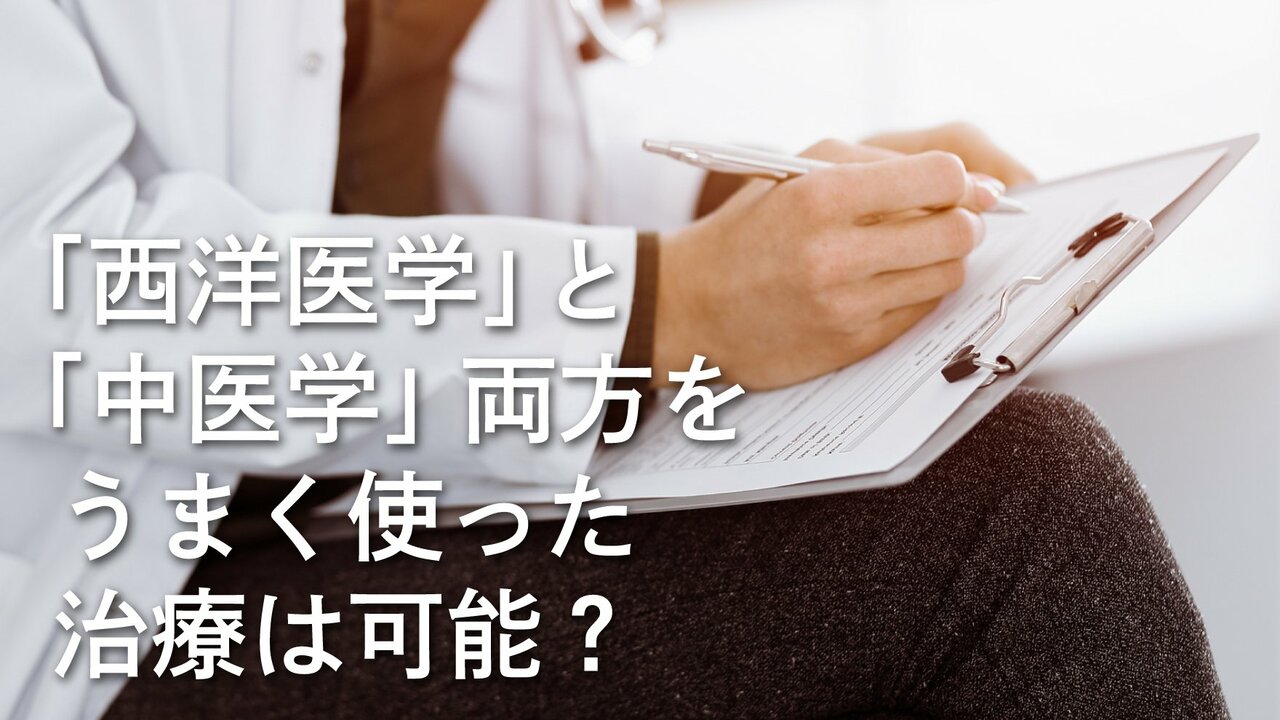彼女は制服から今の私服になり、髪型もショートに変えていたので大人な別人のようにも見えたが、くりくりした目と総じて可愛らしい面影はそのままだ。
むしろいつも自然のなすがままに委ねているような僕は、制服だろうが私服だろうがおそらく以前と変わっていない。
「京都に来てたの?」
「なんとか京史大に通りまして」
「学部は?」
「農です」
やはり同郷の人は安心するのか、高校時代にはそんなに話したことがなくても、県外で出会うとなんとはなしに気軽に話すことができる。
彼女は現役生なので、僕より一学年上になる。でもそれも関係ない。
「家近いの?」
「その通りを左に行ってすぐです」
「私は逆方向だけど、近いね」
「近いね」、
そう言われてなんだかわからないけど嬉しくなる。でも、ちょっと前には春田恵美にドキドキしたばかりなのに、全然違うタイプの木下にも同じように反応してしまうとは、と節操のない自分に呆れてしまう。
メールアドレスを交換して、「今度ご飯行こうよ」と言って別れた。
その笑顔が写真のように頭の中に焼き付けられる。なんだまったく。そして僕ごときに言ってくれたその言葉も社交辞令だろうけれど、やはり嬉しいものは嬉しいのだ。
浮かれた僕は、タイトルだけ見て新刊の文芸書を一冊買った。
でも帰り道に思う。たぶんこれはしばらく読まずに、じりじりと本棚の片隅に寄りついて落ち着くんだろうなと。
※本記事は、2020年11月刊行の書籍『桜舞う春に、きみと歩く』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。
★邪気指数、新陳代謝指数、正気指数
漢方の立場で見た、主人公沢波俊樹の体調を示します。本来、漢方にはこんな指数はありませんが、これに近いことをもっと細かく考えながら対処します。これらの変化は人によって異なります。
●邪気指数
体の中に溜まった不要なもの(邪気)の量を示す指数です。邪気は誰の体の中にもあります。食事の質や偏り、嗜好品、食べる時間などで変化しやすく、新陳代謝指数が下がり排出が悪くなることでも上昇します。邪気がかゆみの元にもなることがあります。ここでは50~150を正常範囲とします。150を超えると体調を崩しやすくなります。ただし、正気指数が高い方は、邪気指数が高くなっても体調を維持することができます。
●新陳代謝指数
体の中の、良い物(正気)、悪い物(邪気)がどれだけスムーズに動いているかを示す指数です。通常人が生きていく中で、良い物(新)を取り入れて、いらないもの(陳)を排出しています。それがスムーズに動いていること(代謝)が大切です。飲食の消化吸収、大小便での排出、血流、発汗などトータルの指数とします。運動不足やストレスなどで低下します。ここでは70~100を正常範囲とします。新陳代謝指数が下がると邪気指数が上がりやすくなり、下がっているときには正気指数も下がっていることが多くなります。
●正気指
数
体の元気(エネルギー≒正気)の指数です。バランスの良い飲食で満たされ、ほど良い休息をとることで作られます。逆にストレスや過労で低下します。正気が少なくなると、体のだるさや意欲の低下がみられ、免疫をコントロールする力が弱り、かゆみを抑えられなくなり、症状が悪化します。ここでは70~100を正常範囲とします。正気指数が高いと新陳代謝指数は上がりやすく、邪気指数が少々高くても生活に支障はありません。