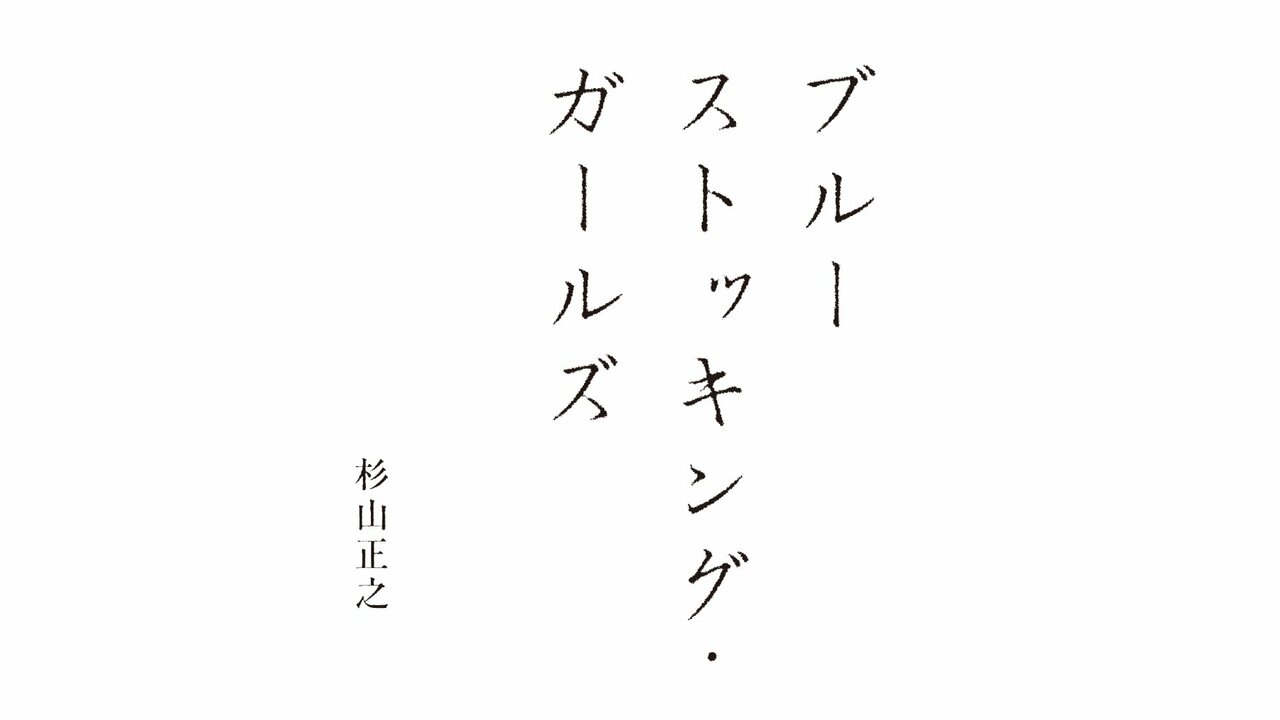第3作『山脈(やまなみ)の光』
笛吹川の向こう岸には、一面に桃色絨毯が広がっていた。甲府盆地の春は急にやって来て、この広大な桃畑から広がっていく。三月の初めには雪も降った。ちょうど卒業式だったのでよく覚えている。
田村先生の、青いボンネットに大きくHと書かれたホンダの軽トラックは、ときどき大きな音で唸り、喘いでいた。舗装が悪い所では必要以上にバウンドした。
「コウちゃん、もう少し優しく運転しろよ。おれのオブジェが壊れちゃうよ」
冬でもTシャツ一枚の顧問の田村先生は、若くて友達のようでもあり、部員たちは少しからかいの意味を込めて「コウちゃん」と呼んでいる。荷台に乗り、シートを被って隠れている村瀬が、大声でコウちゃんに訴えるが、エンジン音にかき消されそうだ。
「仕方ないだろ、道が悪いんだよ。文句があるんなら市役所に言え」
運転しているコウちゃんも負けずに大声で答える。
「こんなぼろっちい車、いいかげんに買い替えろよ」
「こいつには、愛着があるんだよ。二十年の付き合いだ。お互い離れるのがイヤなんだよ」
ぼくも、長い時間をかけた百五十号のカンバスが破れるのではないかと、気が気ではなかった。ぼくたちの高校のOBを交えた、年に一度の美術展は、春先に開催される。それが、いろいろな都合で今年は四月に入ってからになった。
ぼくは美大にすべり、浪人生としてのスタートを切る。もうひとり浪人となった園田と、東京の美大に受かった村瀬が搬入を手伝って、すでに入学の準備で甲府を離れている他の卒業生の作品を運んだ。
浪人になったぼくに、親父は極めて呑気で、
「徹の好きなようにすればいい。人生は長いんだ、三年や四年遊んでいても、飯は食わせてやるよ」
と言ってくれた。親父の言うことはありがたい。しかし浪人となったぼくには、それが厳しくも感じられる。市街の文化会館の前で、赤いダッフルコートの朱美と香子たち一年坊主が、手を振って待っていた。
「遅ーい、何してたのよー」
三年になる朱美は、今年の部長になる。
「コウちゃんの車、エンストばっかりでさ」
「グテグテ言うな、荷物を降ろすぞ」。
コウちゃんは怒って指示した。搬入口から卒業生の数十点の作品を運び入れる。こんなときは、うちの美術部員はきびきびと働く。部員の動きは作品の質と比例するものではないのだ、とシニカルに思った。
ぼくは自分の梱包を開く。こんな大きな作品は初めてだ。受験に失敗してから、美術部の部室にこもって一か月で仕上げた。
今年の二月に大雪が降った。笛吹川から御みさか坂の山麓にかけて、一面白く輝く世界が広がっていた。毎年見る風景なのに、初めて美しく感じた。
まず、古い家屋や田畑や冬枯れの桃畑を丹念に描き、その上に雪を何種類ものホワイトを使って塗り重ねた。それからペインティングナイフで、初めの風景の輪郭が判別できなくなるまで削って、荒々しい質感を表現しようと思った。
そのときの気分は受験からの一応の解放感でもあり、また逆に奇妙な充実感でもあった。根拠のない自信が湧き、今までにない最高の作品を描いている気がした。受験で自分を落とした美大すべてが愚かに思えてくる。
「こんな天才を放っておく気か」