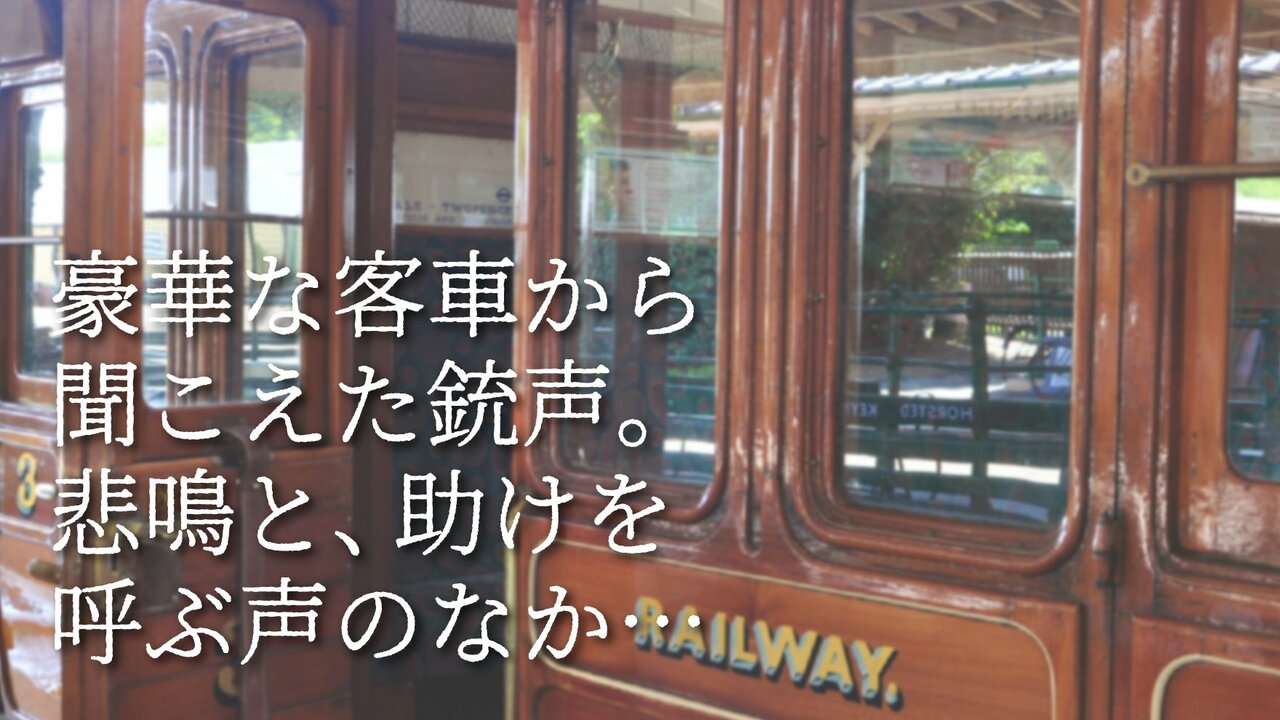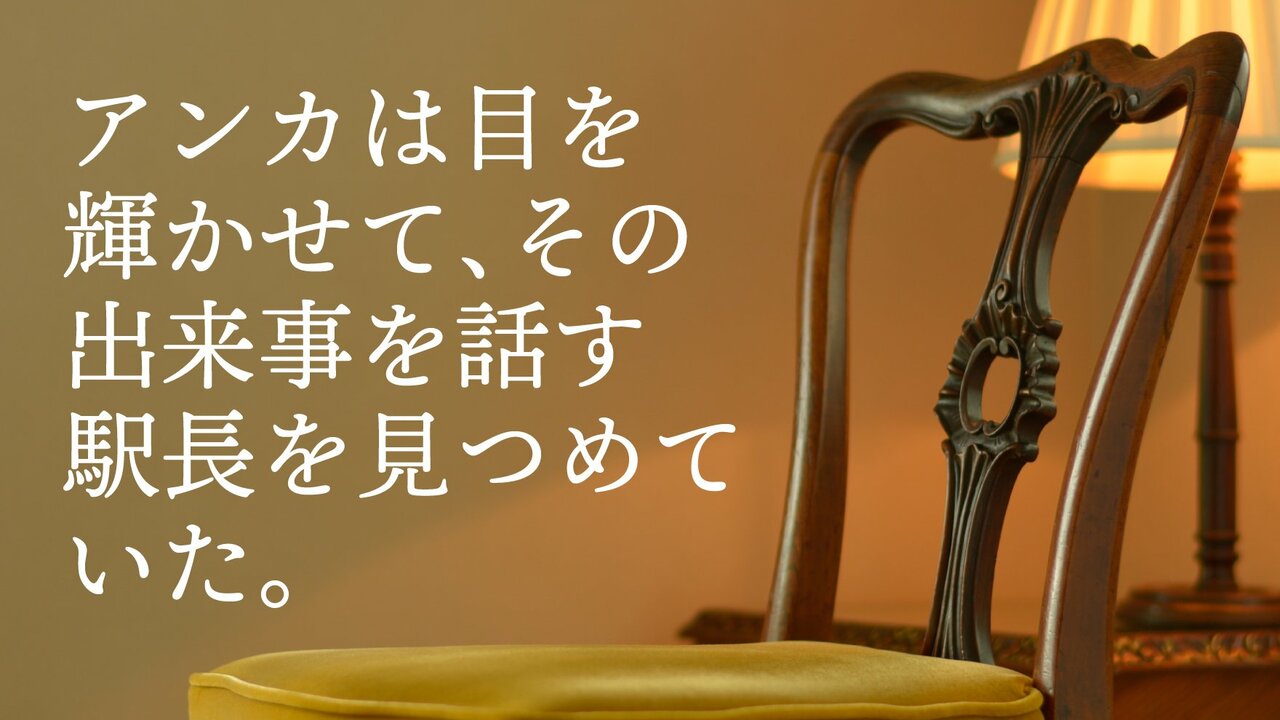アンカ・ツキチは川のほうをもう一度見る。生命を失った体は、跡形もなく姿を消していた。アンカはそれから背後に向きを変えて、まだ埃の中にあったハンドバッグを拾い上げて、鉄道線路のほうに引き返した。
レールの向こう側には、石で舗装された小さなスペースがあった。そこには、大きな防水シートでくるまれた台車と、「よろず屋ミティチ」のエンブレムがついたグラム・バーンスタインの三トントラックのニューモデルがあり、それらに近接して、テスラカーが停められていた。
アンカは素早い足取りで車にたどりついた。それは、わずか三か月前、一九一九年春に売り出されたばかりの電動式オープンカーだった。
彼女は運転席側のドアを開け、席に座った。足元にまで達するタイトなスカートをはいていたけれども、長い脚の力強い動きが妨げられることがなかったのは、隠れた長いスリットのおかげだ。尊敬すべき年長の洋裁師、アリンピェヴィチ夫人の仕立てのおかげであり、アンカはいつも夫人の技を信頼していた。
そんなわけで、時代遅れとなった内燃機関搭載車を真似て配置されたペダルを彼女は難なく操作することができた。若い女性がパネルのスイッチを押すと、電気自動車テスラカーが作動した。
バッテリーの使用可能電力量測定目盛や、スピードメーター、その他の表示器は、この世のものとは思われない仄白い照射となって、アンカの魅力的な面長の顔立ちを下から煌々と照らし出した。車のヘッドライトは、アンカの眼の前に広がる暗闇を照らした。
アンカは変速機をドライブの位置に入れて、ペダルを踏み、電力をパワーオンにすると、テスラカーは前方に滑り出す。がらんとした台地のところを蛇行し、それからサヴスカ通りに曲がる。
彼女はセニャク地区の自分の家へと急いだ。願わくば、この馬鹿げた衣服をできるだけ早く脱ぎ捨て、温かいお風呂につかり、シャンパン一本と少しばかりのアヘンを。いつものように、できるだけ早く仕事のことを忘れてしまいたかった。