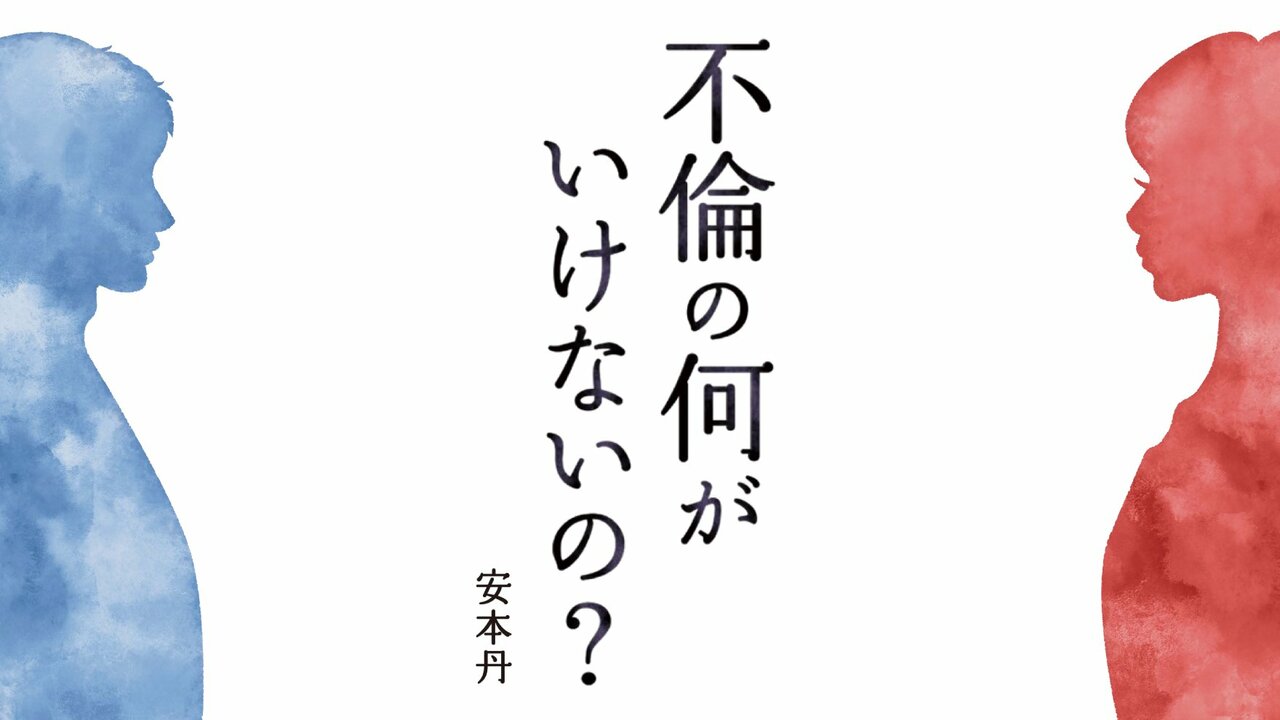第七章 子供ができるということ
うだるように暑い日だった。新幹線の指定席にようやく腰を下ろして、水筒に入った麦茶を一口飲んだ。中の氷がカランカランと涼しげな音を立てる。
夏休みを利用して私は遠方に住む母方の祖父母の家に初めて一人で遊びに行った。小学五年生の頃だ。祖父はとてもニコニコして私を迎えてくれたが、祖母の態度はどこかそっけないように感じた。
「あんたができてしまったせいで、あの子は夢を諦めなきゃいけなくなったのよ」
冷房でキンキンに冷えた部屋でアルバムをめくりながら、祖母がそう呟いた。母はピアニストを目指して芸術大学に在学していた。
念願だったプラハへの留学。私を身籠ったことが分かったのはその直前だった。
父は一流大学を卒業し商社に勤務していた。子供を堕ろさずに大学を辞めて家庭に入るという選択肢を取ったのは、母自身だった。
祖母は反対したのだと言う。母と祖母は大喧嘩し、母は半ば駆け落ちのような形で父と結婚した。
子供の私には祖母の言葉の意味がよく分からなかった。祖母の話を聞きながら、私はアルバムの中の母の顔を睨んだ。
母は結局、私を育てることを途中でやめてしまった。夢を捨てきれず、私と父を残して単身ヨーロッパへと旅立ってしまったのだ。
平生の母は厳しくて、私が菓子や玩具をねだっても滅多に買ってくれることはなかった。しかしそんな母がある日、近所のショッピングモールで私が欲しがったぬいぐるみを珍しくすんなりと買ってくれた。
当時四歳だった私と同じ背丈ほどある大きなゴマフアザラシの抱き枕だ。私はそのぬいぐるみをゴマちゃんと名付け、さっそくその日の晩から抱いて眠った。
フカフカのそれをしっかりと抱き締めて眠ったのに、朝目が覚めると、ゴマちゃんは布団から放り出されていた。「お母さん! ゴマちゃんが動いたの!」母を呼んだが返事はなかった。