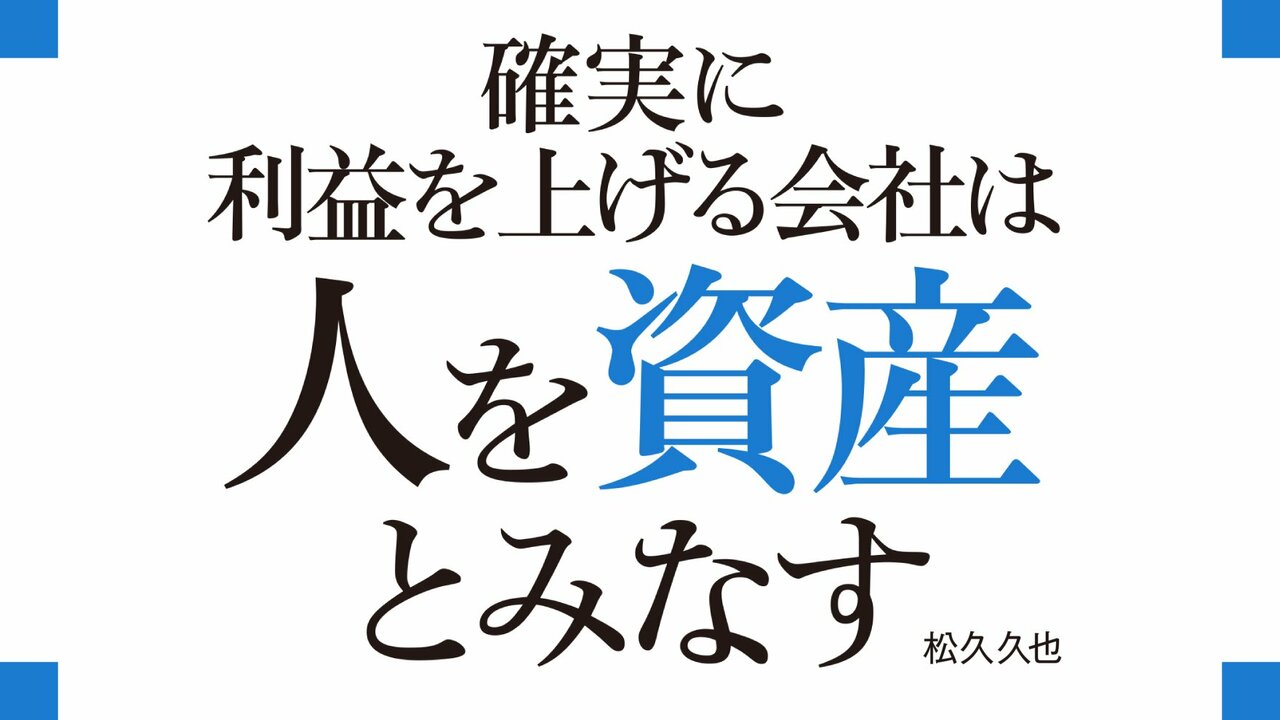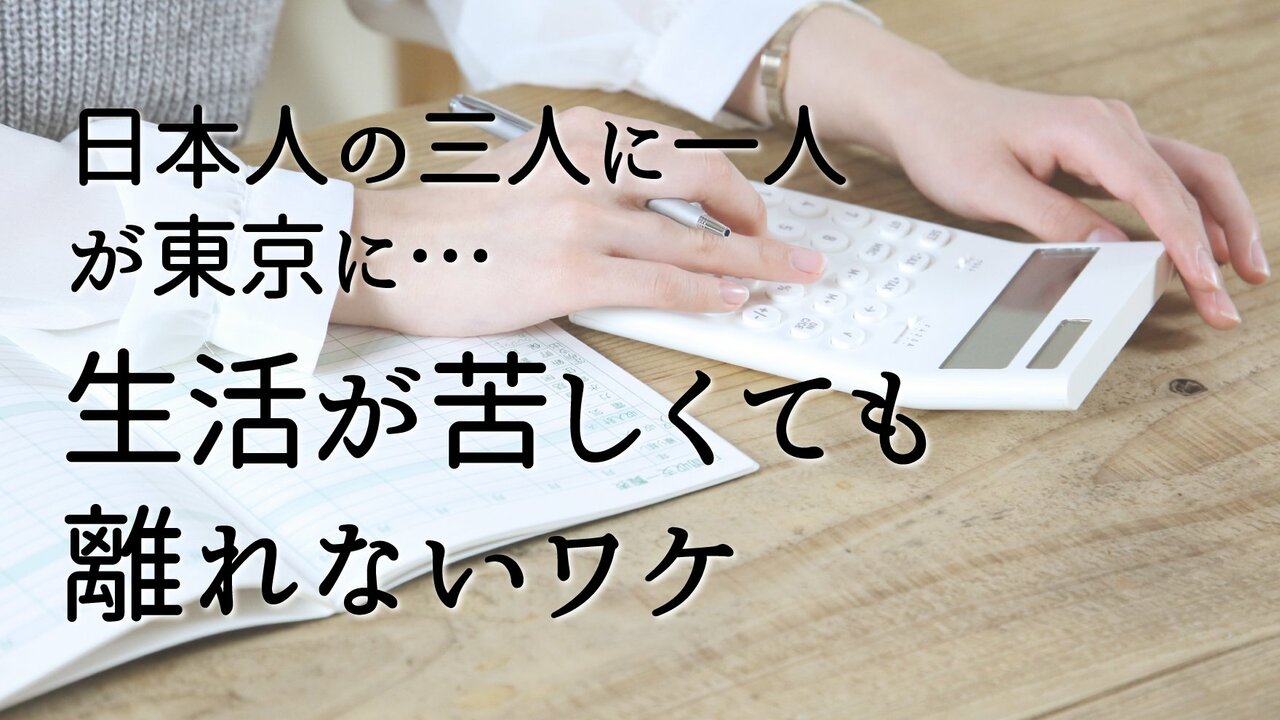第1章 日本人の精神を検証する
過去だけを語る決算書
決算期が近づきますと、経営者と税理士との話し合いの場が持たれます。1年の成果が決算書に表されます。企業が存続する限り1年ごとにその話し合いは繰り返されます。企業経営は決算書にはじまり、決算書に終わります。
決算整理を経て、1年の売上に関するさまざまな数値が確定されます。売掛金、貸倒引当金、減価償却、有価証券などの評価、特別利益、特別損失などの手続きを経て、当初想定していた予想利益が修正されます。想定利益が上下することで経営者の読みが修正され、経営者は落胆したり満足感にひたったりします。
企業の「通知表」ともいうべき決算書の扱いをめぐっては、その立場の違いから経営者と税理士の間で考え方のズレが生じることがあります。
決算書をめぐり次のような光景がよくあります。中小企業の経営者は明日を考え、税理士は過去を見つめながら話し合いをしているという姿です。この決定的な視点のズレをこれまで私はどれほど見てきたかわかりません。このズレが経営者に明日の展望を描かせることを困難にしています。
経営者は税理士が経営の内実を誰よりも知っていると思い込み、今後の展望について意見を求めようとします。しかし、税理士は税の専門家です。経営の舵取りについては専門外です。そこを問われても印象を述べるのが精一杯で、なかなか経営者の期待に応えられないのが正直なところなのです。
決算書を見つめながらも経営者の関心はすでに来期にあり、過去はもう終わったこととして捉えています。過去の決算書の分析から反省点を見つけ、来期に向けてどんな態度で臨むべきかと気持ちを切り替えているのです。
つまり決算作業にとりかかった時点で、経営者の心はすでに来期にあるのです。ところが決算書には過去の出来事が表記されているもので、そこに来期の収益予想につながるデータは存在しません。
全て結果であり、来期につながる要素が乏しく、定量的な把握ができないのです。ここに経営者と税理士の間にズレが生じる理由があります。