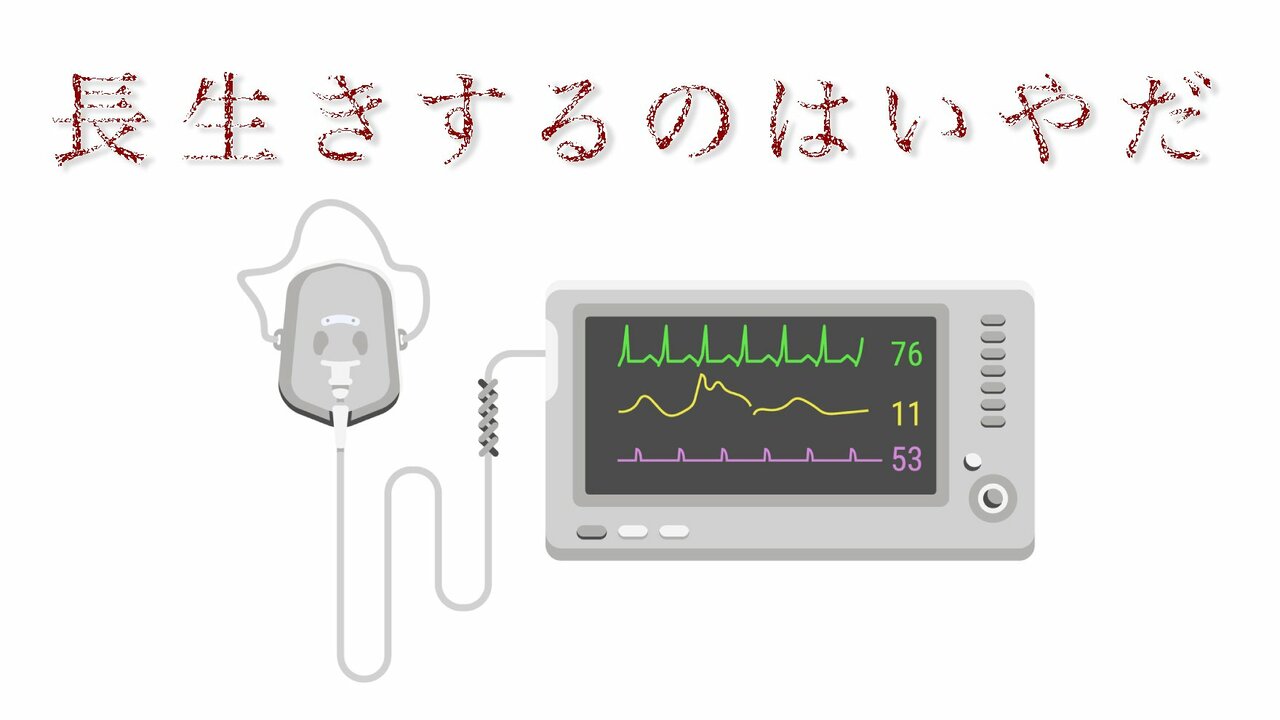天才の軌跡① フロイトの疑問
逆に、未来と現在についてフロイトはどのように感じていたのであろうか。彼のフリースへの手紙を読むと彼は生きるということについて、悲観的であったことがよくわかる。
例を挙げると、一八九三年十一月二十七日の手紙では「みじめに長生きすることは恩恵だと思いますか」と尋ね、一八九三年三月四日の手紙では「また、以前のように、今朝若死にしたいと思った」と述べ、一八九六年七月十五日の手紙では、重態であった父について「私は彼自身望んでいる報われるべき死についてねたむ気持ちはありません」と書いている。また、彼は「私の父と異腹の兄は八十一才まで生きたので、私の将来の見通しは暗い」(長生きするのはいやだ)と言ったともいわれている。
彼の母が九十五才で亡くなり、おくやみの手紙がきた時も、彼は人々が祝わないのを不思議に思うといった意味のことを言っている。彼は生きることを忌むだけでなく、死に魅せられていたとも言える。
このことは、彼がミュンヘンでユングらとの会合があった時、フロイトは気を失ったことがあるが、気がついた直後、彼は「死ぬということは何と甘美であることだろうか」と言ったという事実に明確に表れている。このエピソードは一九一二年十一月のことであるが、その前一九〇九年九月にもブレーメンでユングにワインを飲ませることに成功したあと(ユングは禁酒主義者であった)、同様に気を失っている。
この二つのエピソードはフロイト自身の解釈によると、フロイトが母親から愛を分けなければならなかった憎い弟、ジュリアスが幼児期に死亡した事実と関係があると説明している。この解釈をわかりやすくすると、ユング(十九才年下)は死亡した弟を象徴し、彼が勝つ(ミュンヘンではユングの非難を論破している)ことは、弟が死んでフロイトが潜在意識下に勝ったと思ったことのくり返しなのであるが、勝つことはフロイトが生きのびなければならないということになるので、勝った意味がない。むしろ甘美な死(気絶に象徴されている)の方がよいという意味である。