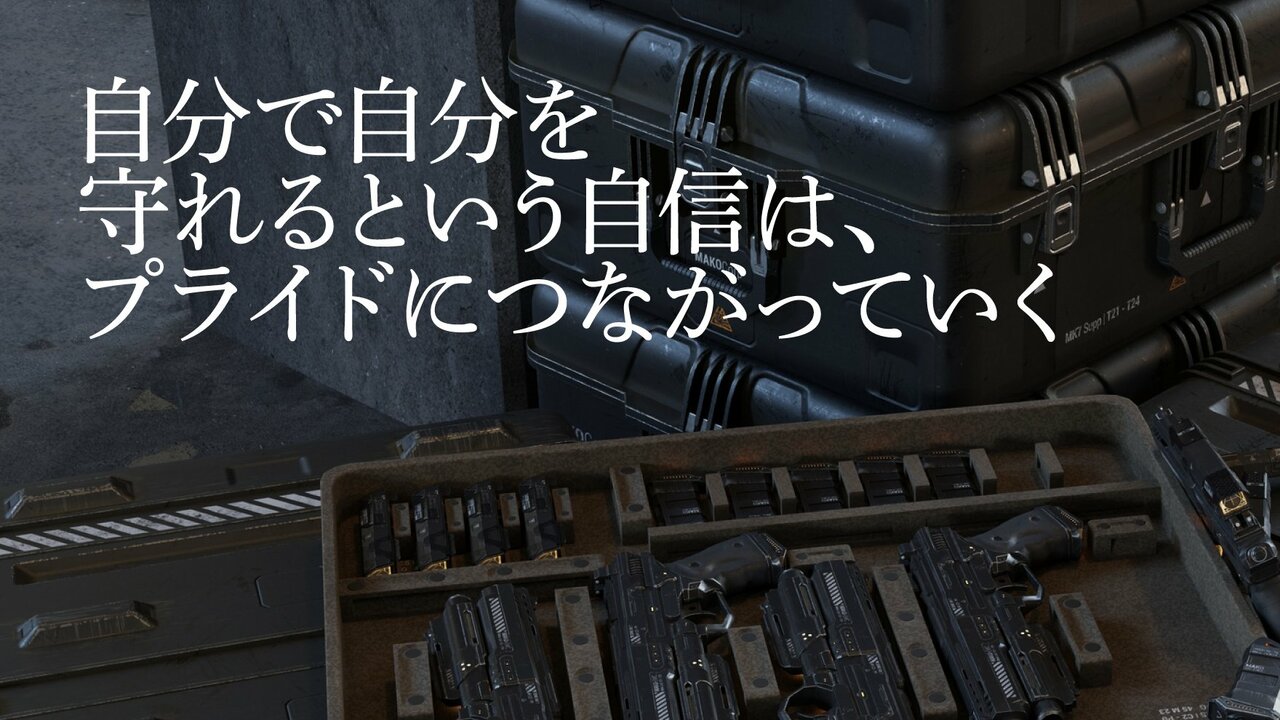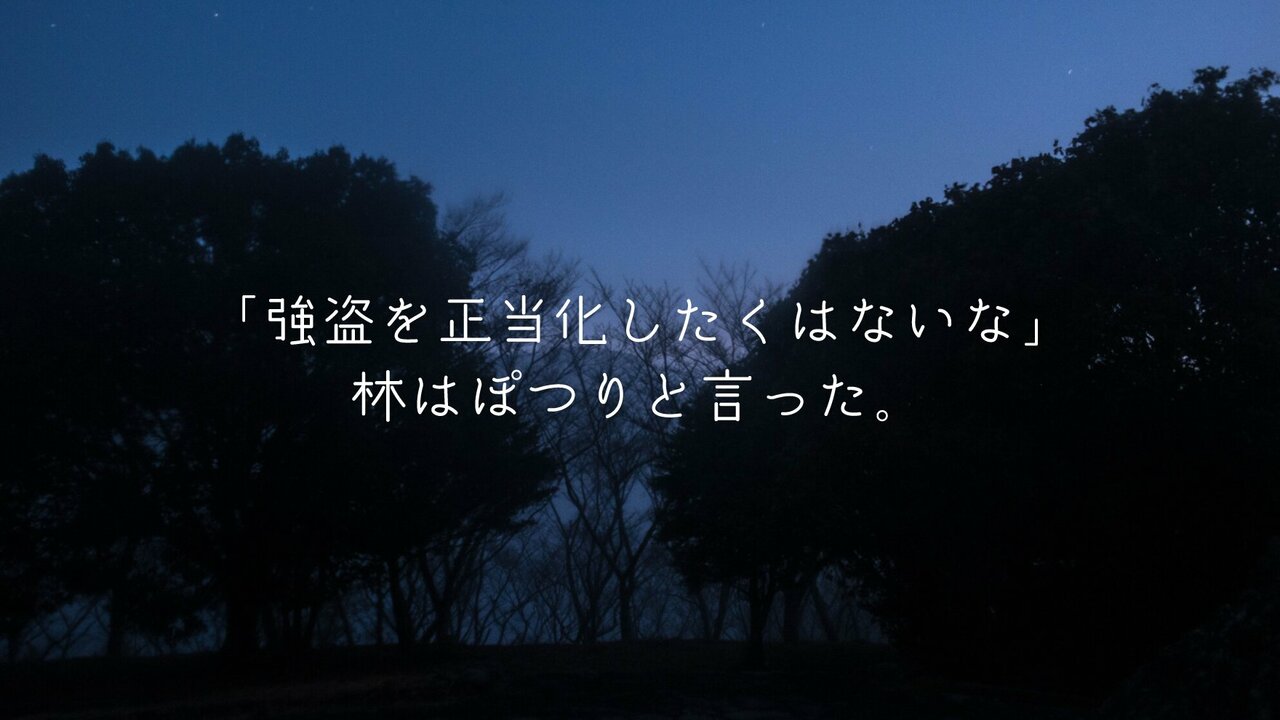Chapter1 天変地異
彼らは、笹見平観光自然公園・通称「縄文の家」にサマーキャンプにやってきた少年少女たち。大学生二十一人、中学生三十二人、総勢五十三人のチームである。
主催は都内の複数の大学のボランティアサークルからなる連合会。二十一人の大学生は、みな都内のどこかの大学のボランティアサークルに所属している。偏差値七〇を超えるエリート大学から、受ければ誰でも合格できるような大学まで様々だ。
キャンプは今回で七回目を迎える。むろん卒業や入学で人は入れ替わっているが、運営方針がきちんと引き継がれているので、毎回無事に成功をおさめてきた。
大学は引率を出さず、縄文の家も監視役を置くことはない。ほぼ学生主導でなりたっている。
ちなみに中学生は参加費無料。運営費は大学生が各自バイトをしたり寄付を募ったり、自分たちで努力して集めたお金で賄われている。そこまでして行われるキャンプとは、一体何なのか。
実は、参加の中学生はみな、自身や周辺に何らかの問題を抱えている子どもたちだった。現代社会は、六家族のうち一家族は貧困状態という悲惨な状況にある。労働者の非正規雇用や離婚率の上昇により、一般家庭の貧困化が進んでいるのである。
貧困家庭に生まれた子どもたちは、社会情勢、親の事情のしわ寄せをもろにかぶり、豊かな友達を尻目に、貧困の苦しみを味わっている。貧しさから逃れるために、万引きをしたり、性風俗に走ったり。あがけばあがくだけ泥沼に陥る。
このキャンプに集められた中学生は、そんな境遇の子どもたちばかり。その他、親がいなかったり親の虐待に遭って施設に暮らす子、いじめで学校に行けなくなった子、素行不良、孤独症、警察のご厄介に何度もなっている子――等々。
それでもこういったキャンプに参加できるくらいだから、いくらかリハビリが効いてきている子と言えなくもない。彼らは施設や保護司、学校や親類に勧められてキャンプに参加している。
大学生は、そんな中学生たちと短期間の共同体験を通じ、彼らを励まし、共に語り、共に笑い、未来に希望を持つきっかけになればと考え、このキャンプを企画運営している。実は参加大学生の多くは、中学時代にこのキャンプに参加したことがある。不遇な中学生たちの置かれた状況が痛いほどよく分かる彼らは、後輩の心の糸を少しでも解きほぐせればと、親身にボランティアに参加しているのだった。
大学生による簡単なオリエンテーションが終わった。キャンプ場広場に緩んだ空気が漂う。
「川田(かわだ)君」
いましがた全員の前でスケジュールを説明した白Tシャツの大学生が、そばにいた長髪ピアスの男子中学生に声を掛けた。
「きみ、去年も参加してくれたよね。ぼくのこと覚えてる?」
川田は細い眉をひそめた。確かに見覚えはあるが、名前は覚えていない。すると、
「林(はやし)だよ。今年も全体リーダーをやってる。よろしく」
大学生は生白い腕をぬっと差し出した。川田は握手には応えず、ほんのちょっと会釈をして目を逸らした。