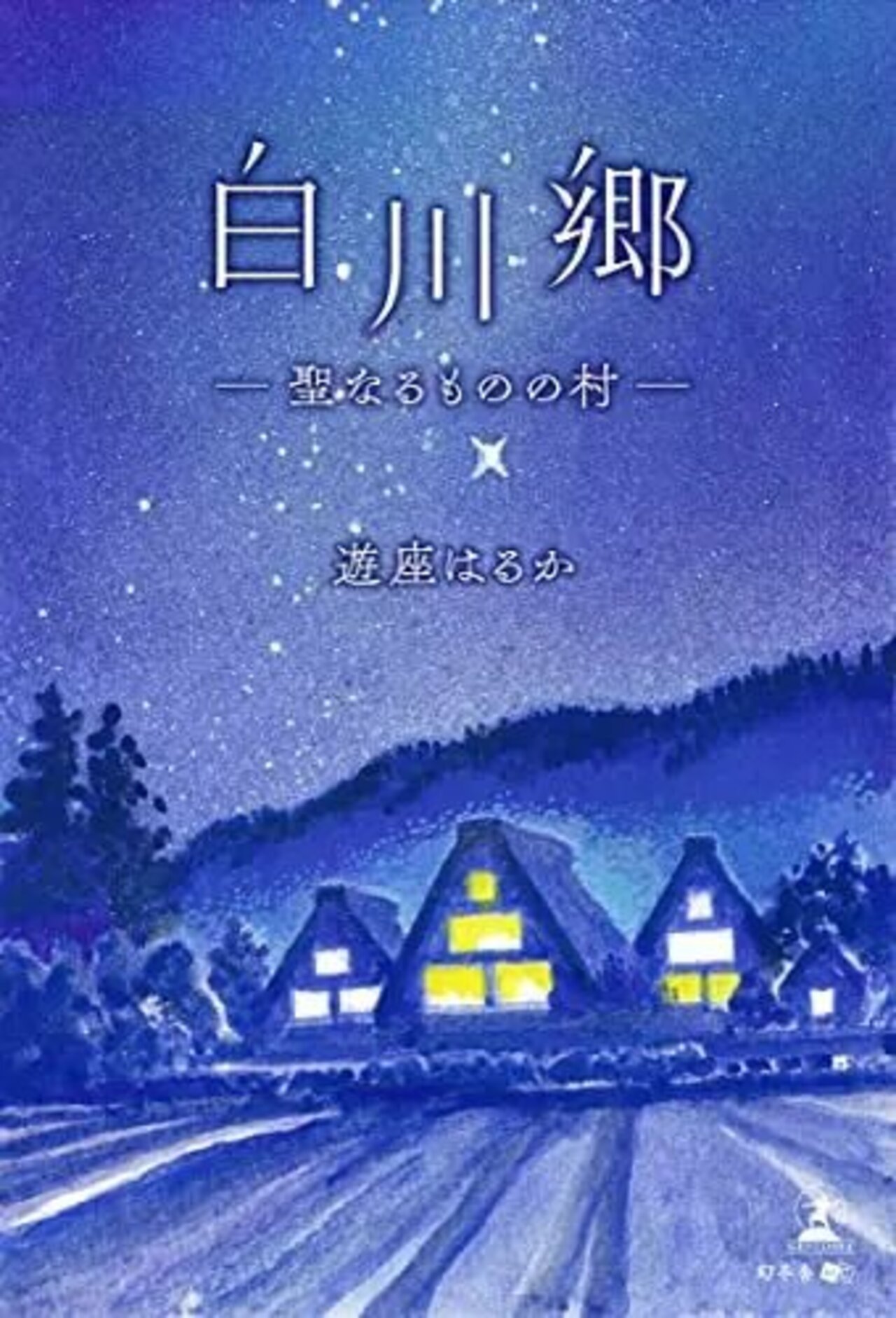第二章 飛騨の中の白川郷
4
「わたしは、子供の頃に父が亡くなったから、母と二人だけで暮らしてたの。でも母は、しっかり者でね、近所の娘さんたちにお茶やお花を教えていて、いつも家の中は賑やかで、わたしは寂しいって感じたこともなかったわ。
だから、わたしが結婚して、母は一人暮らしになったけど、何の心配もしていなかった。それに、この村で暮らし始めたのは結婚の翌年だから昭和五十一年で、ここはまだ山奥の秘境だったの。里帰りなんて簡単に出来ないし、今みたいに携帯なんてないから、嫁のわたしが東京に遠距離電話をかけるのも遠慮で、ろくに電話もかけなかった。
母からはたまにかかってきたけど、舅夫婦も見てるから、ほとんど話もしないで切ったりしてね。ある時、朝の一番忙しい時間に、母から電話がかかってきたの。いつもろくに話もしないのに、朝だから、よけいにバタバタして、母が何も言わないうちに電話を切ってしまったのよ。
そうしたらその日の夜に、警察から、母が亡くなったって連絡が来たの。心筋梗塞だった。
近所の人が庭に倒れていた母を見つけてくれたの。朝、なんか具合が悪くて、わたしに電話してきたのかもしれない。なのにわたしは、母の声もろくに聞かないで電話を切ってしまったのよ。
わたし、母に申し訳ないって思った。それに亡くなってみたら、この世で本当に甘えられたのは、母しかいなかったって、心底わかったの。
寂しくて、わたしも死にたいって思ったけど、死ねないし、村に戻るしかなかった。でも、村に戻っても、全然動けないの。ずっと部屋にこもってた。
それでも、家族は食事を持ってきてくれるし、主人も優しいしね。少しずつ、動けるようになって、ちょっと外に出てみたの。そしたら、村の人たちが、前とはガラッと変わってたの。温かくて優しくてね。
もう誰も「東京もん」なんて言わない。この村しか生きる場所がなくなったら、村の人たちだけじゃなくて、村の山や川までが、ふわっと包んでくれるみたいに優しかった。それからね、わたしと村は一つだという気持ちになったのは。
ユイも、だから、今は当たり前のこと。自分ってものが村そのものに、融けて入っている感じ」
「はあ、そうなんですか。でも、すみません、それってユイなのかなあ。村の人たちが優しいってことはわかりましたけど」
「そうか、篠原さんには、わからないか……」
「僕なりに考えたのは、秘境で外に簡単に行けないし外からの助けもないから、村の人たちだけで生きていくために、互いに助け合っていたことが、身体に染みついていったのかと。それで自己愛のスイッチが日常的に切ってあって、無償の奉仕が出来るのだと思ったのですが」
「生きていくための相互扶助、ということで納得したのね。ユイの説明は、本でもだいたい、そういうことになっているみたいね。でも、篠原さん、この村のユイは、そんなギブアンドテイクの助け合いではないのよ。白川郷のような厳しい環境だと、お互いのギブアンドテイクでは、全滅していたわ。この村のユイは、みんな一緒っていう、根っこからの優しさだけなのよ」
「はあー、わからないなあ……。すみません、やっぱり僕、わからないです」
篠原にとって、瑞江の言うこの村のユイは、まだ全然わからなかった。わからないけれど、何かとても重要なことだとは思うのだった。