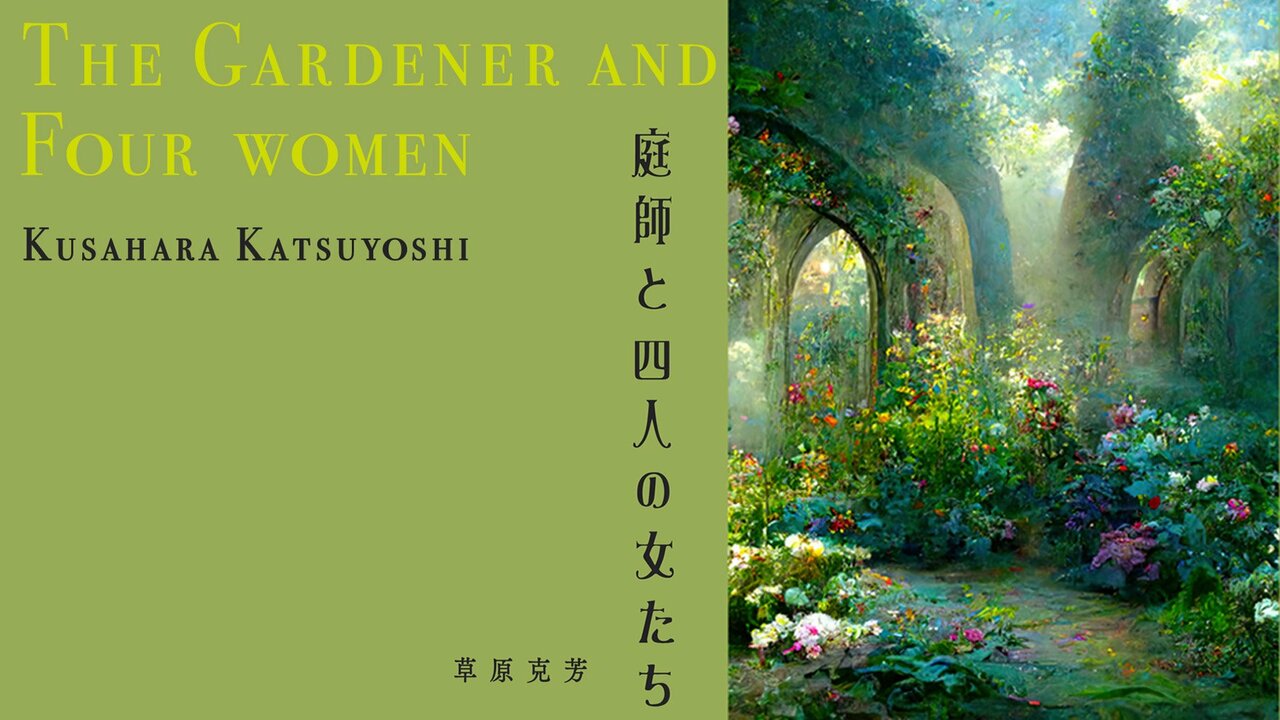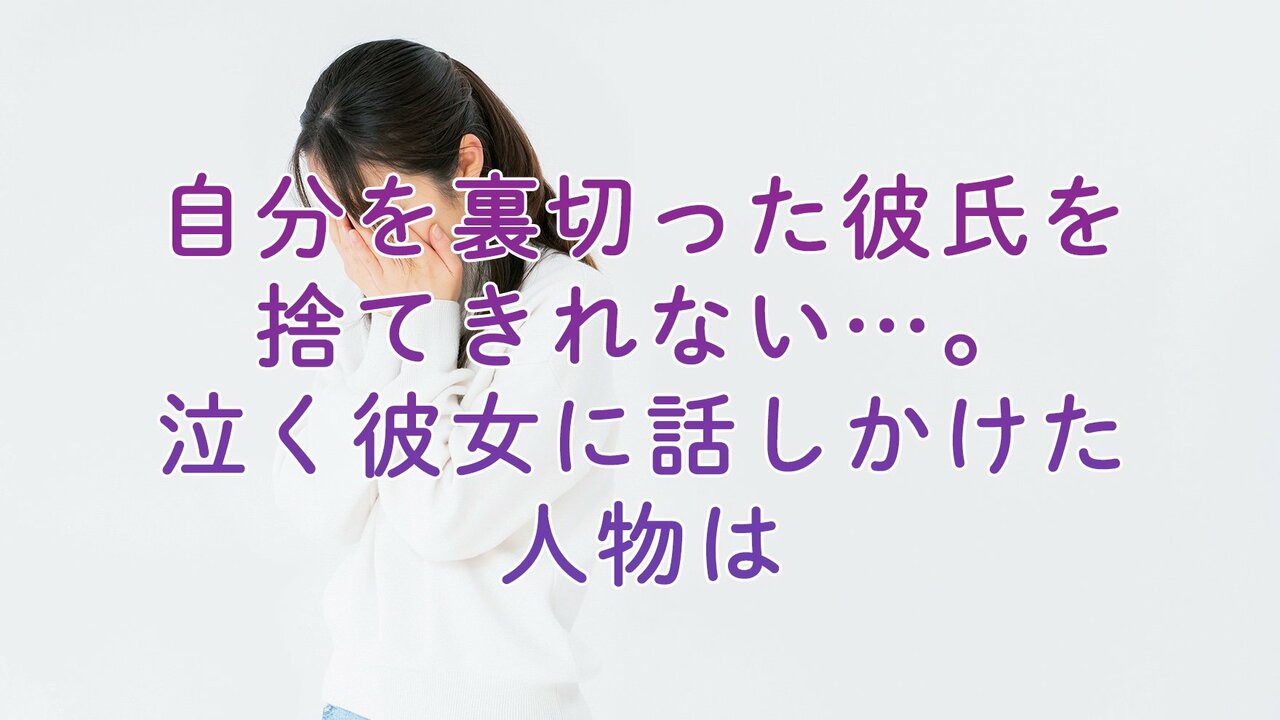庭師と四人の女たち
3
「水着なんですけど。でも、ナレーションの台詞がまだ頭に入ってないし、こんな気持ちじゃ暗記できない。どうしよう。お仕事うまくいかなくて、クビになっちゃうかも知れない。お金入んなかったら、辰郎にまた怒られちゃう」
「あらら、まだ言っている。何度も泣かされてきたくせに。もうそんな辰郎みたいな不実な男、見限っちゃいなさいよ。しょうがないじゃないの」
「しょうがないんです! だって、もうひとつの生活があったんだもの。歯ブラシも、マグカップも二つ並んで。騙されてたんだもの。もうあんな男。あたしから切ってやる――。でもどうしよう、イベントの台本、まだ何も覚えてないし」
睦子も、駄目だわこりゃ、という顔をした。
彼女にとって、いささか神経に障る「もうひとつの生活」というフレーズを、彩香が厭らしく繰り返すことに、睦子は内心苛立っていた。「ニセ仙人」との因縁のある言葉だ。
「ちッ。鬱陶しい馬鹿娘だわ、まったく」
老婆は新聞の裏に隠れて、小さく言った。「ありゃりゃあ、本丸のトヨタまで下がってる。あたしの唯一の資産の百株。また塩漬けだわよ」
「わかった、わかった。あんたね、アヤカちゃん。カルシウムが足りないのよ。神経を落ち着かせるため、ミルク入りのバナナジュースでもあげようか。それとも、玄米のフレークに牛乳をかけて……」
「ちょっと、いいかなァ?」
不意に椅子から立ち上がり、男っぽいぶっきらぼうな声でそう言ったのは、黒崎耀子であった。マス江の存在のせいで、さっきから睦子ママにまで放置状態にされていた不満が、ありありと顔に出ていた。
彼女は黒褐色のサングラスを弄びながら、眉をしかめ、
「さっき言ってたイベントって、ひょっとして『フューチャー・サニタリー・ジャパン』のことかしら」と言った。
「ええ。あの……どうして」と彩香。
「どうしてって。あたしの仕事だもん」と黒崎耀子は両手を軽く広げていった。
「ははーん、あなた、ひょっして、コンパニオンなわけ。失礼だけど、担当企業は?」
「クラリス製陶さんです。代理店は西光エージェンシーさんて聞いてますけど」
「で、所属のプロダクションは?」
「ラピスライト」
「なんだ、ラピス系列か。青柳さんのとこね。お仲間じゃん。ニシミツとも、あたしよく仕事やるんだわ。コーディネーターでね。まあ、雑用係だけど。……あたし、こういうもんなんだけど、ヨロシク」
耀子はおもむろに名刺を差し出した。
「ほら、ここのガーデンの南側のヴィラ・フローレンスの二階に住んでるのよ」
「あ、いちばん素敵なオウチですね。わたし、東側の樫の木コーポです。へえ、ご近所なんですね。じゃあ、コンパニオンさんとかの対応は?」
「それが、この、あたしなの」