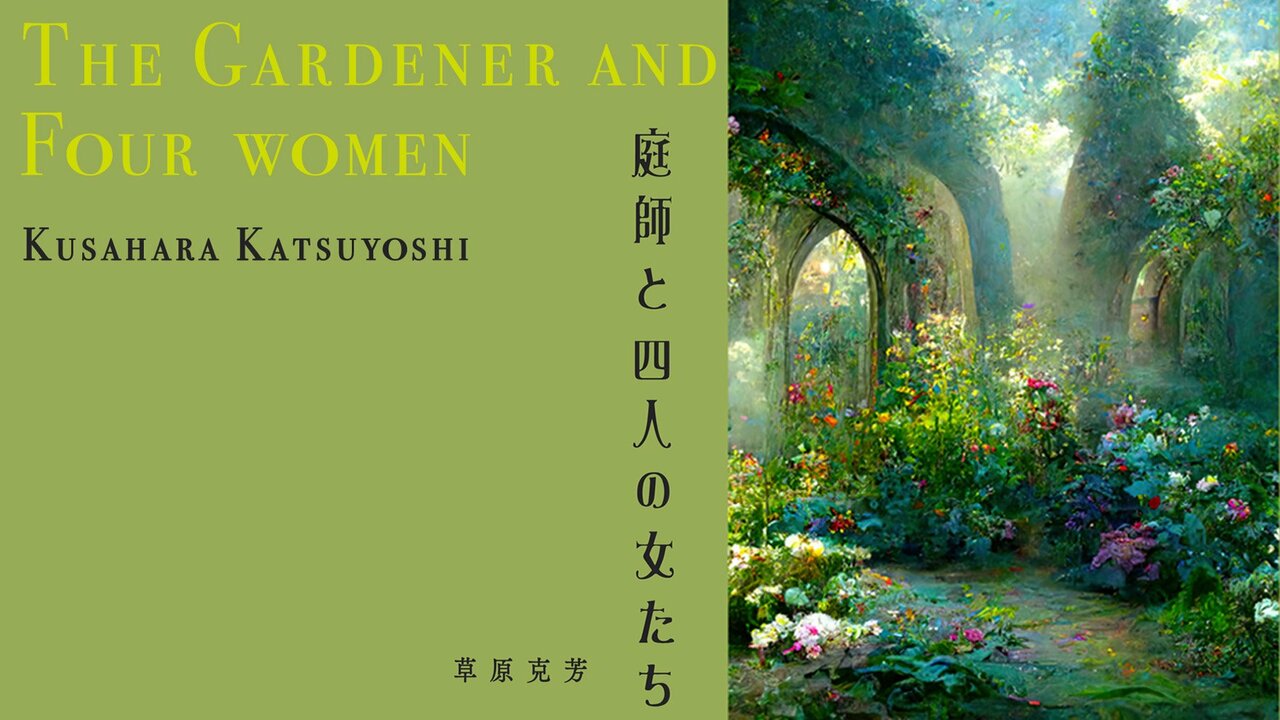庭師と四人の女たち
3
「そうそう。今度、これをよしみに、庭でバーベキューでもやりましょうよ。みんなで食材とビール持ち寄って。せっかく素敵なパティオがあるんだし」
睦子は、皆に問いかけるように、目をきらきらさせた。
タバコの煙を、フーッと横向きに吐いて、黒崎耀子は場の気配を読むような顔で腕を組んだ。
「ははん、活用できるわね、この緑のスペース」
耀子は、顎に手を当て、何か品定めのような顔つきをしている。
「それ、グッド・アイディアじゃない?」と睦子。
「この庭は、植物のフィトンチッドとマイナスイオンが豊富なのよ。だからさ、失恋なんて、たちまち治しちゃうわよ。あたし、本当を言うと、彩香ちゃんにあの彼氏、あんまりいいとは思わなかったのよ。ごめんね、あんたのこと考えて、言ってるんだからね」
少女は素直にこくりと頷いた。
「うん。それがいいわよ。バーベキューで、気分直しに、一杯やろう。アヤカ」
いつのまにやら、耀子は呼び捨てになっている。姐御風を吹かせて、ぽんと肩を叩いた。それから、なれなれしくも、相手の褐色の巻き毛を指先でいじり始めた。
さっきからしょげていた彩香は、弱々しい笑みを浮かべると、こくりと頷いた。
「だけどさ。バーベキューなんて、煙が出て大変だわ、そりゃ。あのガマガエルみたいな大家が何ていうかねぇ。なんかさ、最近、ややこしい都の条例とか、あるんじゃないのかい」
袋田マス江が、不機嫌につぶやいた。
「別にいいわよぅ、参加しなくても」と悪戯っぽく睦子。「生協で三元豚の美味しいお肉、選んでくるけどさ。契約農家の健康な食材よ」
マス江は「なァに、そう言ってみただけだよ。だからさ。その、全員参加が義務なんじゃ、仕方ないだろ、地域住民としては」と、つまらなそうに下唇を突き出した。
しぶしぶといった顔をしながら参加する気は満々のようであった。三人は目配せして笑った。
――そこで電話が鳴った。