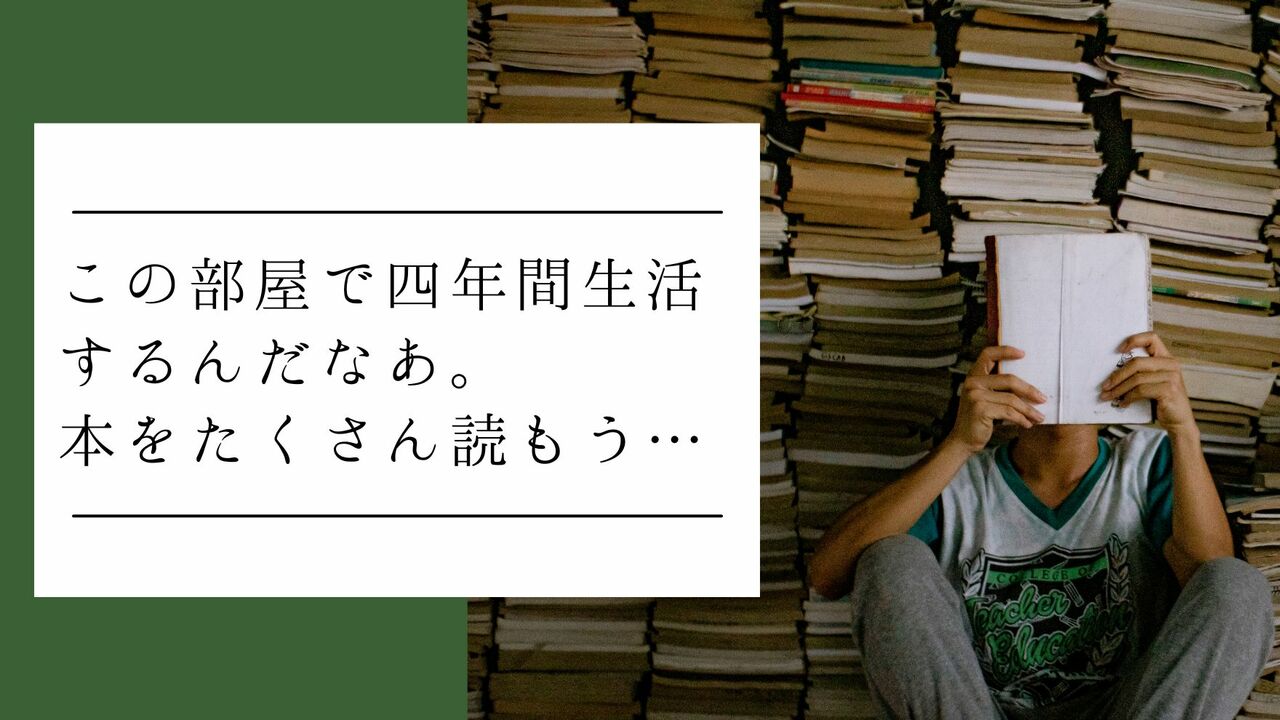一
「あいつの前歯は全部入れ歯やで」
おっちゃんは店から出て行く男を、うすら笑みを浮かべながら見送る。
夏生はおっちゃんから窓の方に目を移した。窓の外側にはアルミ製の格子が設えてある。その格子の間に男が見えた。格子と格子の間に、歩く男の顔が見えたり消えたりする。
一間あるガラス窓の左端から男が消えようとする直前、男がこちらを見た。太い眉のすぐ下にある大きな目が夏生を見た。目が合った瞬間、肩を掴まれるような圧迫感が夏生を押した。
西側の入り口と窓から昼過ぎの陽光が入ってくる。それに照らされ艶々と光った白く太い腕を組み直し、自分の前歯を爪で叩きながらおっちゃんが言う。
「あいつは組に入った当時、兄貴分に前歯折られてなあ。ほれから何年や。少しは組で働けるようになったんやろ。いつの間にか、前歯が生えとった。真っ白い前歯や」
時計は午後二時半だ。夏生がアルバイト生として勤める天国飯店には、客は誰もいない。十分ほど前に前歯の男がやって来て
「兄ちゃん、餃子二人前、お持ち帰りや」とカウンターに肘をつくなり言ったのだった。
「お持ち帰り」やと? 俺に持って帰れっちゅうのんか、この兄ィは。我が身が持って帰るんなら「持ち帰り」やろ。夏生は前歯の言葉遣いに嫌悪を感じる。
「餃子二人前。持ち帰り!」
夏生が注文承りの声を上げる。
「餃子二人前、お持ち帰り」
おっちゃんの復唱が聞こえた。
夏生が上洛した四月六日は初夏を思わせる陽気だった。一人で下宿生活をしながら大学に通う。家財道具は布団が一組と座机、あとは着替えや鍋や茶碗などが入った段ボール箱が一つ。父親が運転する軽トラックの荷台に乗せて京都まで運んだ。
道中、学生用の下宿斡旋業者に立ち寄り、手頃な部屋を物色した。運よく六畳間が見つかった。家賃は月二万円。決して高くはないという。その下宿は、大学からもさして遠くない大将軍にあった。
近くにあるラーメン屋で遅い昼食をとり、「火事だけは出すな」と一声かけて父親は軽トラックで帰っていった。トラックが左折して西大路通りに消えると、夏生はカンカンと鉄製の階段を上って、自分の部屋に向かった。