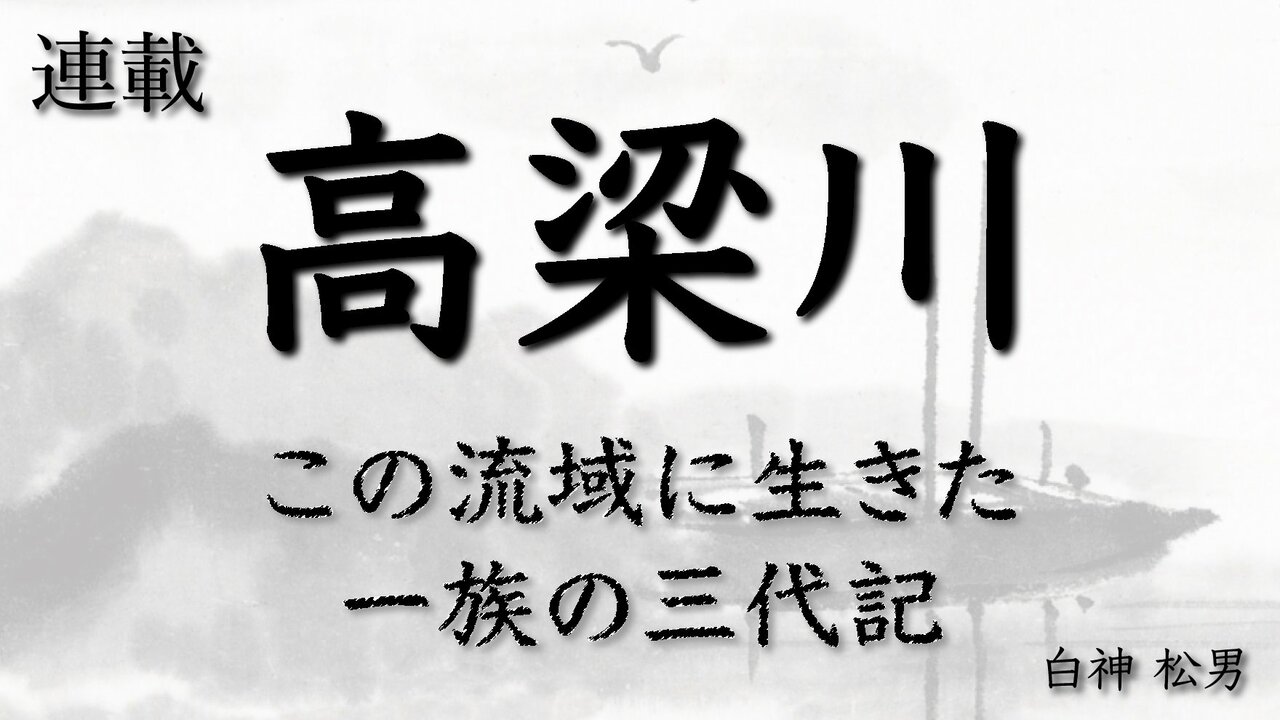第一部
七
やがて、一般的なお産の筋書き通りに陣痛はしだいに強さを増してきた。周期的に起きてくる痛みに合わせて半も力をこめてきばる。その都度痛みに顔がゆがみ苦悶にあえぐ。しかし、やはり、高齢であるためかその力が弱いからか、胎児はおもったほど降りてこない。
そうこうしている内に、夜半が過ぎ午前一時、二時と時は過ぎていく。何度も強い痛みが来るがしばらくすると和らぐ。その繰り返しの連続がしばらく続く。
しかし、確実に陣痛は度合いを増し、その都度半は懸命に力をいれて力む。やがて、頭の先がのぞき始めた。
「もっと、力を入れて!」
「赤ちゃんも苦しいんだよ!」
もはや、小倉先生の言葉は荒く、半を叱り飛ばすごとき口調である。しかし、半は元々多産体質だ。幾度もお産は経験しているから、こんな時の力の入れ方も会得している。
さらに胎児の頭が出てきた。あと一息だ。産婆さんの叱咤激励の大声がひびく。そこで、最後の力をしぼると、いっきにがばっと胎児が出てきたのである。
「そら、出た。男の児だよ」
産婆さんは、手慣れた手さばきで胎児を抱え、へその緒を縛り切って、手早い処置をほどこした。
ところが、抱き上げた胎児は、なぜか泣き声を発しない。産婆さんにも民にも一瞬緊張が走った。産婆さんは、背中をポンポンと叩いた。
出産時の胎児は、のどや気管に羊水がつまっているから、早く取り除かねばならない。その手法は十分心得ているようだった。そのあとすぐに胎児は大声を発したのである。
「オギャー! オギャー!」
赤子の誕生である。産婆さんは、おもむろにたらいに張った産湯で身体を洗い清め、手拭いにくるめると民へと手渡した。それは、民の手からお母さんに見せてあげなさいという意味が込められていた。
小倉先生は、民が献身的に母親の世話をしていたことをよく知っていたのである。だから、自分より民の手で、母に見せた方がいいと考えた。
「お母ちゃん、よく見て、男の児だよ。よかったね。わたしにも、弟ができてうれしい」
そこへ、となりの部屋で、いまかいまかとやきもきして待っていた佐治衛門と度助が入ってきた。
「男の児だって、半、よくやった。それは何よりうれしい。これで世継ぎができた。この歳になってやっとできたよ」
うれしさと安堵感が混じったような佐治衛門の言葉だった。しばらく産後の処置をしていた小倉助産婦さんが隣部屋の火鉢に輪になっていた佐治衛門や民の所にやってきた。
座るとすぐにキセルを出し、たばこの葉を先につめて火鉢で火をつけて、いっきに吸いこんだのである。それからあたたかいお茶をぐいっと飲み干した。「ああ、おいしい。生き返った」といいながら、みんなの方に向かってしゃべり始めた。
「やっぱり、高齢だったから時間がかかった。以前はもっと早く済んでいたと思う。半さんは、これまでみんな軽いお産だったからな。でも、男でよかった。これでお家も安泰だよ」
「でも、これからうまいこと育てないといけんよ。これから寒い季節になるから、風邪には気をつけてな。赤子はすぐに肺炎になるから怖い。これからも民ちゃん、がんばってもらわないといけないね」
「はい、がんばります」
民は正直にこたえた。
「民ちゃんはできた子だよ。昨日から一睡もせずつきっきりでがんばったからな。こんな娘さん、ほかにはいないよ、お父さん……」
「ええ、よく分かっています。民には感謝しています」
父親は、民に向かって頭を下げた。やがて、初冬の遅い夜明けがやってきて、周りの景色がうすぼんやりと見え始めた頃、小倉先生は終い支度をはじめ、おもむろに立ち上がって別れを告げた。
「私ゃ、今日も予定日の子がいて、そちらにも行かないといけんのじゃ。まずは帰ってひと眠りしないと……。まあ、毎日もいそがしいわ」
そう言いながら、出ていったのであった。