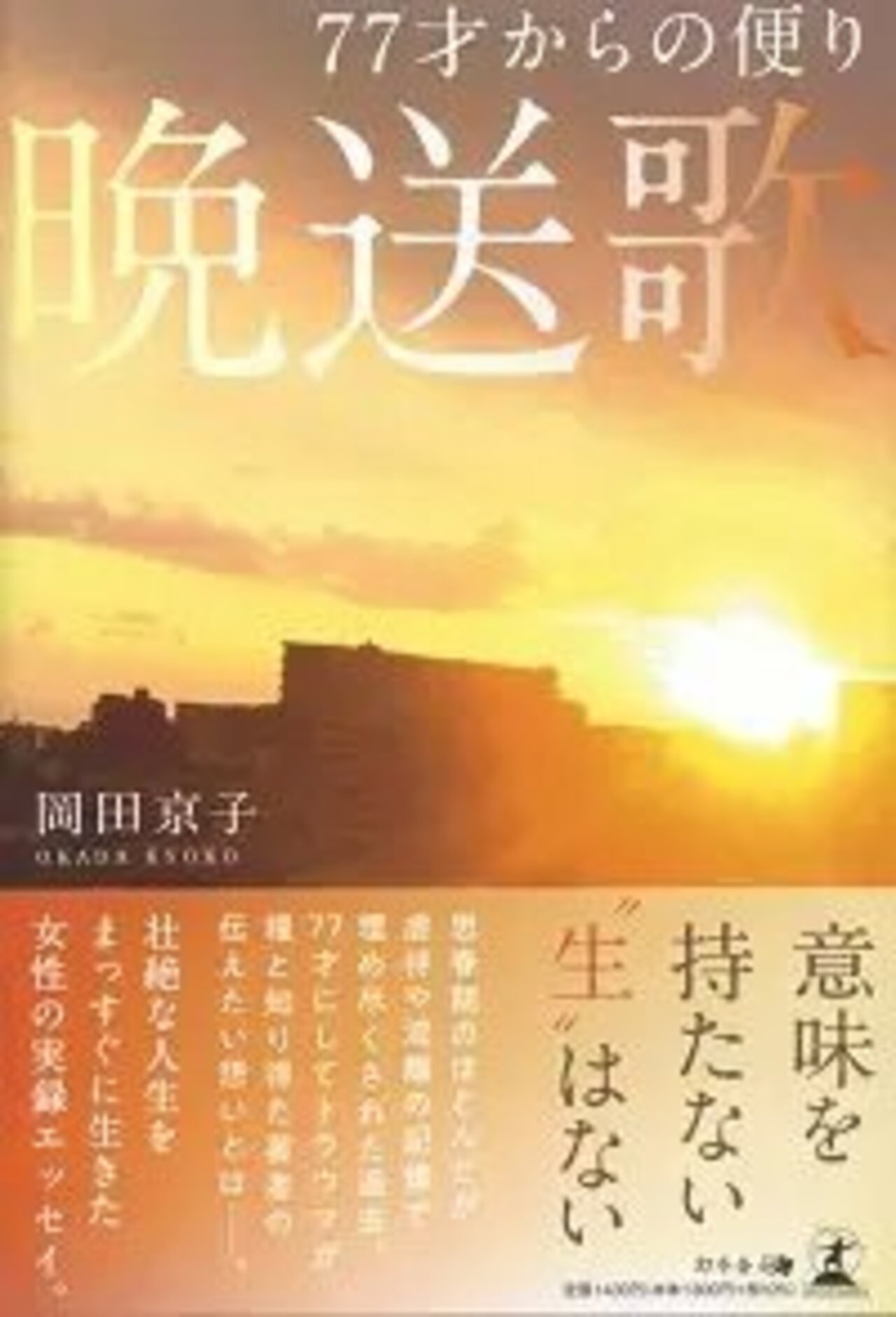彼女は38才、女になっていた。住まいが独立したのはそのせいか、男性の名は三宅さん。彼の来る日は彼女は休む、そんな自由も得られるようにもなれたらしく。時を同じくして、私の生涯を通して心に寄り添ってくれる人との出逢いが始まった。
今は95才になり足は弱っているが貧乏を貧乏と思うことなくいつ会っても少し反っ歯の口を閉じる暇なく笑っていたチャーミングな叔母さん、養母の妹で名はみどり。みどりの叔母さん、私にとってこの時からの人生、産みの母、育ての母、父の後妻、三人足してもたちうちできぬ“天使”になる。
男が来る。当時、訳はもちろん知る由もなく学校から帰るとカバンを置く間も無く、敷居をまたぐことも無く“おばちゃんとこ行って来ィ”の声で、歩いて小1時間程の彼女の家に行かされる。
そこは別世界、血のつながっていないいとこ5人が居て、もう夕暮れ時でおじさんも居て、二間と小さな裏庭を誰かれとなく右へ左へと誰もじっとしていない。相撲、プロレスその他アラカルト。私が何時、急に行っても元々の家族の様にとけこませてくれる。「セキスイ」という会社の社宅。
おばちゃんは共有の台所で料理を作り部屋に持ち帰る。私に気が付くと“美夜、来たんか”と歯をむいて笑う。半身しかないサバの煮つけを7切れのところを8切れにして、それも名人技のごとくどの部分があたっても寸分の差もなくワイワイと賑やか、それでも私は居候気分のまま同じ様には騒げず静かに食事、ここにある楽しき家族は仮の姿と思っていたらしい。
もうその頃には孤独と寂しさは私をつくりあげていた。
養母の男は変わる……そして……又、変わる、私の居場所も変わる。或る日気が付いた、お米を研いだり、飲んだりしている水は大家のかわやの手洗い水だった。
程なく引っ越す、関目と云う町の小さなアパート。何処に住もうと私には何の変わりも無く。ほの暗い場所でのほの暗い日々、それでも男性の影はカゲロウの如く垣間見え、そして何故か幸せでは無いが束の間私の心を休ませてくれた。
その余裕のせいか、学校でのいじめを知る。
でもそんなことは穏やかな春の嵐だ。