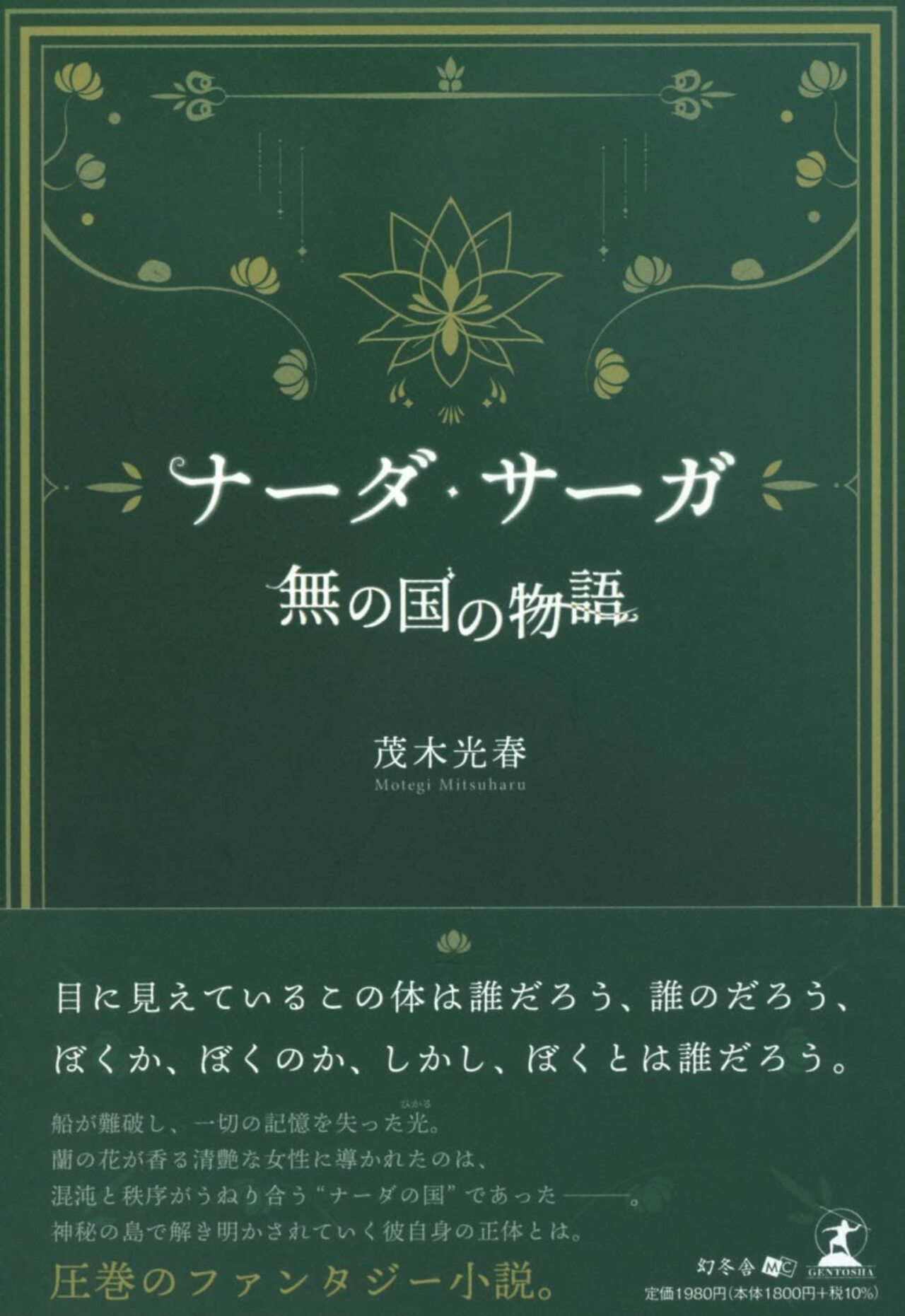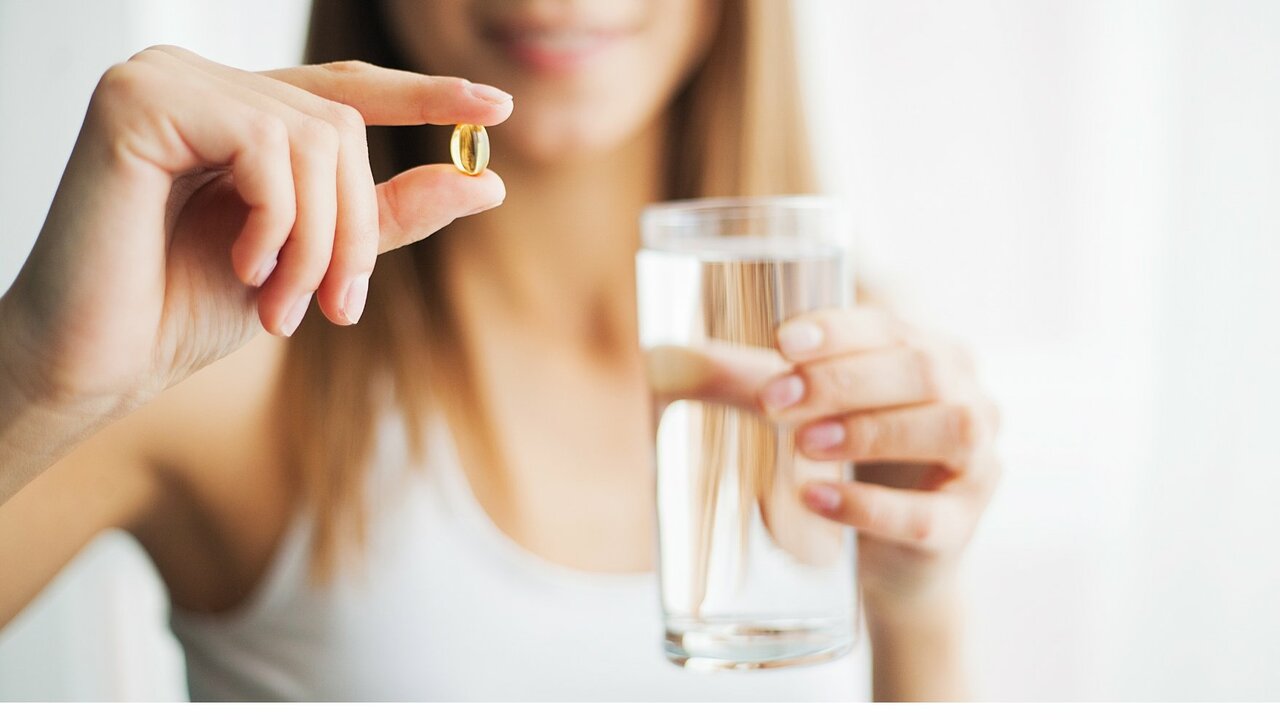少女はそう言って踵を返して背を向けると、ぼくの前をゆるりと歩き出した。かすかな蘭の花の香り、ふっとぼくを酔わせ、ぼくを狂わせるがごとき、濃密な、そしてどこか狂艶な、寄生蘭の花の香りのごときものを漂わせながら歩き出した。長い黒髪にオレンジのヘアバンドを締め、白いサーリーのごとき衣を纏い、足にはトカゲの革のサンダルを革紐をもって結わえて履き、静々と歩き始めたのである。
しかも、時に、白い衣はふとした瞬間にかすれて行き、見えなくなり、白い、すべすべと艶やかな裸体だけが浮かび上がり、やがてふっとその裸体までがかすれて行き、見えなくなって、ただ蘭の花の匂いが漂うばかり。と、また、肉体は現れ、白い衣は現れ、何事もなかったごとく、一人のサーリーを纏った少女が目の前を歩いて行くのだ。
少女は存在から半存在へ、半存在から非存在へと消えて行き、そしてまた非存在から半存在へ、半存在から存在へと現れて来る、何か絶え間ない変容のただ中にいるようだった。ぼくにそう見えているにすぎないのか、文字通りそうなのか、皆目分からない。しかも、その中にあって、蘭の花の香りだけは変わらず漂い続けているのであってみれば、もしかしたら、少女の存在そのものは蘭の花の化身か、蘭の花の精か、その絶え間ない変身か、そのいずれかもしれないと考えられたが、あくまでぼくの想像で、ただ一人の少女がいて、そこから蘭の花の香りが発散され漂い来っているにすぎないのかもしれなかった。
しかし、分からない。何もかも分からない。しかも分からないということが神秘の時間感覚の始まりであり、その世界へ入る唯一の狭き門だと少女は言った。であれば、ぼくはすでにそんな神秘世界に入っているのかもしれない。
いずれにせよ、少女がすらすらとそんな深い言葉を言ったというのは、その時十九歳の少女が言っているのではなくて、少女の不思議な言葉をもってすれば、少女の中の八十歳の老女、百八十歳の大老女がそう言い出しているのかもしれなかった。三重の年齢を生きている、三重の年齢を持っているとは不思議なことだった。