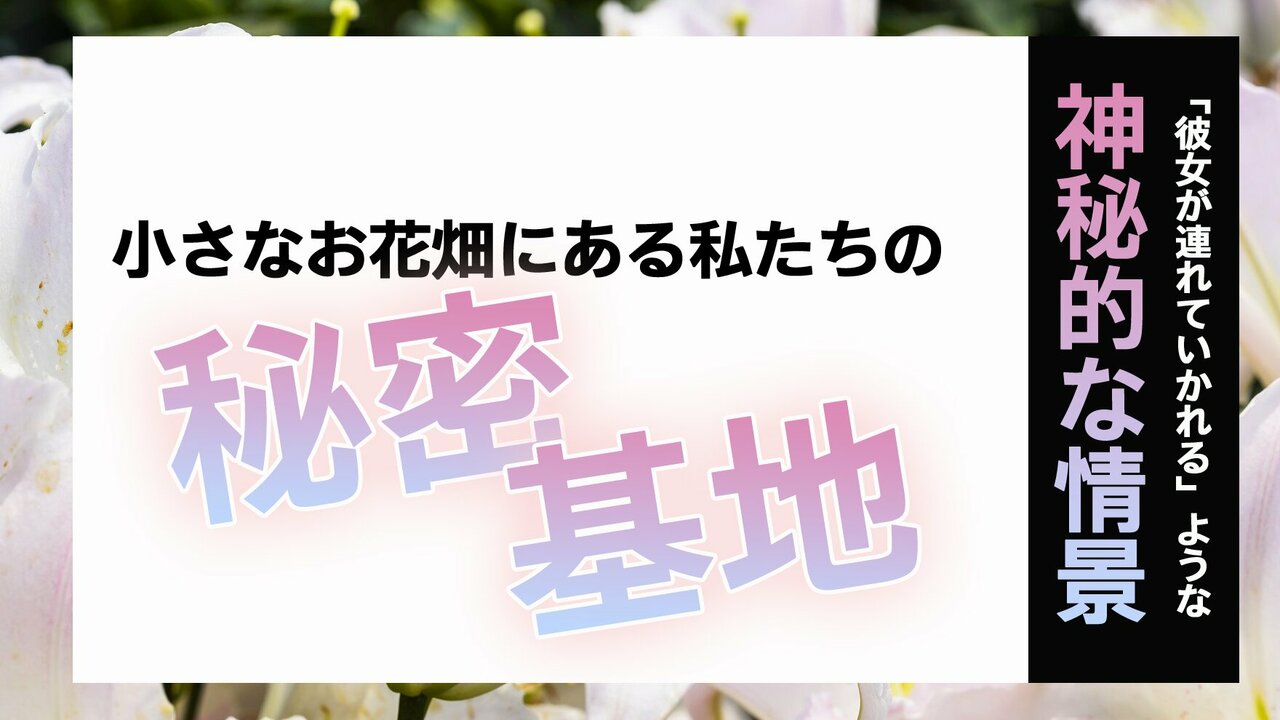背筋をほぐしてベンチから立ち上がる。一つ年上の彼女と、視線が水平になった。成長期は相手も同じこと。だけど、このままいけば、私がさよちゃんの背を追い抜く日は近いだろう。私がそんな密かな野望を抱いているなんて露とも知らず、さよちゃんが小首を傾げる。視線の角度がわずかにぶれた。
「どうかした?」
「ううん、ちょっと立ちくらみ」
「大丈夫? お茶、飲む?」
「自分の持ってる。……なんともないから、そろそろ行こうよ」
まだ午前中だというのに強い日差しが地面を焼いていた。私たちはなるべく日陰から出ないようにして駅舎の中へと入って行く。
「なんで制服?」歩きながら訊く。
「え、変かな?」さよちゃんが声をうわずらせて答えた。
「変とかじゃなくて。登校日ならわかるけど、夏休みの……なんにもない日でも学校へ行く時は制服着ていかなきゃいけないの? ってこと」
「ああ、ぜんぜん。そういう決まりはないよ。でもふつう学校へ行くときは制服じゃない? その……気分的に?」
「わからなくはないけど、まあ、さよちゃんがいいなら何も言わない」
「なぁに? 気になる言い方だなー。……あ、わかった。自分が制服じゃないから気になるんでしょ?」
「別にそういうわけじゃないし」
「ゆかちゃんけっこう他人の視線気にするタイプだもんね。でも仕方ないよー、まだ中学生なんだし、まさか中学の制服着てくるわけにも……あっ!」
ホームまで来たところで突然、さよちゃんが何かに気づいたように足を止めた。
「どうしたの?」
「自転車の鍵、掛けてないかも」
「掛けなくても大丈夫でしょ。夕方までには戻るんだし、こんな田舎でチャリ盗む人なんていないって」
「そうかなー、ゆかちゃんも掛けてこなかったの?」
「掛けた」
「もう!」
さよちゃんは持っていた通学鞄を乱暴に私へ預けると、回れ右をして改札のない無人の駅舎を小走りで抜けていった。