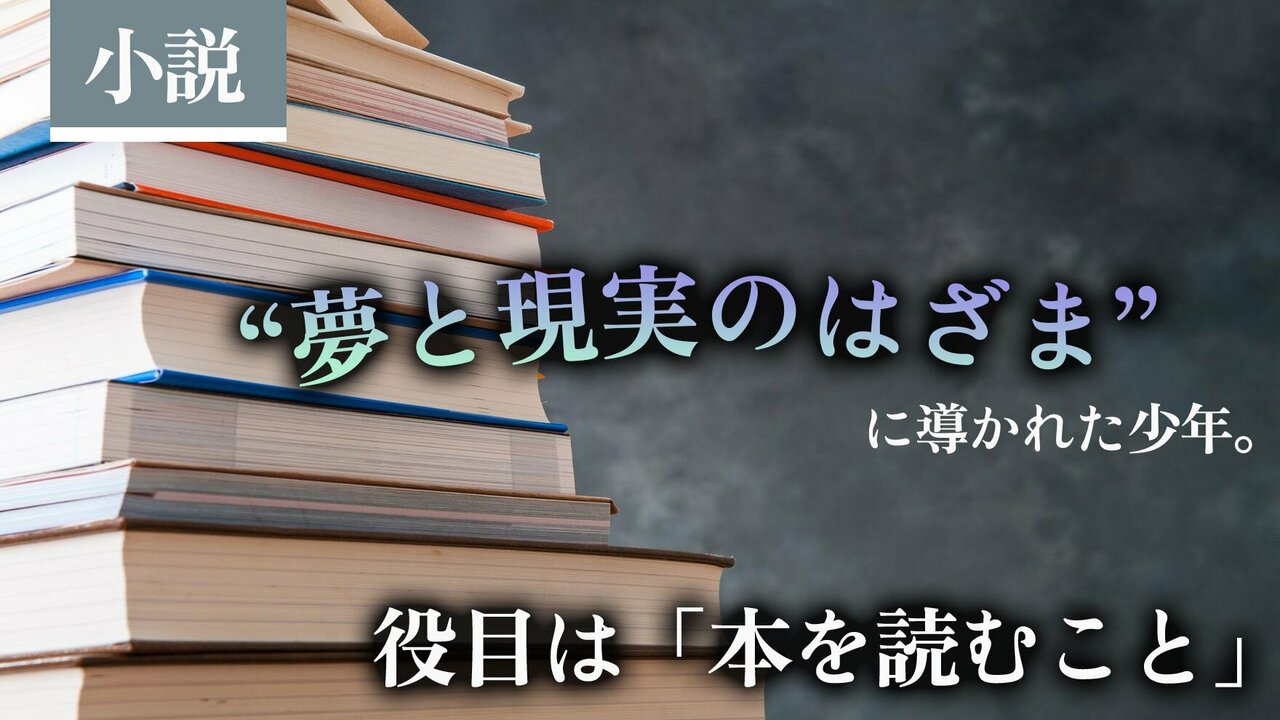おじいさんについて行くこと約二十分。あたしは、一度も足を踏み入れたことのない森の中を進んでいた。
「足下に気をつけなされ」
彼はそう言って、ランタンを揺らした。獣道を奥へ奥へと進んで行く。
「おじいさん、どこまで行くの?」
「もう少しじゃ。辛抱なされよ」
諦めて歩を進めると、目の前に洞窟が見えてきた。
「ほれ、あの奥じゃよ」彼はそう言って、躊躇うことなく洞窟へと吸い込まれていった。
「怖いけど、今更戻れないしなぁ……。仕方ない、入るぞ!」
気合いを入れて、歩を進める。人一人がやっと通れる幅を進んで行く。時々、肩や腕を擦ってしまったが、進むしかない。この暗闇では、おじいさんのランタンだけが頼りだ。どこかからサラサラと水が流れる音がするが、この暗闇では、それがどこで流れているのかわからない。ただ、向かい風が吹いていることだけは感じる。出口が近づいてきたのか、ほんのり草木の香りが鼻の周りを漂い始めた。しかし、歩けど歩けど、一向に出口は見えてこない。
「おじいさん、まだー?」
「あと少しじゃ。踏ん張りなされ」
おじいさんは、振り返らずに歩を進める。この状況では、おとなしくついて行くしか、あたしに選択肢はない。洞窟に入ってから、三十分は歩いただろうか。ようやく細い一筋の光が見えてきた。
「やっと着いた……」
言葉を漏らしながら、洞窟を出る。すると、あたしの目を、容赦ない光が攻撃してきた。思わず目を閉じて、目を光に慣らすことに専念する。思わぬ眩しさに、涙が出てきた。
「おじいさん。申し訳ないけど、少し待ってくれない? 目が辛くて……」
あたしは涙をぼろぼろと流しながら、前方に顔を向けた。
「おやおや。これは、少し休むしかなさそうじゃの。あと少しじゃが、仕方がないのう……」
彼の言葉を聞きながら、いつものごとく光からの攻撃にひたすら耐える。なぜか、いつも暗がりから一気に明るい場所に出ると、こうなってしまう。普段暗がりにいるわけではないのに。出かける時は、サングラス必須だ。
しかし、まさか洞窟の外がこんなにも明るいとは思わなかった。だって、洞窟に入る前は星空の下にいたのだから。明るいはずがない。こういう時に限ってサングラスがないため、眩しさにひたすらに涙を流す。