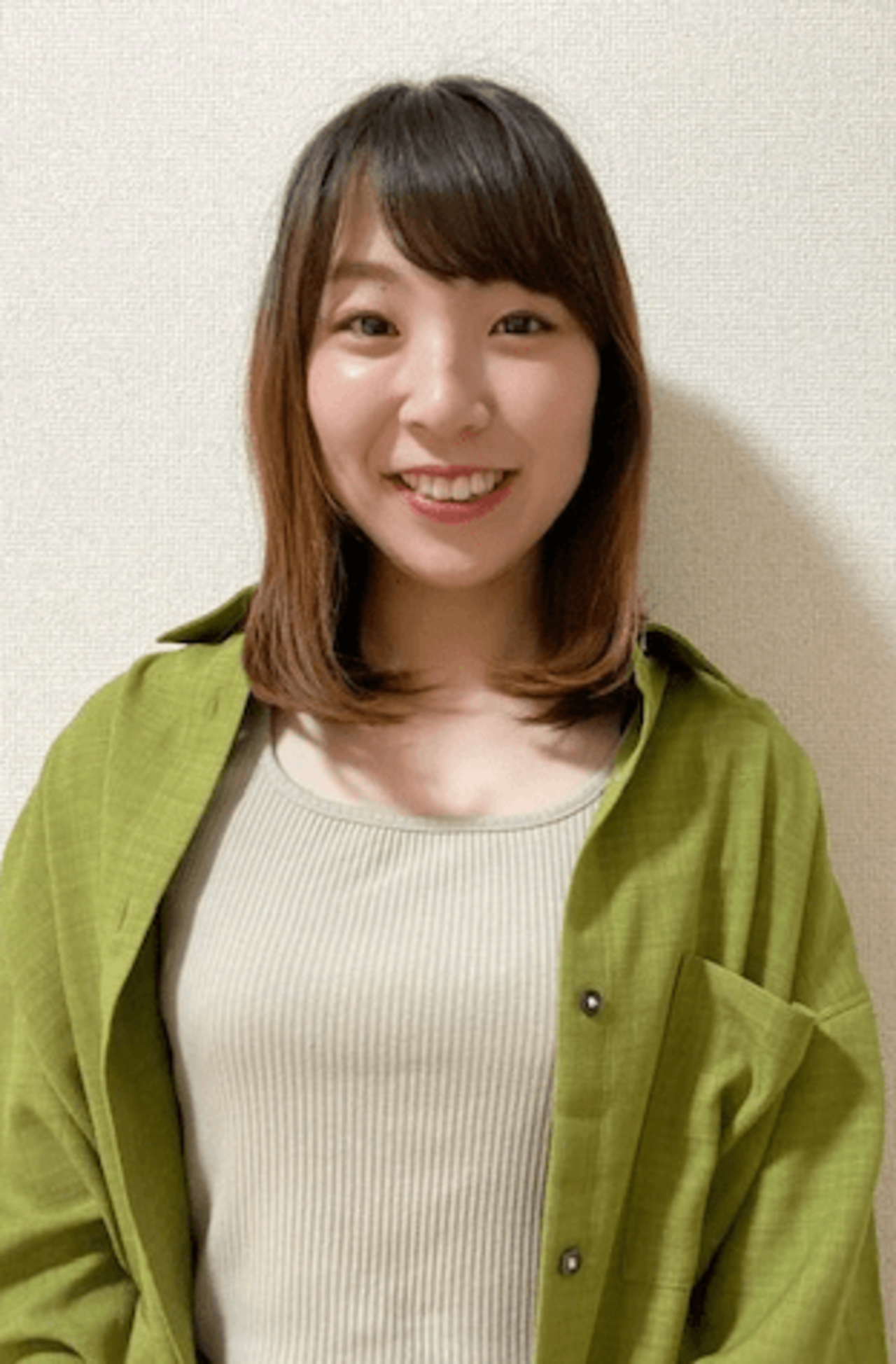「もういい! 」
そう言って家を飛び出してしまった。素直になれない私も、お母さんなのにそれに気づいてくれないお母さんも大嫌いだ。家の横の細い路地を通り抜けしばらく歩き、道路に出ると向かい側にバス停が見えた。〝あのバスに乗ってどこかへ行ってしまおう〟
携帯の電源を切ってお母さんに探されないように。このまま帰らなくてもいいや。次に来たバスに乗ろう。そう決めてバス停で待っていると、
「りんちゃん! 」
とどこからか声が聞こえた。辺りをうかがうと暗い路地の向こうからばあちゃんが息を切らして走ってくるのが見えた。ばあちゃんは私を見つけるとホッとしたような、泣きそうな顔をしていた。が、私はすぐに顔をそらし気づいていないふりをした。車やバイクの重低音のうしろで「りんちゃん」という優しくて思わず泣いてしまいそうな、でもうるさいと感じるばあちゃんの声が聞こえる。二車線はさんだ道路の向こう側から何度も
「りんちゃん! ばあちゃんよ。ここよ! 」
と手を振り、叫んでいる。十回は呼んでくれただろう。でも私は気づいていないふりをして顔を少し道路に乗り出し、バスを待っている素振りを続けた。しばらくするとばあちゃんの声は聞こえなくなった。
私は気になって、顔はバス停の方を向けたまま目だけ泳がせてばあちゃんを探した。すると、ばあちゃんは向こう側の道路からこっち側に渡ってこようと、車の流れが止むタイミングをうかがっていた。しかし、車通りが多いこの道路を横断歩道なしでタイミングよく渡るのはばあちゃんにとっては大変なようで、勢いよく右足で一歩を踏み出すも次の左足が出ず、下手なステップを踏んでいるかのようだった。
このままバスが来て目の前でバスに乗ってやろう。ばあちゃんというよりもお母さんを困らせたいという思いで、私の心はどす黒く曇っていく。
ちょうどその時バスがやってくるのが見えた。視界の片隅で動くばあちゃんのステップはさっきより少し早くなった気がしたが、私はバスに乗ろうと決めていた。バスが停留所の前で停車したその時、〝パァーーーン〟と車のクラクションが鳴り響いた。私は瞬時に分かった。
「ばあちゃん! 」
心臓がバクバクし、慌てて反対車線を探すとばあちゃんが右手を上げ、止まってくれた車に何度も何度もお辞儀をしながら小走りでこちらへ渡ってくる。
「もう、危ないやろ! 」
とばあちゃんを叱りながら涙がこぼれた。そして、
「追いかけてこんでよ! 」
と言葉が出た。
違う、そうじゃない、私が言いたいのは、
〝心配かけてごめん〟〝追いかけてきてくれてありがとう〟
なのに、やっぱり違う言葉が出てきてしまった。