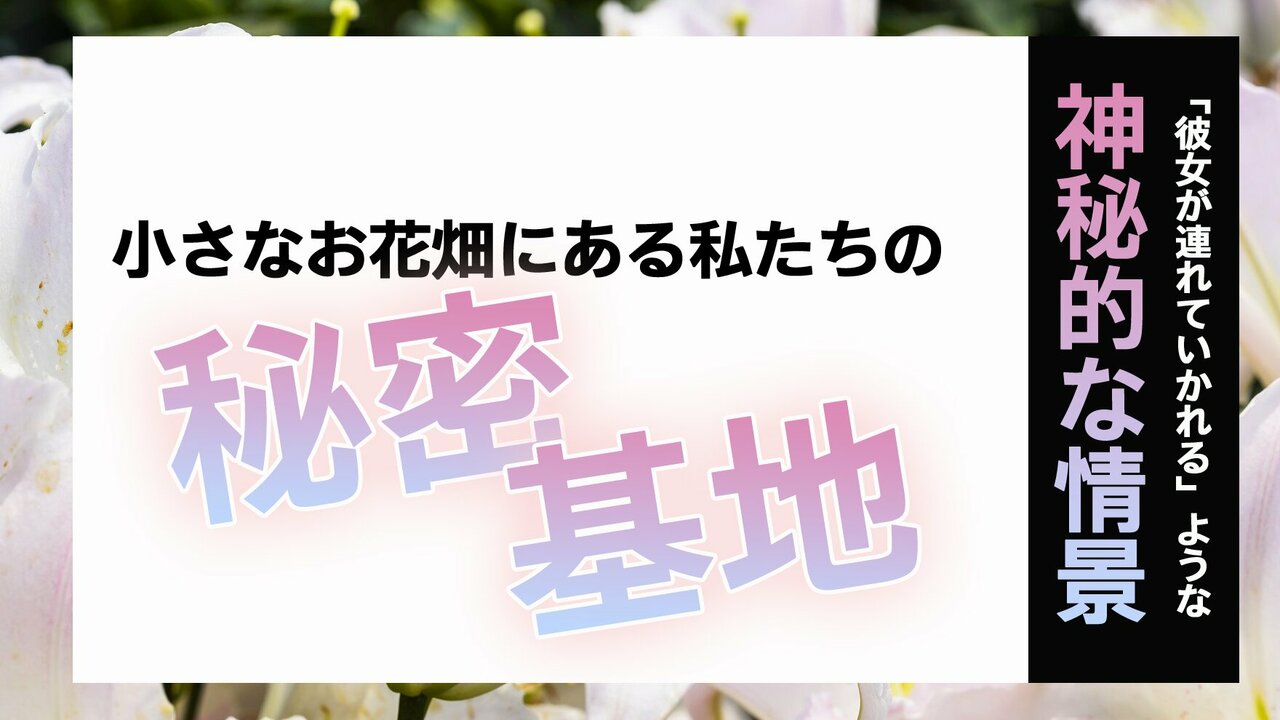1
どこかでアラームが鳴っていた。その音は最初、遠いところで小さく鳴っていただけだったけれど、すぐに近づいて来て、大きな音となり私の意識を揺さぶってくる。煩わしさを意識する前に反射的に伸ばした手は、目を閉じたままだというのに的確にスマートフォンを掴みアラームを切っていた。頭の中でパチパチと何かが燃えるような、痛みにも似た不快感を覚え、小さく唸ってから、そこでようやく目を開く。
滲んださまざまな緑色が目に飛び込んできた。ゆっくりと焦点を合わせていくと、それは車窓の奥に広がる木々や田畑だとわかった。背の高い木々が山の斜面を覆い、開けた所では大きな田んぼが段々と連なっている。遠くのほうには茶畑も見えた。いずれも夏の日差しを受けて青々と輝いている。
眩しいくらいの生命力と、何より大きく広がる空の青さに後ろめたさを感じ、思わず目を細める。都会とはかけ離れた圧倒的な植物の多さに、電車内にいるにも関わらず緑の匂いがした……気がした。
毎年のことだが、この景色を見ると故郷という存在の大きさを実感する。過去、毎日のように見ていた景色だが、土地を離れ時間を置き帰省のタイミングでしか見られないようになると、途端に尊い物のように感じる。実際、故郷とは尊い物だ。自分が生まれ・育ち、思い出が積み重なった家や土地が残っているという事実は、自分が思っているよりも遥かに自分の心を支えてくれている。
学生の頃は考えもしないことだったが、社会に出てさまざまな人や出来事に触れるとそう考えるようになった。いや、私がそういうふうになってしまった、と言ってもいいだろう。
再びアラームが鳴り響き思考が遮られた。スヌーズ機能を切り忘れていたようだ。慌ててアラームを止める。己の慎重さと詰めの甘さを同時に意識しつつ、設定時刻ごと削除した。悪目立ちしていないかと周囲を窺うが、それはまったくの杞憂と言っていい。車両には私を除いて数人しかいなかった。
穏やかな表情で外の景色を眺めている初老の婦人が一人。私と同じく帰省中なのか、隣の席に大きなアウトドア風のボストンバッグを座らせている青年が一人。彼はイヤホンを着けてスマホで動画だかアプリだかに夢中になっている。そして最後の二人は、近所の高校の制服に身を包んだ女生徒。車両にはこの四人、私を含めて五人しか乗っていない。休暇期間中の昼間とはいえ都会とは比較にならない過疎っぷりに、この路線に思い入れのある身としては行く末を案じずにはいられない。