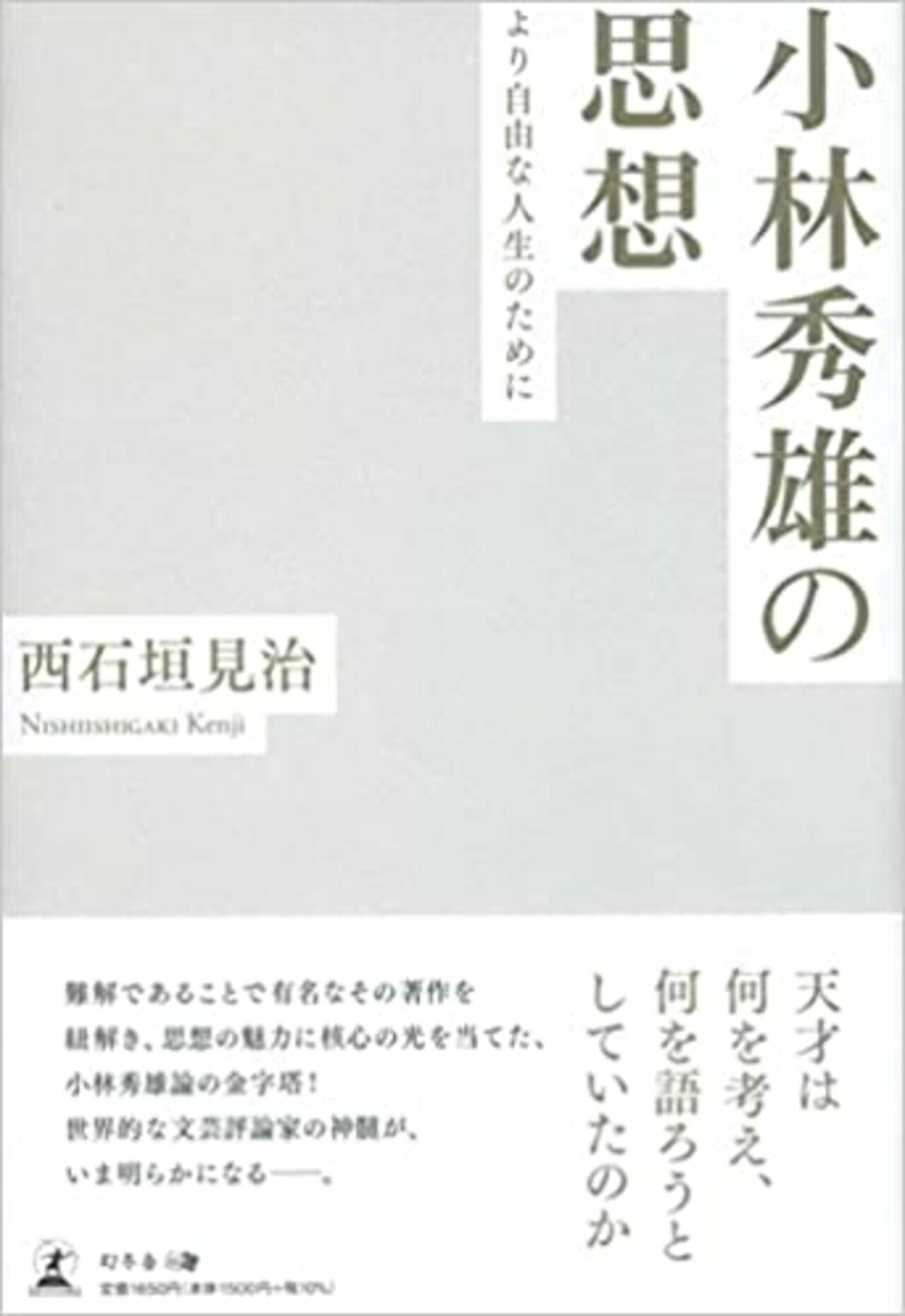小林は、科学への理性の貢献を、限定的、二次的なものに見ているのである。理性は、科学者が、その発見や創造の霊感を汲み上げる、“水源”としての物も の自体ないし実在の世界には、直接、その支配を及ぼすことはできないのである。
可能なのは、そこから科学者が多少なりと直観的に捉えて、自ら漠然と意識に浮上させつつある心的イメージに対して、科学化の過程を及ぼすことなのである。
つまり、科学以前の直観的、イメージ的産物に対して、進化の過程で理性が獲得した、概念的な抽象化作用を及ぼすことなのである。そのことによって、仮説という言葉や論理・数式への置換によって、当該産物を、いわば時間や空間、因果が律という認識の形式のうちに嵌め込むことで、行為やその手続きに還元し、行為の能力としての知の資産を増加させることである。
しかし、それは、発生期の沸騰する創造的な状態は別として、成果としての科学が、行為の延長線上の道具的能力として、広義の技術であることを否定するものではない。しかし、常識による制御が欠落していると、ちょうど、ロープの切れたアドバルーンか何かのように、科学の位置付け自体が、人生論的支配への野望で膨張したままに、世界観のはるか高みにまで、代償的、妄想的に上昇するのである。