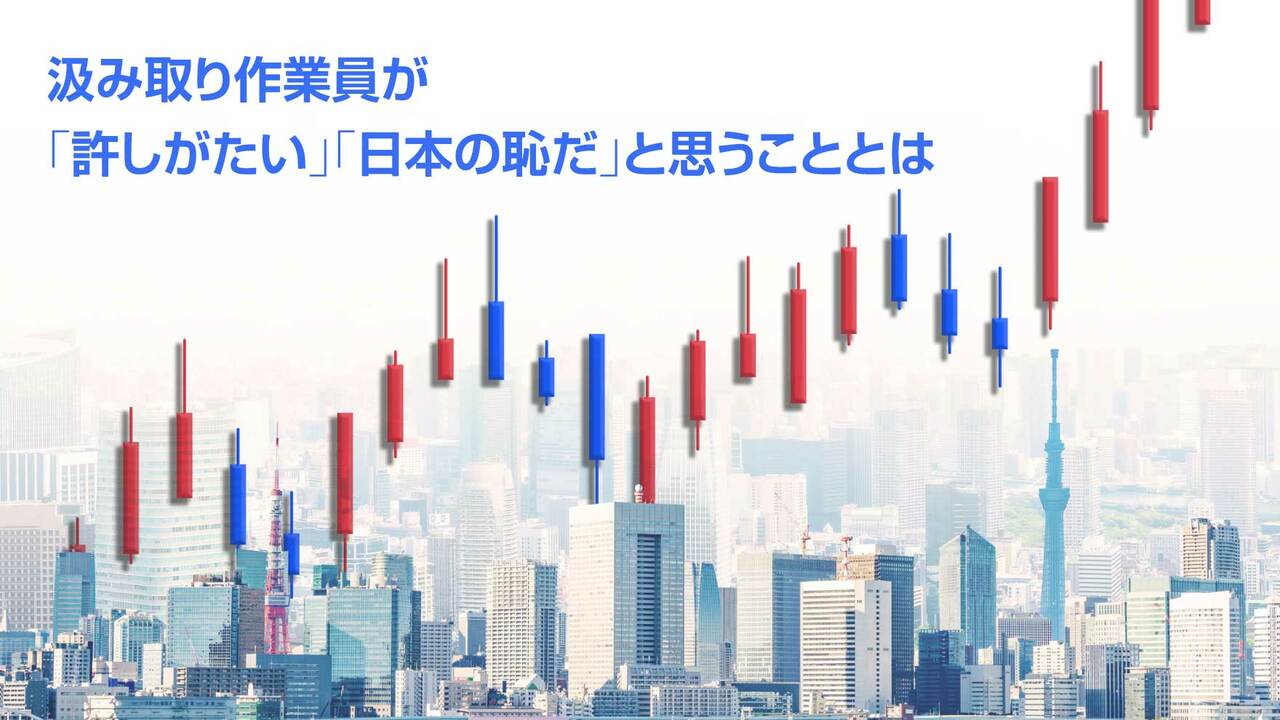【前回の記事を読む】出勤2時間前なのに報告書が終わらない!ピンチを救ったのは妻
第二章 警察官は怖くない
西方警察署の入り口で、健一と内村の二人が待っていると、しばらくして刑事の下条がやってきて、
「お待たせしました。こちらへどうぞ」
と言って会議室のような部屋に案内された。そしてまず内村が隣の机一つと椅子が三脚置かれた部屋に通されて聴取が始まった。内村への聴取は、十分ほどですぐに終わった。会議室に戻ってきた内村は健一に向かって、
「俺はよく分からないから、高井に聞いてくれ。そう言っておいたから後はよろしく頼む」
と言うと、チャッカリお礼の五千円だけもらうと、家が近くなのをいいことに先にサッサと帰って行った。健一が、
「なんて人だ」
と呟いていると、下条が隣の部屋に移るようにと健一を迎えに来た。そして聴取が始まった。下条は、
「今日は本当にありがとうございました。お疲れでしょうがもう少しご協力下さい。先ほど現場でお聞きした事とダブる部分があるかもしれませんが、確認の意味もありますので宜しくお願いします」
と丁寧に挨拶をして、
「よろしかったらどうぞ」
とペットボトルのお茶を差し出した。
普通警察というと、わけも分からず怖いところと思っている人もいるが健一は違った。警察官に合うと安心し、リラックスできた。
というのは、健一が一浪して十九歳で大学に入るために、福島県の会津から東京に出てきたときに、親切に道を教えてくれたり電車の乗り方を教えてくれたのは、交番のお巡りさんだったからだ。
その当時の会津若松駅に、多数の鉄道路線が入り込んでいることはなかったので、健一には、東京の上野駅や新宿駅などの大きな駅では、何線のどのホームに行けばよいのかすら分からなかった。また健一が貧血を起こしてうずくまっているときに保護して交番で休ませてくれたり、トイレが見つからないときは交番に駆け込むと快く貸してくれた。
健一は、元来体力がなく、脳性麻痺の障害者によくある排便の制御が困難な体質だった。また財布をなくして帰りの電車賃がないときなどは、交番のお巡りさんが自分のポケットマネーを貸してくれたこともあった。東京に知り合いのいない健一にとって、警察官、特に交番のお巡りさんは優しく頼りになる人たちであり、交番は健一にとって俗にいう駆け込み寺だった。
通りすがりの人に道を聞いても、電車の中で貧血を起こしてうずくまっていても、ほとんどの人は健一の風貌や異常な身体の動きのせいか、関わってはならいもののように無視した。会津の田舎でも、健一はからかわれたり、いじめられたりはしたが、完全に無視されるようなことはなかった。
無視されるということは、その存在を完全に否定されるということである。健一は、自分という存在を完全に否定され、まったく価値のない者、いてはいけない者として、抹殺されたような気がして心が潰れた。心も身体も、まるで底の見えない深い井戸にたたき落されたような感じがした。
それは健一にとって、経験したことのない究極のいじめであった。