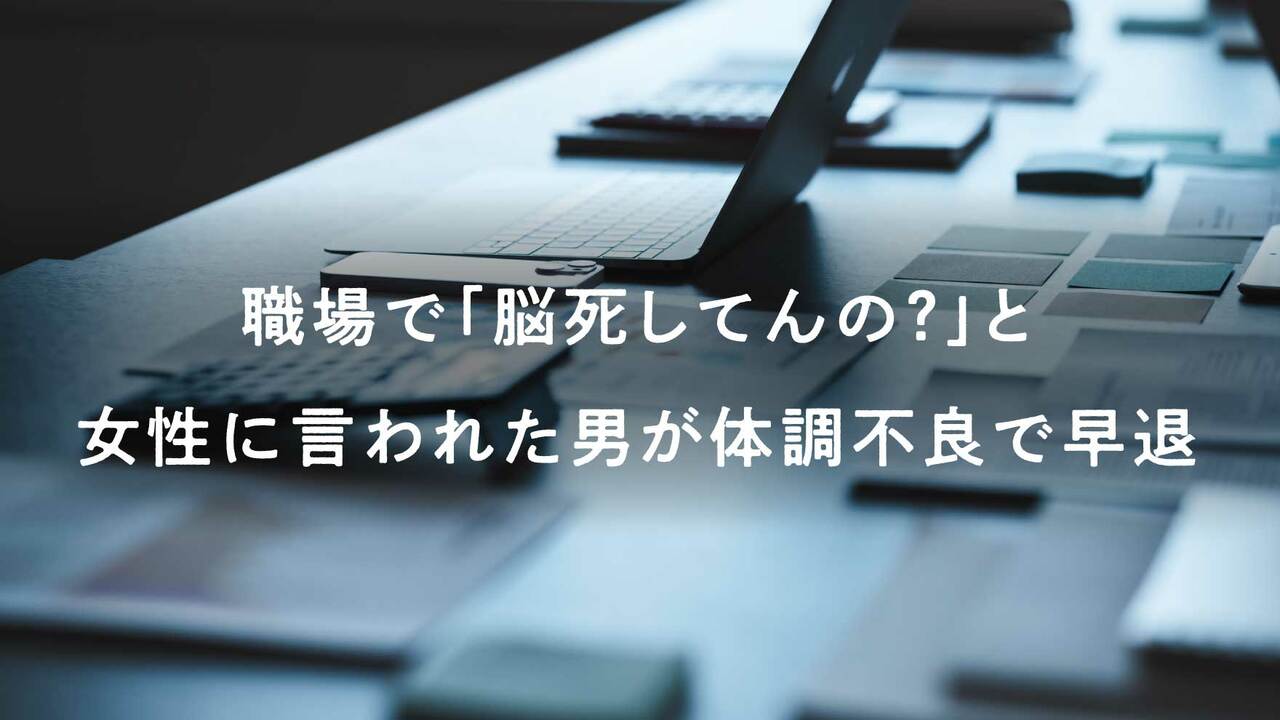【前回の記事を読む】美大に合格し、喜んだのも束の間…「俺たち、別れよう」
第三章
平成二十二年四月一日、十八歳の私は憧れの東京という舞台に立ってデザイナーとして成功するのだと胸を踊らせていた。不動産の契約や生活用品は母がほとんどを済ませてくれ、一日もあればなんとか住めるくらいになった。
「ちゃんとご飯食べるのよ」
「はいはい。もういいから」
上京は母と一緒にした。といっても母は金曜日に休みを取って日曜の夕方には帰ってしまう。不安と期待を抱えながら入学式を迎え、学科ごとに分けられたブースの中に並んだ椅子に腰をおろして、式の挨拶を待っていた。後方にいた私は目線だけ動かして全体を見回す。知らない顔ばかりが並ぶ空間に、改めて新しい地に足を踏み入れたのだと実感した。緊張しているとモデルのように綺麗な女の子が目の前に現れた。
「隣いいですか? 恵っていいます。お名前なんていうの?」
人見知りの私に緊張が走る。
「り、里奈です」
「里奈ちゃん。里奈って呼んでもいい?」
これが恵との最初の会話だった。誰一人知る人がいない学内で、恵という友人に出会えたことは何よりも心強い。初めての課題では相談相手になってくれ、二人で力を合わせながら期限までに提出することができた。単に課題提出という訳ではなく、講評会という形で自分の作品を教授陣と同学年の生徒達の前でプレゼンしなければならない。何度もプレゼン内容を頭で繰り返し、出席番号順に回ってくるのを手の中に滲む汗を握りながら待った。
教授陣は時に静かに、時に笑みを漏らしながら辛辣な意見を淡々と述べる。手厳しい言葉に引きつった顔で反論する者や、臆して黙り込んでしまう者もいる中、私は噛まないようにプレゼンすることだけに集中した。今更どう足掻いても出来上がった目の前の作品がこれ以上良くなることはない。名前が呼ばれたあと頭が真っ白になり、気づけば自分の出番は終わっていた。
何と講評されたかも覚えていないほど一瞬の出来事である。それほど緊張していた。恵が終わるのを見届けてから二人で食堂へ向かい、席に着くと同時に私たちは大きなため息を漏らした。緊張の糸が切れると空腹感に襲われ、スタミナたっぷりのニンニクが効いた唐揚げ定食を大盛りで注文した。