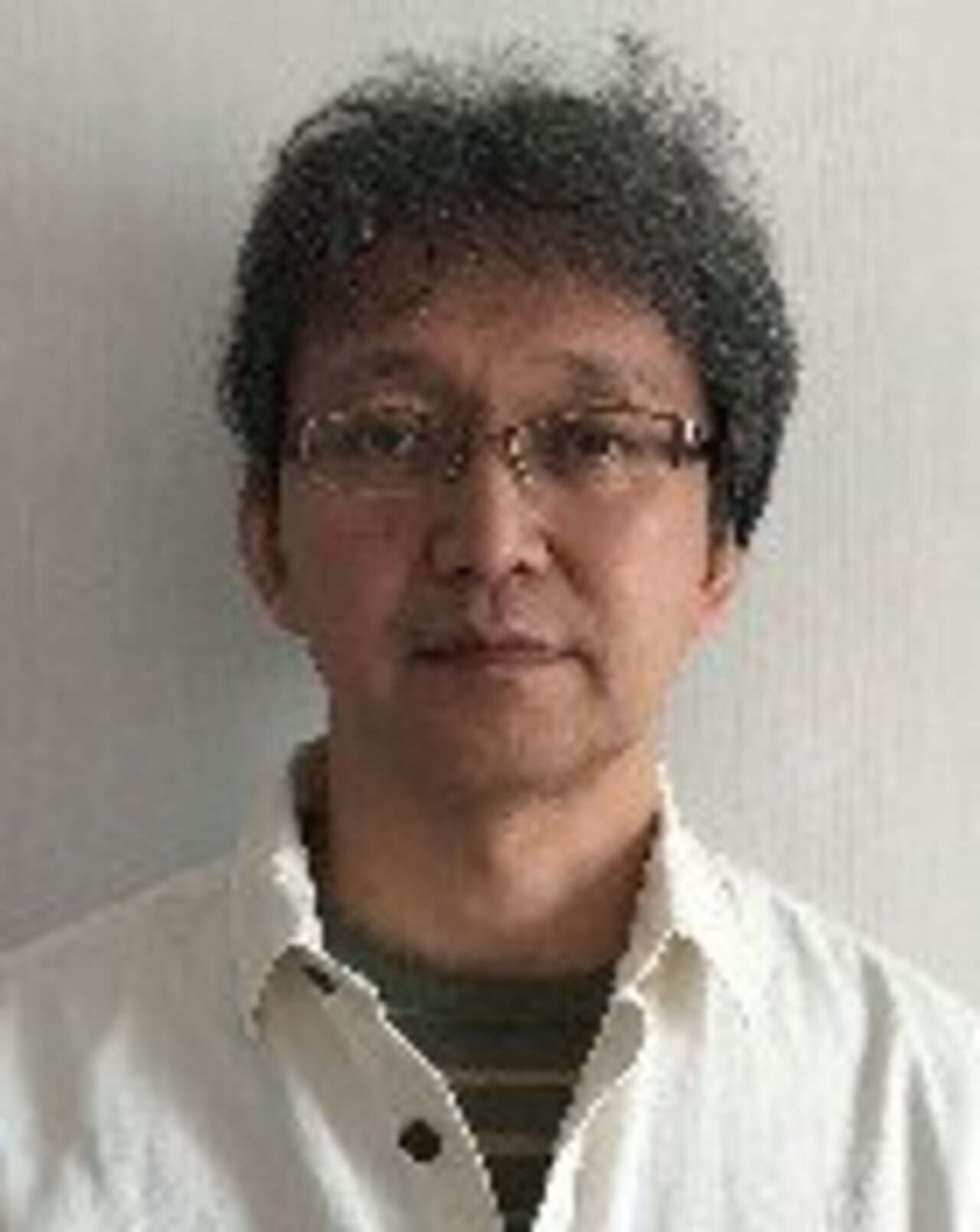「弾く」と「聴く」
ただ、デートにはなかなか行けなかった。というのも和枝が「EFG新人ピアノコンクール」にエントリーしたからだ。これは二人が知り合うずっと以前から決めていたことで、和枝は前年の夏から本格的に練習を積んでいた。
一次予選はテープ審査ですんなり通った。そして二次予選の会場だが、これはやはり縁というしかないだろう、廉が勤める新聞社の浜風ホールだったのだ。
花冷えの青空が澄みわたる午後、廉はホールに向かった。シューボックス型、つまり「靴箱のような立方体」という意味の、長細い室内楽専用ホールで、真ん中辺りの席に座った廉の目に、舞台の和枝は随分遠く見えた。
しかし彼女の両手が振り下ろされ第一音が耳に届いた瞬間、視覚は頼りにならなくなった。聞こえてくる音だけに廉はついていった。
ショパンの幻想ポロネーズ。心を打ち砕かれた人の慟哭のような低音、諦めを甘受するように中音から高音へと広がっていく波紋。音楽そのものはもちろんだが、何よりこのピアノが発する音は和枝の言葉になり得ていた。
廉は最初から最後の三十人目までを聴き通したが、後半は「十六番高森和枝」の演奏ばかりが頭の中で繰り返し流れていた。
その夕方、初めて二人で銀座の街を歩いた。和枝は銀座のことはあまり知らなかった。にもかかわらず鎌倉で出会った日と同じあの笑顔を見ると「銀座の街にぴったり馴染むな」と廉は嬉しかった。
数寄屋橋交差点を渡ってすぐのイタリア料理店に入り、早めの夕食にした。二階の窓辺の席からは、斜め向こうにソニービルが見え、灯のともる、この街が一番綺麗に見える時間帯だった。
「きょう弾いたピアノ、響きが神がかっていたけど……」
和枝はクスッと笑って「でしょう、私が弾いたんだもん」
「うん、そうだね」
「冗談よ。そのくらいのこと、ポンと平気な顔で言い切れる図太さが私にもあったらなぁ。ところであのピアノね、ベーゼンドルファーっていうのよ。名前聞いたことある?」
「ああ、名前だけはね。ウチの社のホールを運営する文化事業部の人に、コンクールの予習のつもりでこの前聞いたんだけど、あのホールにはヤマハ一台と二台のスタインウェイと、そのなんだっけベーゼンなんとか」
「ドルファーね」
「そう、合わせてその四台がスタンバイされているんだって」
「へぇー、いいこと聞いた。ありがと。それでさ、ホールが立派過ぎるじゃない。コンクールの緊張感がますます高まったってわけ。でもどうしてなんだろう。ほら、あのポロネーズ特有の『ターンタララッタタンタンタン』ってフレーズがあるでしょ。あそこからは曲にぐいと引き込まれて、最後まで気持ちよく弾ききることができたのよ」
「ものすごくいい時間を過ごせたってこと?」
「うん、そうねえ、何かに体ごと持っていかれている感じ。あんなの初めてかな。拍手受けてお辞儀した瞬間、思わずピアノの金色のロゴを確認しちゃった」
「これがBösendorfer(ベーゼンドルファー)かって?」
「そうなの」
ベーゼンドルファーで弾いたショパンの幻想ポロネーズが和枝と自分を急速に近づけてくれている、と廉は感じていた。和枝の音は廉にとって、真っ直ぐ心に届く大好きな音になっていた。