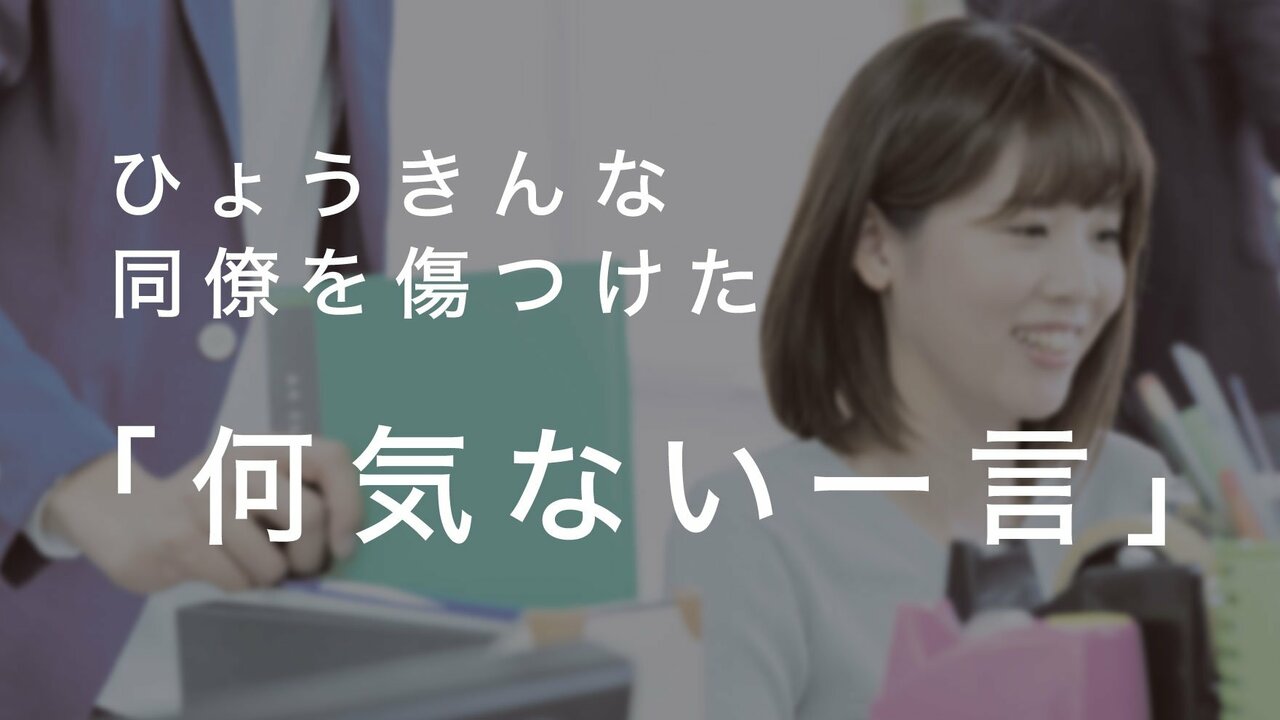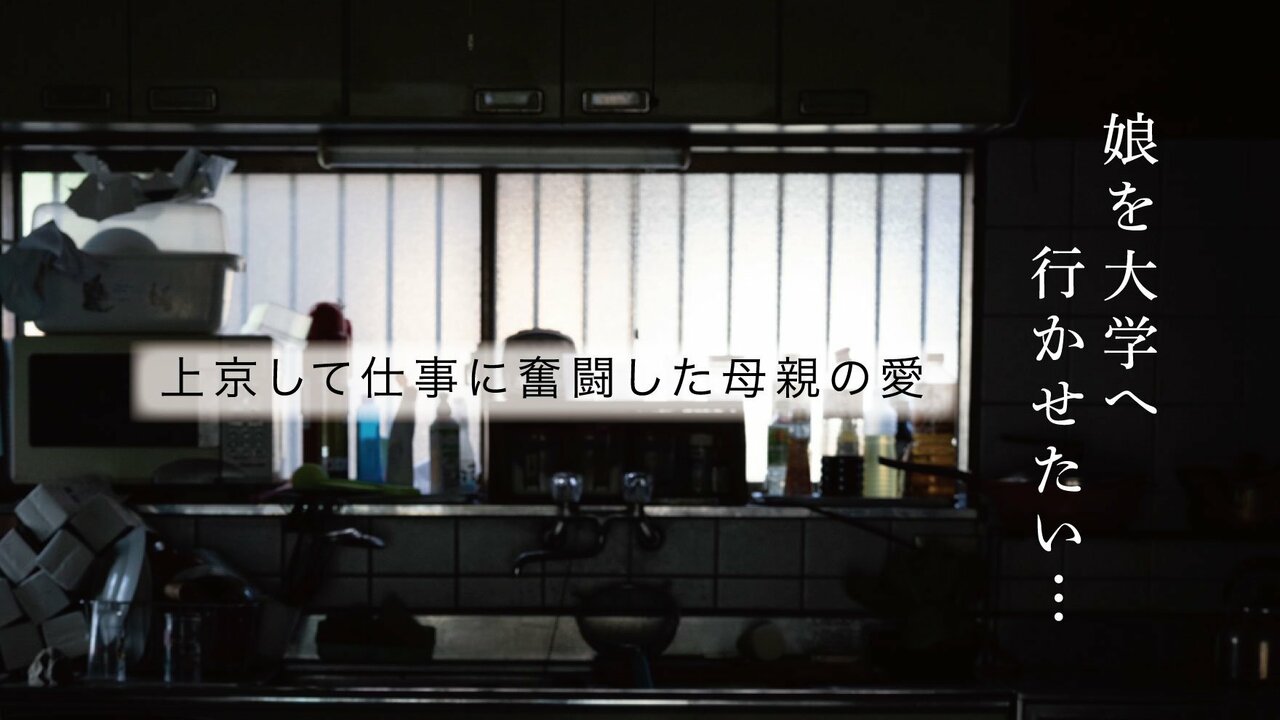クマンバチとタイサンボク
会長は八十歳を超えた。時折、社内をぶらぶらし、女子社員とだけ、おしゃべりをする。小さな町工場を従業員三百人の会社に育てた創業者である。豊かな白髪でお腹も出ておらず、まあまあの風貌と言えるだろう。
二〇一〇年の秋口のことだった。経理課に来て私の机の脇に立ち、得意気に言った。
「おれの部屋の前にタイサンボクを植えたんだ。知ってるか、タイサンボク」
「あっ、わかります。白い大きな花で、いい香りがするんですよね」
「そうだ、来年の夏の初めには、いい匂いがするぞ」
前年の冬のことだったと思う。椅子の背に掛けた私のコートを見て、会長が言った。
「もっと、いいものを着ろ」
「これ暖かくて、気に入っているんです」
ユニクロのエアテックコートだった。彼は隣の光子のダウンコートも見て、フードの縁取りの毛を指し、また言った。
「こんなもの、ニセの合成の毛だろ」
「えーっ!」
二人で顔を見合わせた。合成じゃないと思うけれど、言い返せなかった。彼は毛皮のコートがいかに暖かいか、毛並みが美しいかを話しだした。
「私たちの給料で毛皮なんて買えるわけないじゃん!」
と思い、つい反発した。
「動物愛護精神から、毛皮は着ないことにしているんです! ああいうものを欲しがる人がいるから、動物がむやみに殺されるんです」
「そうですよ」
光子も言ってくれた。会長は「フン」という顔をして営業課へ行ってしまった。向こうでまた女子社員とおしゃべりをしている。
「そんなに毛皮が暖かいのなら、私たちにも買ってくれなきゃねえ」
と、二人でぼやいた。
新しくダウンコートを買った。フードの毛は、見るからに本物である。ラクーンという毛足の長い動物の毛だという。会長の言葉を思い出して、店の人に確認して買ったのである。そのコートを見て、また会長が言った。
「何だ、動物愛護だとか何とか言いおって、これは動物の毛じゃないか」
「えっ!」
今度は私の方が、言葉に詰まった。
「だってフードにはどれも、動物の毛がついていたんです……」
もぞもぞと弁解した。