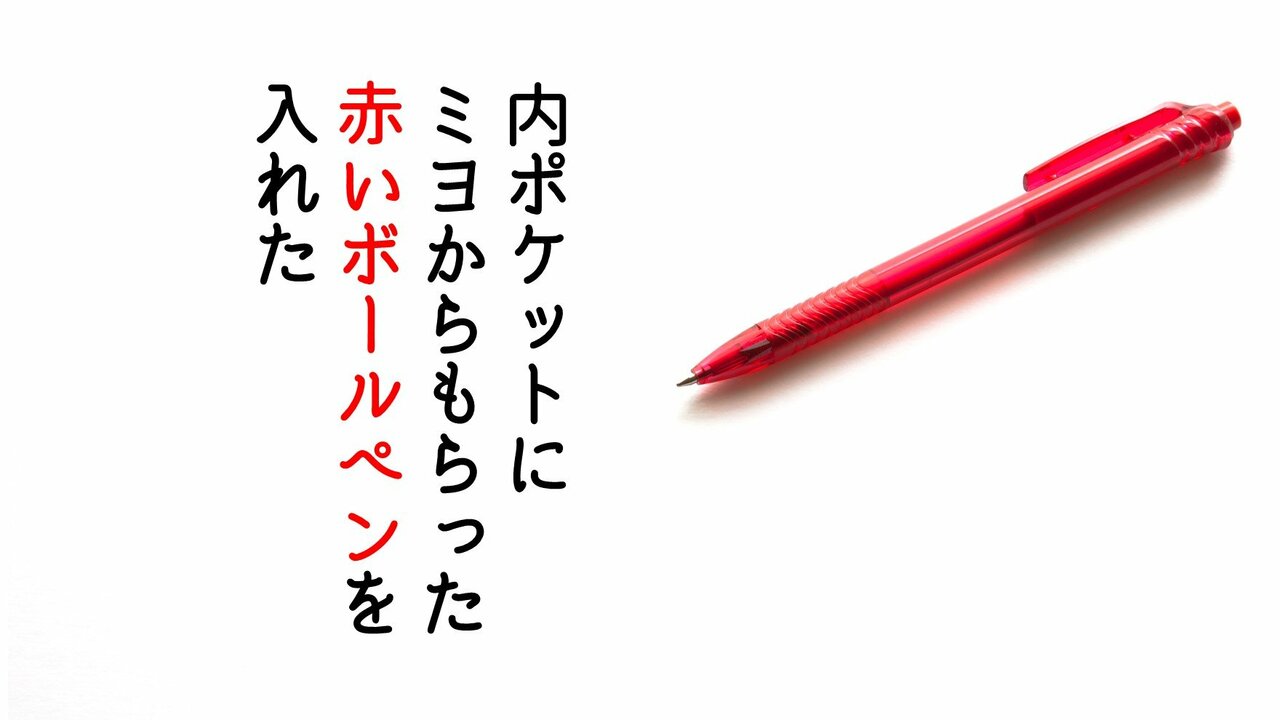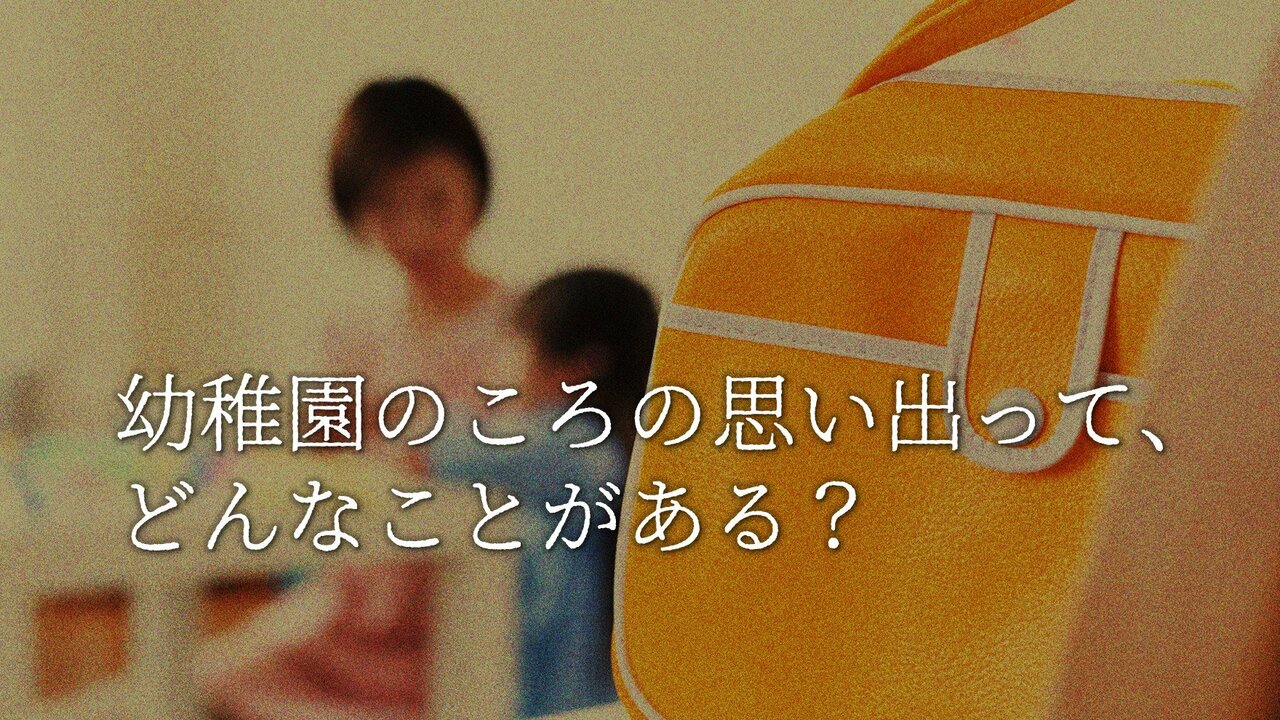第二章 希望
ふと彼女がいたホームへ視線を移した時だった。快速に乗ったはずの彼女が、達也の向かい側に立っていたのだ。彼女と目が合うが、一瞬のできごとに戸惑う達也は、とっさに視線をそらしそうになる。
ドクン。胸の鼓動が耳をつんざく。再び彼女に視線を向けると、ほんのりと赤い光が彼女の身を包み、揺らめいている。前にも見た同じ光景。彼女は無表情に達也を見つめている。達也の体は動かない。
見えるのは彼女の姿だけ。まるでこの世に達也と彼女二人きりみたいだ。体が勝手に震えはじめる。冷や汗が首筋を伝う。
ドクン。達也が乱れはじめた呼吸を整えようとすると、彼女は右手をゆっくりと差し伸べてきた。彼女を包む光は鮮やかな深紅へと変化していく。達也は瞬きもせず彼女を見つめ続ける。彼女はゆっくりと口を開き、何かを伝えようとしている。
唇(くちびる)の動きに全神経を集中させた瞬間、二人の間に電車が滑りこみ、まるで呪縛(じゆばく)を解かれたように達也は我に返った。電車に乗っても胸の鼓動は抑えられない。脱力した体を座席にあずけ、達也は遠ざかるホームを見つめていた。
一週間後、達也はみそぎ学園高校の入試説明会に向かっていた。結花もいっしょだ。最寄り駅の北松本から送迎のスクールバスに揺られること約十分。松本城を北に進むと、長い歴史を感じさせるレトロな建物が見えてきた。丘の上にそびえる私立みそぎ学園高校に到着した。
三階くらいはあろうか。ゴシック建築のスクラッチタイル張りの古めかしい校舎。アカデミックな雰囲気はまるで大学のキャンパスのようだ。校舎を見渡すと黄色に染まった銀杏がキャンパスを彩り、秋の説明会に華(はな)を添えている。
入り口では、在校生たちが礼儀正しく来校者の応対をしている。その中の一人、結花によく似たショートカットの女子生徒が笑顔で手を振っている。
「お姉ちゃんだ。達也くん、行こう」
結花の姉、朝倉実花(みか)だ。
「もう、結花ったら。彼氏といっしょに来るなら言っといてよね」
からかう実花に、顔を真っ赤にした結花があわてて答える。
「ち、違うよ、そんなんじゃないってば。同級生の斉藤達也くん。同じバスケ部でクラスもいっしょの、ただの友だちよ」
「ふうん。ま、そういうことにしておいてあげるわ」
実花の目がいたずらっぽく笑っている。「知らない」と頬を膨らます結花をなだめながら、実花は二人を説明会場へ案内する。
「あそこに見えるのが講堂よ。入り口に受付があるから、学校名と名前を言うのよ。あ、それから、記念品に校章が入ったボールペンを配っているはずだから、もらっておくといいわ」