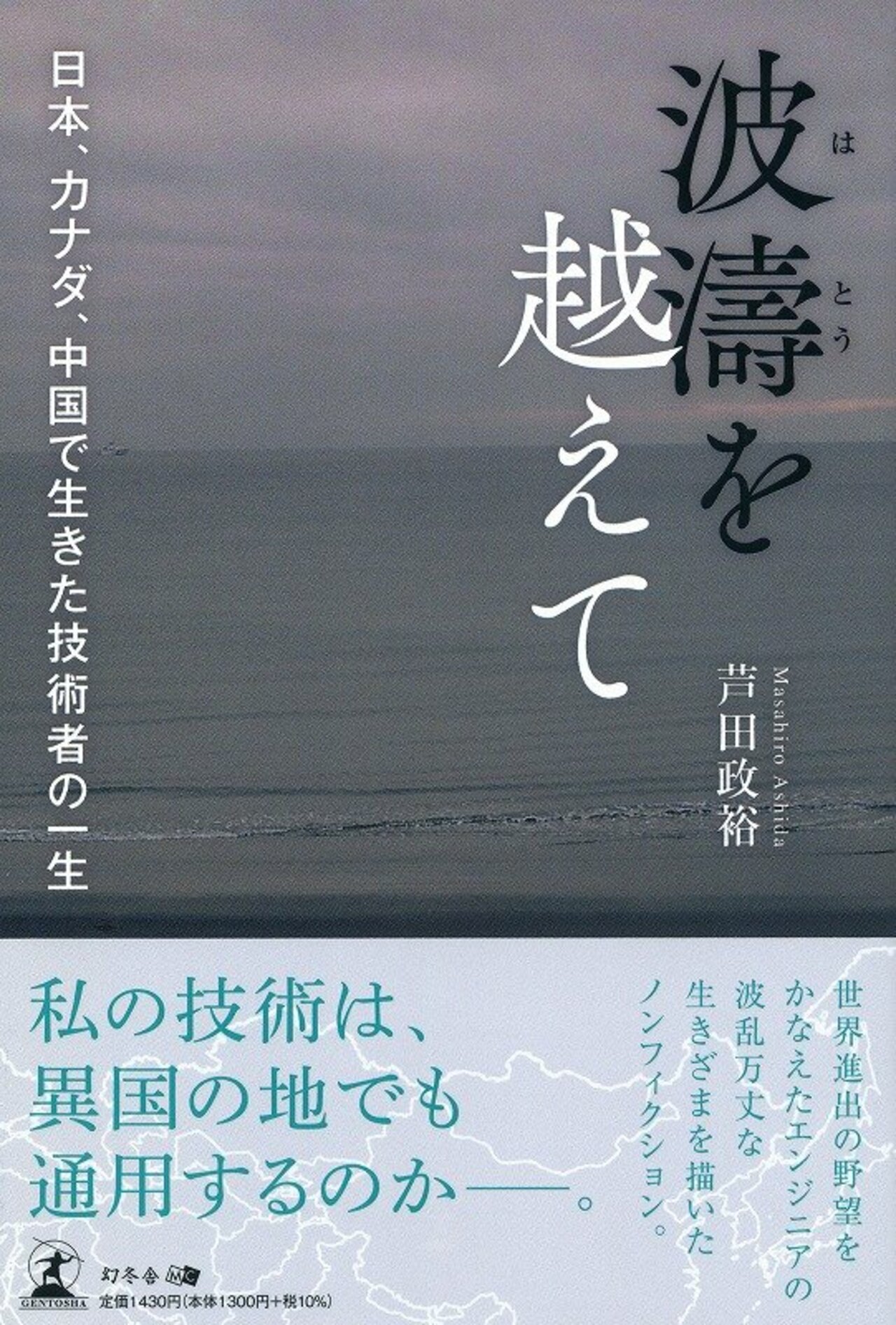彼の話は大きく自慢ばかりでほら吹きだと思った。祖父はその話を頷きながら満足気に聞いていた。友達と遊びに来たようなものだ。家のことはほったらかしで大阪の宿屋に帰っていった。
祖父母は息子の我儘を許し、むしろ自慢していた。政裕は彼から労いの言葉を聞いたこともなかった。
何年もの間に鍬、鋤、肥桶、鎌、斧などすべての道具を使いこなすようになった。ほかに特製の道具も必要に応じ自分で作った。
作物は大麦、小麦、裸麦、粟、馬鈴薯、薩摩芋、里芋、茄、胡瓜、牛蒡、人参、青野菜など、畑を耕して種まき、水やり、施肥、収穫まで、祖母も一緒に働きながら教えてくれた。
正月の三が日は仕事から解放される。正月を指折り数えて楽しみにしていた。丹波の冬は寒かった。よく雪が積もった。雪が積もると水汲みに行く小道や、通学で通りに出るまでの道の雪かきが、雪の朝の仕事だった。
暮れ近くになると餅つきが政裕の仕事になっていた。福岡で父が存命のころ、屋敷の中庭で三人組の餅つき屋が掛け声かけながら威勢よく搗いていたのを思い出す。
祖父がかまどの前に座って薪をくべ、せいろのもち米の蒸し加減を見る。大木の根の上端をお椀型にくりぬいて作った木の臼で餅を搗いた。この臼は代々大事に保管されていたもので年季が入っていた。政裕は杵を取ったが重くて力が入らなかった。祖母が傍で合いの手を打ちながら水を足したり混ぜたりした。
お供えに使う鏡餅をまず形を整える。熱々の餅をちぎって丸める、朝から夕方まで次々に搗いては丸めの一日仕事だった。雑煮を食べたり、囲炉裏を囲んで栗を焼いたり、正月気分が楽しかった。
もち米は親戚からもらってきたもので、畑でとれた粟も、もち米に混ぜて粟餅を搗いた。餅は保存食だ。これだけあれば春になるまで雑煮とか焼き餅にして食べられる。
こんな正月気分が楽しかった。
丹波の山奥での田舎生活は福岡の都会生活では味わえない鄙びた世界だった。
政裕に与えられた仕事で、父が残した七段かの棚田のあとに檜が整然と植えられていた山林の手入れがあった。直径二十センチほどに成長していた。下草を刈り、枯れ枝を落とし、水はけの点検など仕事は楽しかった。
いつも仕事は一人だった。その一帯の地所は今寺と呼ばれていた。すぐ近くに、昔、尼寺があったらしく、その尼たちの丸い墓石が並んでいた。その尼寺は明智光秀によって焼かれたと言われていた。
山の楽しみは、秋になると裏山に連なる尾根の斜面の松林で松茸を探すことだった。祖父母は採ってきた松茸を喜んでくれた。