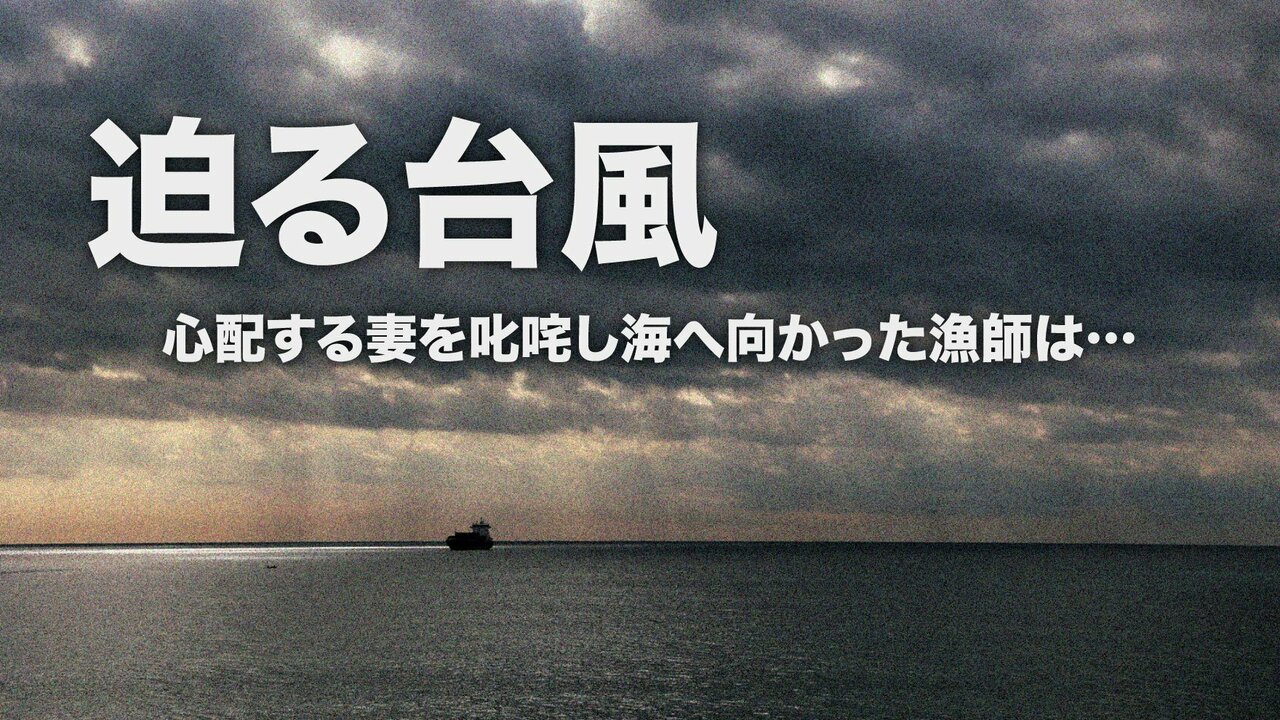康代はスナックの開店直後や客が少なくなりグラスなどの洗い物をしていときによく子供の話や亡くなった夫の話をした。
「うっとこのお兄ちゃんの方やけど、中学の部活のサッカーチームでレギュラーに選ばれたんよ。今度の日曜日に伊勢の総合競技場で試合があるんで応援しに行くの。来んでもええ言うんやけど子供の応援って楽しいもんよ。間違ごてもプロのサッカー選手にはなれへんやろけど何か楽しみでね。
そやけどね、お兄ちゃんは放っておいても大丈夫やけど、下の子が運動神経も学校の成績もあまりよくないの。何しとん言うていつも叱り倒してるのよ。でもね、手が掛かって厄介だけど、どういうわけか下の子の方が可愛いのよ。不思議なものね。これ、兄ちゃんには内緒」
そう言って康代は片眼を瞑って見せた。子供の話をするときは日頃の疲れも影を潜め生き生きとして喋るのだった。
そんなことを話す康代も運に恵まれない苦労の多い女だった。康代は、地元の県立の高等学校を卒業すると浜島にある観光ホテルのフロントに採用された。働き始めて三年も経つと女らしさも増し、よく気の利く働き者との評判も得た。
二十二歳のとき、五歳年上の漁師との結婚話が持ち上がった。相手は浦村登という名前で小型だったが自前の船を持ち水揚げもそれなりにある漁師だった。結婚話は母の親戚から持ち込まれた。登がホテルのフロントで働く康代を見染めて人を介したのだった。康代は、それほど豊かではない漁師の家に生まれ育ち、女ばかりの四人姉妹の三番目であった。
「嫁にくれと言われるうちが華さ。登なら水産高校も出た立派な漁師やないか。それに次男で嫁にいっても舅や姑の世話はないし気楽なもんや。不服を言ったら罰が当たる」
両親はそう言って娘の気持ちに頓着することなくトントンと話を進めてしまい康代に選択の余地はなかった。まるで厄介払いでもするかのような話の進め方をする両親に反発も感じたが、康代もこの話は嫌ではなかった。