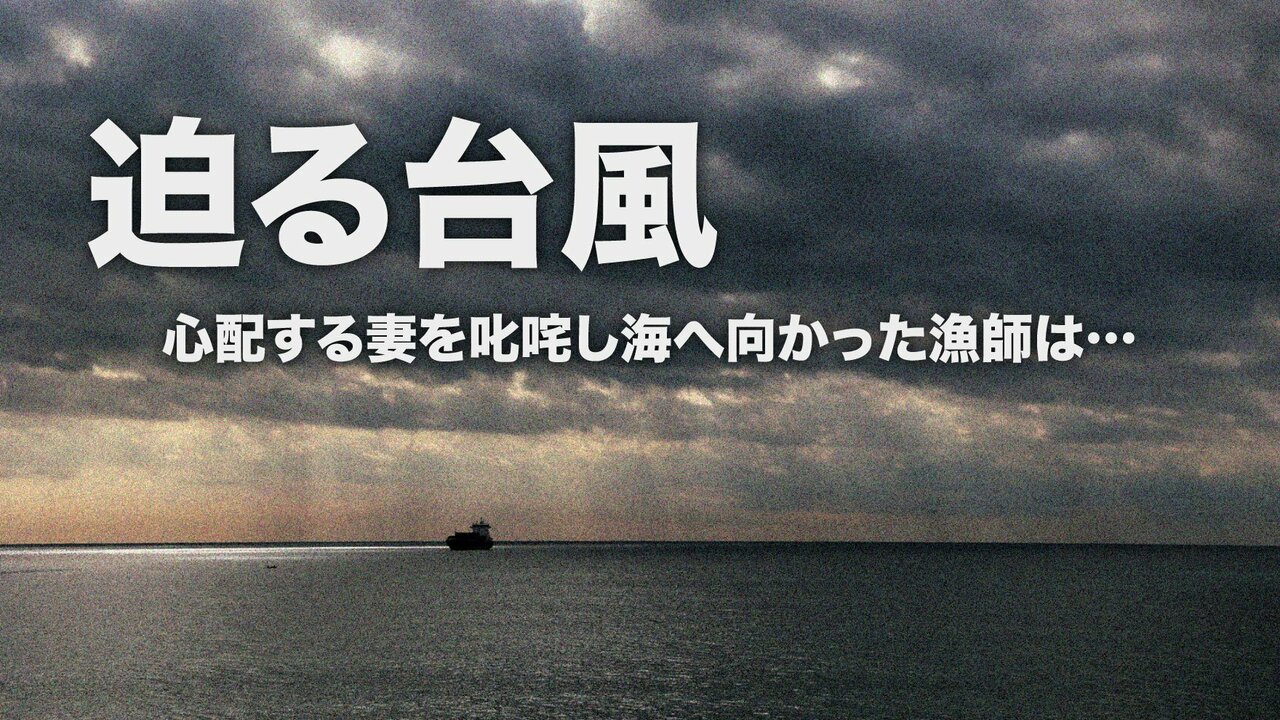美紀は、生活のため夜遅くまで働く智子の苦労を身近で見てきた。
高校受験を控えた中学三年生のときも階下から漏れてくる漁火のカラオケと嬌声に閉口し、学校では友だちから水商売を揶揄されることもあったが、智子の苦労を思うと不満めいたものは口に出すことはできなかった。
美紀の高校は、一時間半ほど掛けて通った松阪市にある普通科の県立高校だった。
卒業すると漁師たちが出入りする地元の漁業協同組合に就職した。
美紀は少し生臭いけれど魚の匂いが嫌いではなかった。それは、決して母の前では言い出せなかったが小さい頃に亡くなった父親の匂いだったからだ。
中学、高校とソフトボール部に所属していた美紀は、母親に似て華奢に見える体つきをしていたが体力があり、その上事務処理もそつなく熟し漁協では重宝がられた。
そんな美紀を組合長は可愛がり水産会社で事務を務める息子の嫁にと望んだ。
「美紀ちゃん、一度逢うだけでも逢ってやってくれへんか。親の口から言うのもなんやけど、ちょっと奥手で引っ込み思案の性格やとは思う。それでもな、くそがつくほど真面目な子なんや」
組合長は何かと機会がある毎に美紀をそう言って口説いた。
「息子さんのことはよう知らんけど、組合長の息子さんというのならええ話やないか。向こうが言うように一度逢うだけでも逢ってみたらどうや?」
美紀が私もまだ逢ったことは無いけど勤め先の組合長から息子の嫁に請われていると打ち明けたとき、智子はそう言った。
一人娘ではあったが娘の結婚について智子に深い思い入れがあるわけではなかった。
ただ、娘には収入の不安定な漁師に嫁がせるより経済的に安定した勤め人に嫁がせたいとの思いはあった。
美紀から結婚の話を聞き、実家が水商売をしていることを承知で、しかも地元の名士である組合長の息子ということもあり、智子には反対の理由は浮かばなかった。
娘がどれだけ可愛くても嫁にも遣らず一生手元に置いておくことなどできはしない。
勤め出して三年あまりの二十一歳。この地方では嫁にいくには早いという歳ではない。良縁なら嫁に出す頃合いだとこの結婚話は智子を乗り気にさせもしたのだった。
美紀は、自分の結婚で一人家に残る母のことを心配した。
「何を言うとんのこの子は。あとのことは心配なんかせんでもええよ。子供いうたらお前一人しかできんだけど、お前がお嫁にいくことはずっと前から覚悟しとる。母さんには店もあるし寂しいことなんかない。早く孫でも作って顔を見せて」
智子は真顔でそう言うだけだった。