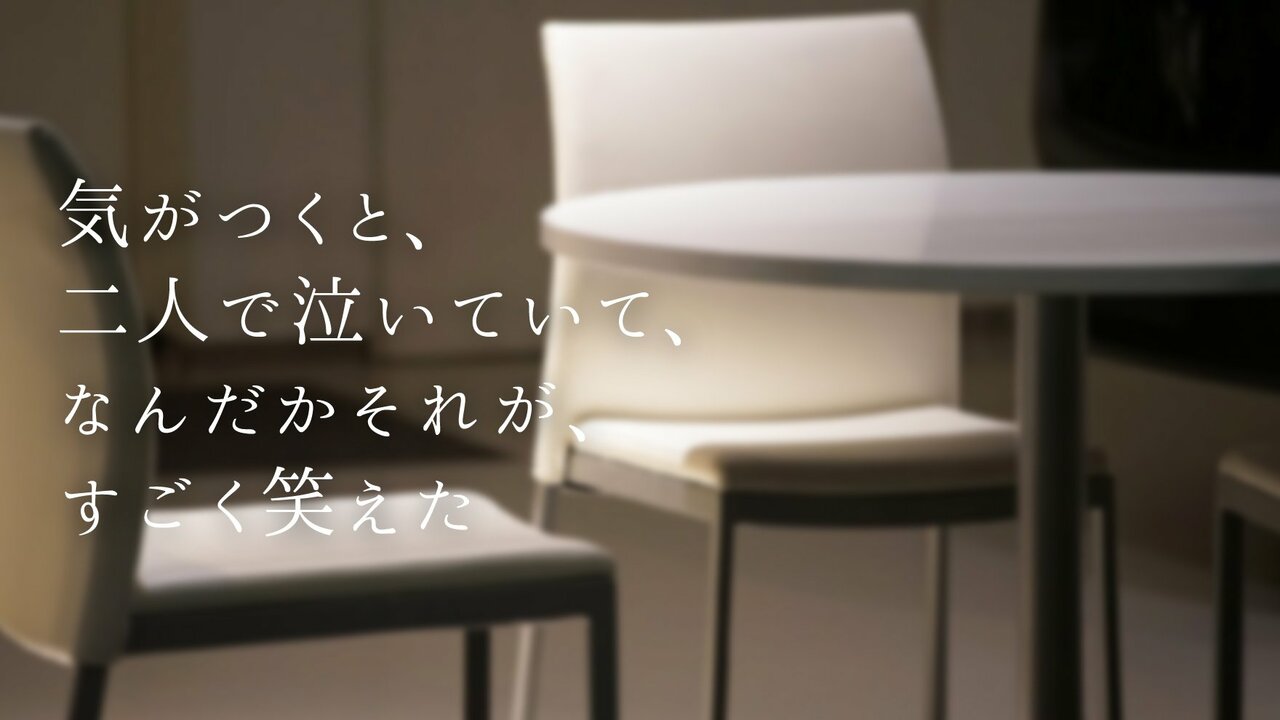シャツ専門店
私は小さな頃から部屋に閉じこもり、ひたすらに本を読む子どもだった。本ならいつまでも読んでいられた。天井高くまでキッチリと本が並んでいるのを眺めるのが好きで、見ていると、本に詰まった様々な物語が本の中でうごめいている気がして胸が膨れた。早く、誰かにこの物語を開いて、そして読んで感じてほしいと願う、本たちの声が聞こえる気がした。
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
彼のお店にある本棚は、まさに私の理想とする本棚で、よく使い込まれていた。本はもちろん、本棚自体が、本たちが持つ物語を語りたがっているようだった。
私はとうとう店の前に来た。
もうこれ以上時間は潰せなかった。
とにかくすぐに、彼に会いたかった。
ただあまりに自分が楽しみに待ちわびてしまったから、なんだか、自分がどんな顔をしているか不安だった。ニヤついてはいないだろうか。逆に強張ってはいないか。
そこで途端に、自分が大きな失敗をしたことに気づいた。
そういえば、ついさっき寄ったお店で、試着したときには鏡を見たはずなのに、その後自分の服に着替えるのに再びフェイスカバーをかぶり、Tシャツを脱いだ。それから私は、改めて鏡を見ることをしなかった。あまりにも、上の空だった。気持ちはとうに彼のお店に飛んでいたから、彼のお店を開けた瞬間や、彼がどこに立っていてくれるのがいいかなどと妄想を繰り返し、身なりを整えるのを忘れてしまっていた。
私は思わず後ずさりした。
まるで、10代の女の子が、初めて人を好きになるみたいな行動に、私自身が動揺していた。
どちらかと言えば、今までうまく、いくつもの恋愛を経験したほうではなかったか。
私は、一度、お手洗いのある百貨店に戻ろうとした。髪を触ってみた。ますます乱れているような気がしてきた。じんわりと汗が滲む。
大きめのバッグを持ち直して、彼のお店にちらりと目を向けた瞬間、でももう、そんな時間はないことに気づく。
ガラス戸の向こうに、彼の、優しい顔があったからだ。