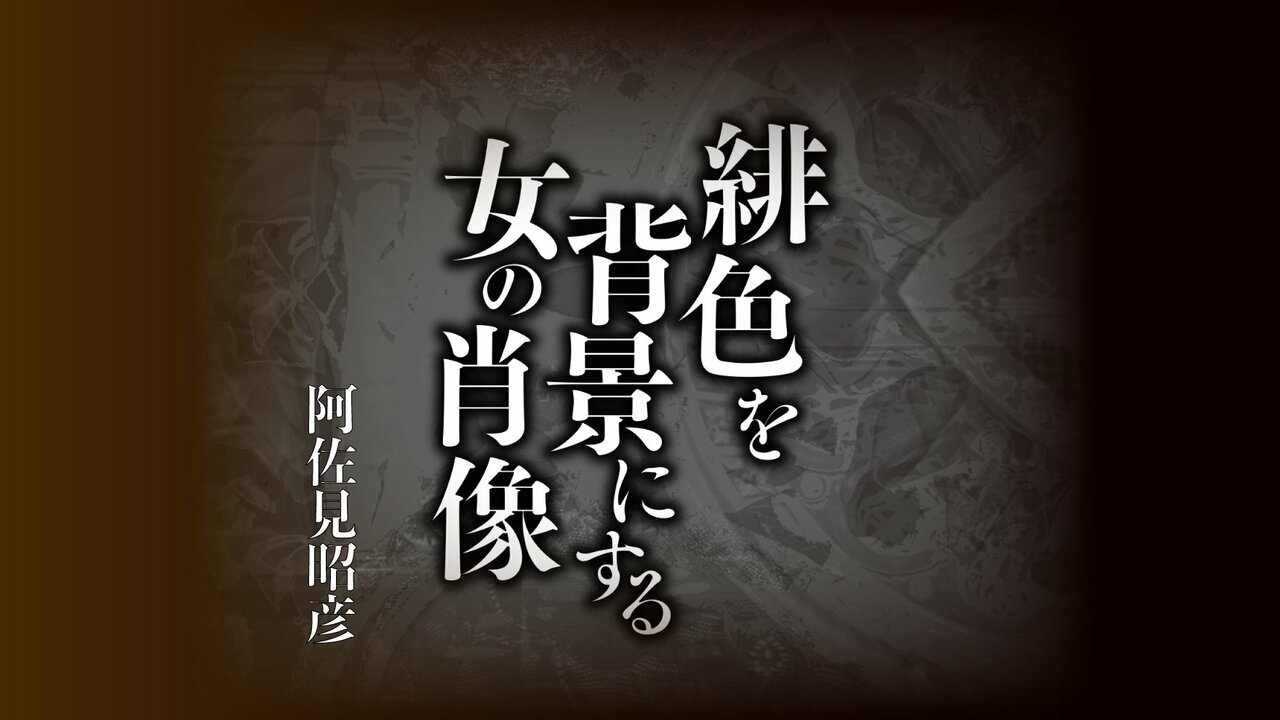ロイド財団
「『なんと言われようともこれは俺一人の欲得ではない。三者がそれぞれ助かるのだ。娘の年だが、二歳とはちょうど良いではないか。これ以下だと将来の容姿が不安だ。これ以上大きくなれば家族と離れづらくなるし、記憶にも残ってしまう。良いか、時間がないのだ。俺は二日後にロンドンへ行くから、子供の写真を何枚か用意してもらおう。最後にもう一度言う。了承するか、さもなくば耳を揃えて百二十万リラを返すかだ。分かったな!』
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
大声を張り上げてしまったが、店のためにもやむを得なかったんだ。わかってくれ、こちらも必死だった。それにまあ、娘だって玉の輿ではないか。必ずや幸せになれる」
例の窪んだ二つの目を爛々と輝かせ、コジモがフェラーラを脅した様子がまざまざと目に浮かんだ。黙って話を聞いていたエリザベスは、二歳の時に起こった恐ろしい出来事に、一言も声を発せず、身を硬くしていた。
遠い昔に記憶を遡らせてみたが、今日の今日まで自分はブリストルで生まれ、小学校を卒業してロンドンに出て来たと思っていたのだった。突如、記憶の断片がエリザベスの脳裏を過ぎった。そのか細い糸を必死に手繰ろうとしてみたが、モヤモヤした霧が立ち込めてしまった。
コジモはそんな様子をチラチラと見遣りながら、できるだけありのまま話すと言いながらさらに先を続けた。
「二日後のことだった。恐ろしい形相をしたフェラーラが事務所に現れ、四枚の写真を置いて帰ったが、私とは一言も交わさなかった。あれから家に帰って、アンナさんとどんなやりとりをしたのかは分からないがね。でも、実の娘を手放すのだからね、想像くらいはつくよ。見方を変えれば、私が彼らを助けてあげたのに、ああ、恐らく大悪人にされていたに違いない」
コジモは見当違いの言い訳に終始した。
「その日の夕方、写真を持って再びロンドンに飛んだ。夜遅く、エドワードが予約したホテルで彼と落ち合った。漏れれば大スキャンダルになるような秘密の取引を前に、彼もいつになくそわそわと不安顔だった。まあ無理からぬことだった。
『エドワード、吉報だ。うまくいった。後は君が気に入るかどうかだな。ほら、この子がユーレ、先日話した娘だよ。ここにいるのが父親のピエトロ・フェラーラさ。そしてこちらが母親のアンナ。そうら、言った通りの凄い美人だろう。この子もやがてそうなるんだ』
ピエトロから渡された写真をエドワードに渡した。彼が写真に見入っている間、知る限りの説明を付け加えて彼の顔色を窺った。長い時間が経ったようだが僅か一、二分のことだったろう。再びいつものエドワードに戻ると、静かにそして重々しく口を開いた。
『コジモ、よくやってくれた。これならば家内のキャサリンも満足するだろう。彼女は養生を装って、昨年からブリストルに住んでいる。子供はしばらくそこで育てることにするよ。コジモ、この子に決めたい。先方とは話がついているのだな? どんな条件になるのだ?』