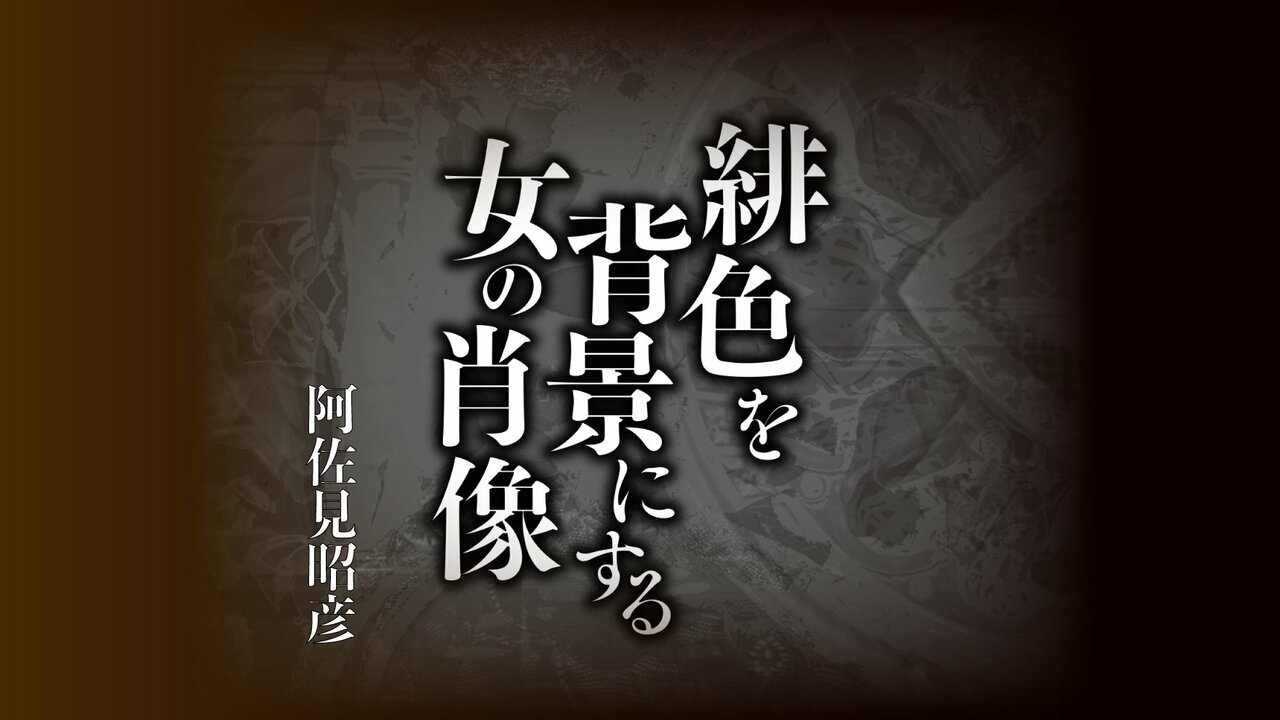1
秋も深まったある月曜日の朝のこと。高級住宅地としてつとにその名を知られるロンドンのメイフェア地区。その中でも、いかにも由緒正しそうな空気を漂わせるフラットの玄関に一人の女が立っていた。
毎日のことなのだが、彼女はインターホンの隣に彫り込まれた真鍮製の丸いボタンをあちこちと押した後、銀色に鈍く光る鍵を取り出した。左右の刻み具合を確認しているようだったが、やがて鍵穴に差入れて捻ると扉は右側に引き込まれて開いた。
女は素早く鍵を引き抜き、室内に滑り込むように入ると同時に、振り返って周りの様子を窺い、今度は内部のボタンを押して扉を閉めた。
ジーッ、カシャッと、 重厚な音が静かなロビーに響く。そして再び前に向き直ると、扉が開いたまま一階に止まっているエレベーターに近寄った。
ともかくも、まずはそれに乗り込み、先ほどの鍵を四階の印が刻まれた鍵穴に差し込んで右に回すと、扉は静かに閉まって籠が動き出した。わずかに横揺れしながら上昇するエレベーターは、やがてガクンとスピードを落としながら停止した。
扉が開ききるのを確認すると、籠から出て小さいロビーに降り立ったが、どうやらそこは玄関の前室らしかった。彼女は0401と刻印された左側の扉を、先ほど玄関で操作したように開けて室内に入った。
いつものことだが洗濯から始め、その後厨房の掃除に移った。なにしろ老人の一人住まいだったから、流しに置かれた食器などたいした数ではない。グラスが四個と皿が数枚、それにナイフとフォークとティースプーンが一本ずつ。それで全部だった。
手早く洗い終えると、次は壁のタイルを拭き始めた。家政婦の口からリズミカルな鼻歌が流れる。続いて浴室、トイレ、居間と済ませたところで、彼女は軽く首を傾げた。
いつもならこの時間、寝室の扉はまだ閉まっているはずなのに、今日はほんの少し開いていて、前を通ると室内がわずかに目に入ったが、内部に人の気配はなさそうだった。
主人はとても几帳面だったし、ことのほか時間には正確だった。この時間には必ずガウン着姿で、一度は厨房や居間に姿を現していた。家政婦はそれを確認して、朝食の支度を始めるのだった。これまで主人が家を留守にする場合、必ず事前に電話連絡があるか、テーブルにメモ書きがあった。