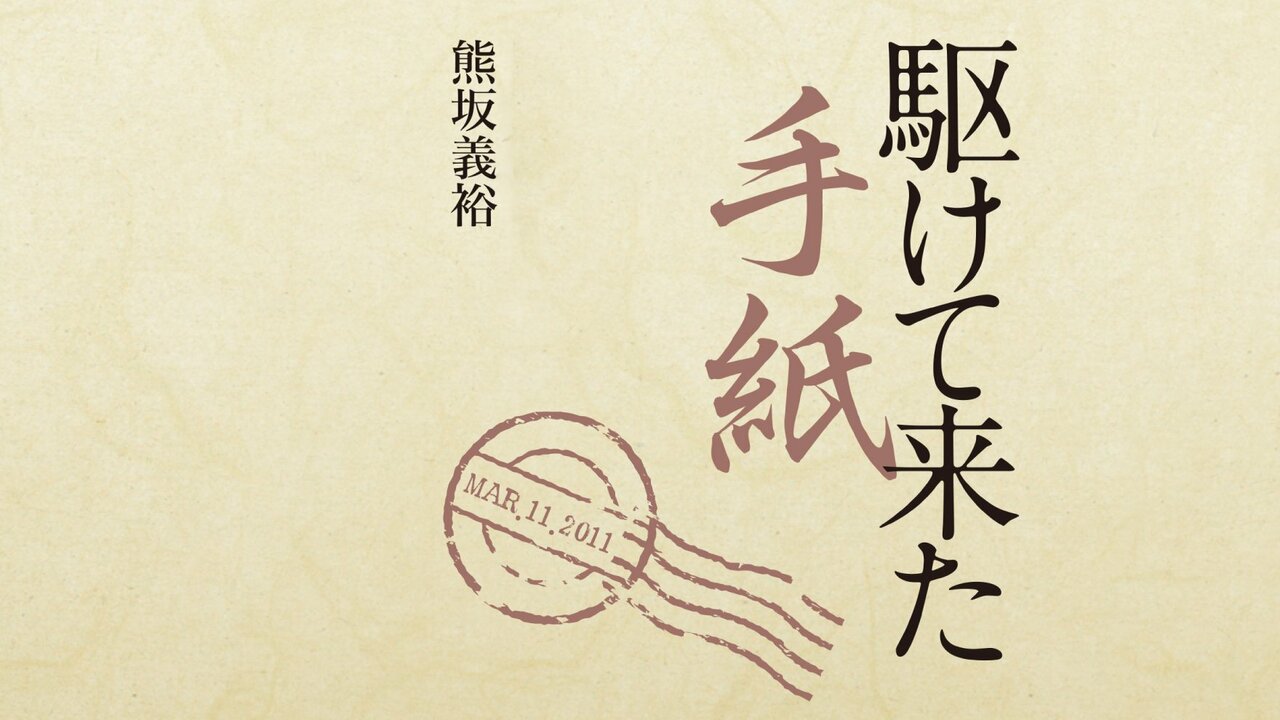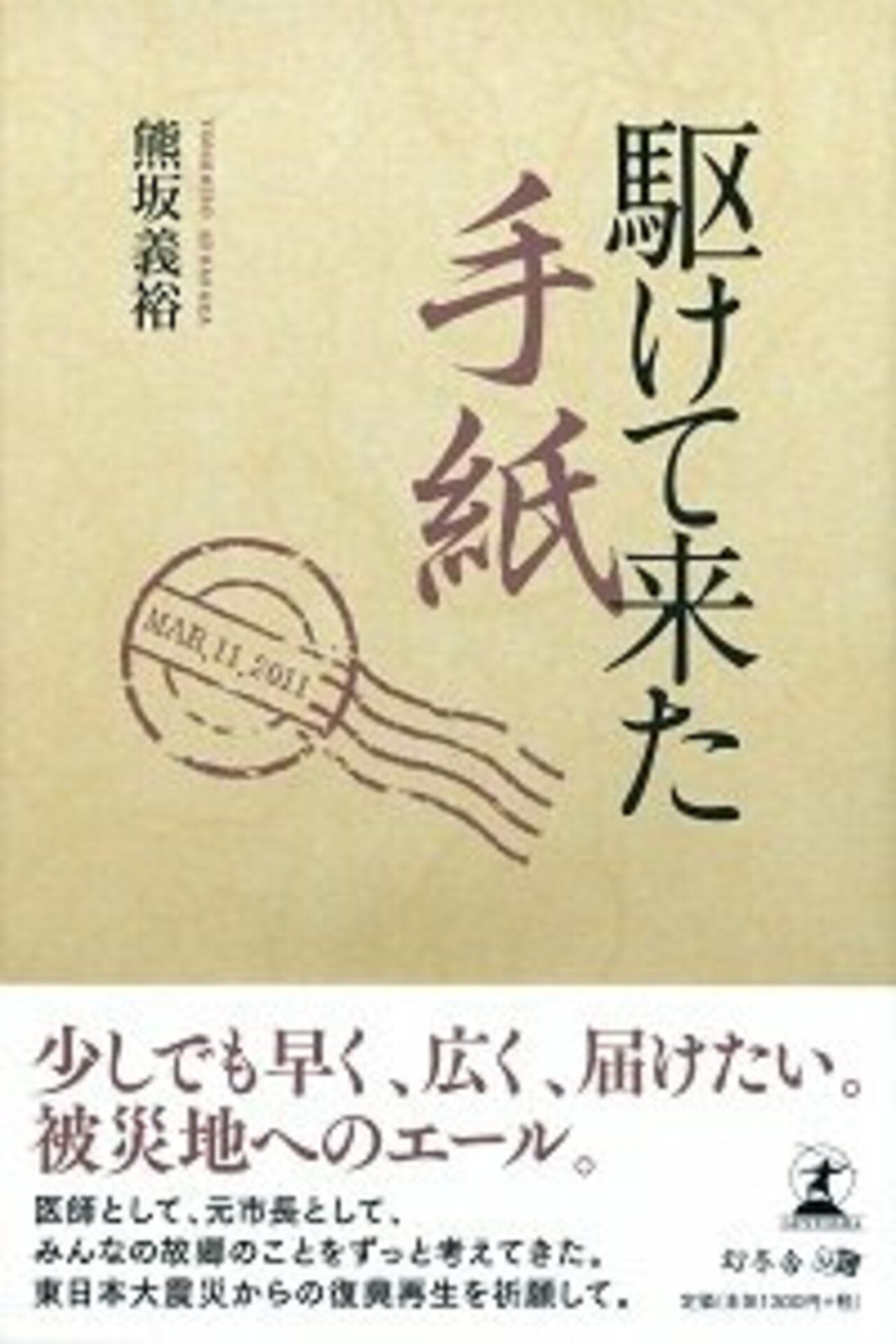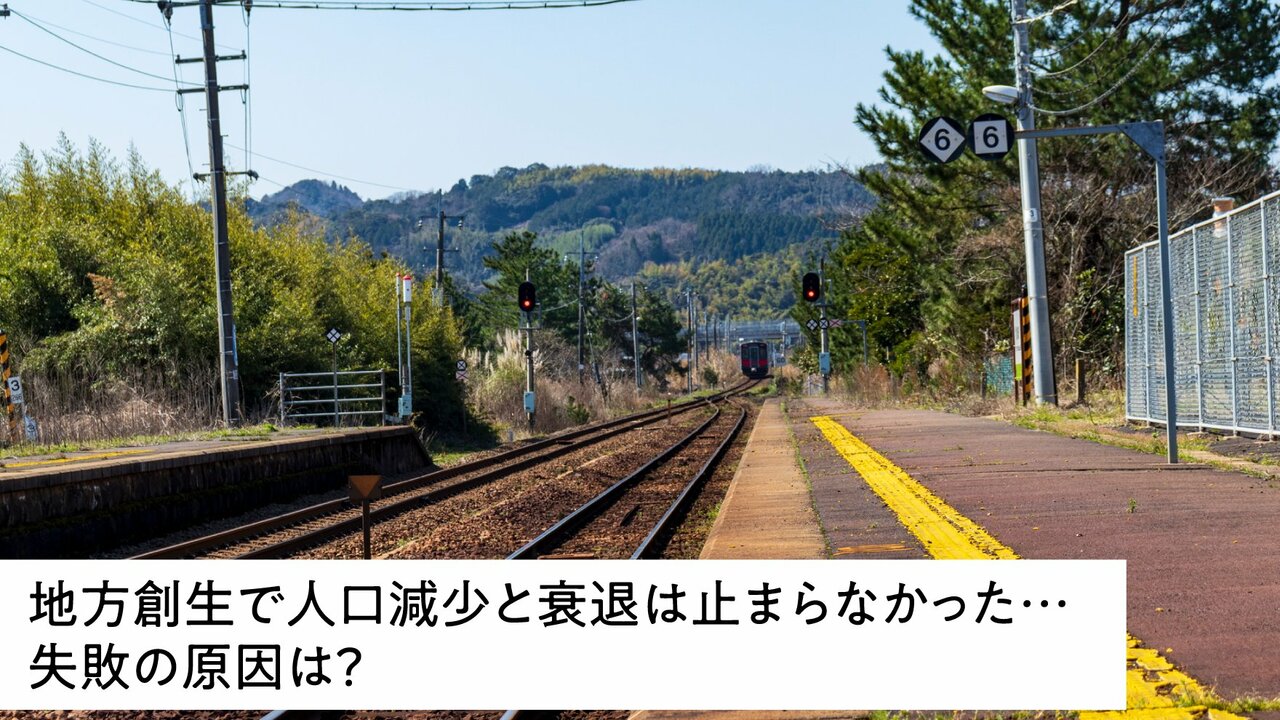子どもの甲状腺がんを考える
原発事故当時18歳以下の子ども約37万人を対象に2011年10月から福島県が実施した1巡目の甲状腺検査で109人、事故後1年間に生まれた子どもを加えて昨年4月から始まった2巡目の検査では8人(昨年12月末現在。いずれも1巡目で異常なしとされた子ども)に甲状腺がんやその疑いがあるとされた。
【注目記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
これらの結果については、将来発症する甲状腺がんを単に早めに見つけているスクリーニング効果(仮にどの都道府県で検査をしても同様の結果になるということ)に過ぎないのか、原発事故による放射能の影響があるのか、専門家の間でも意見が分かれている。
若い世代における甲状腺がん増加の可能性は、原発事故後に最も憂慮すべき健康被害であり、そこにはチェルノブイリ事故からの歴史的教訓がある。それは、チェルノブイリ甲状腺がんは被ばく由来であること、被ばく時の年齢が低いほど発症率が高いこと、被ばく後の若い時よりも歳をとってから発症する確率が高いこと、潜伏期間が非常に長くなる例があること、現実に起きた結果は予想外の連続であり過小評価をしてはいけないこと、これらが明らかになるまで実に20年を要した(今も調査継続中だが)こと等である。
3月下旬、私はこの問題について話し合うために大学の内分泌代謝内科医局で机を並べた春日部厚生病院院長の渡部肇医師(元公益財団法人震災復興支援放射能対策研究所長)を訪ねた。彼は、医師であった亡き父君が相馬市出身であり福島に貢献したいとの思いから原発事故後、ひらた中央病院の甲状腺検査活動に参加してこの分野で最初となる英文論文を発表したことで知られる。