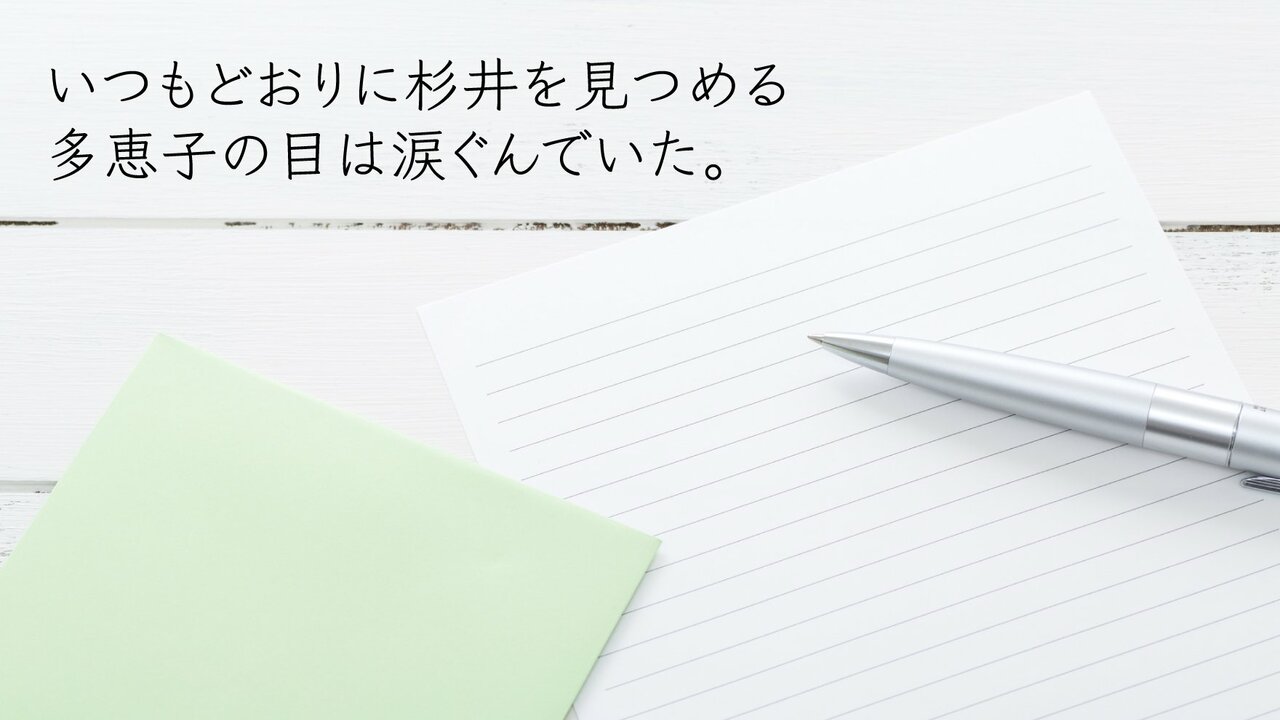「先生も、杉井なら今から一所懸命勉強すれば横浜高商か神戸高商に合格できると言ってくれました。お父さんは立派に仕事をしているし、今私が家に入らなくても商売は絶対にうまくいくと思います。それに大学で商科の勉強をすれば、きっと家の商売にも役に立つし……」
「お前は今俺が立派に仕事をしていると言ったな。家の仕事を立派にやるのに大学での勉強など必要ないことは俺が証明している。お前だって四人の弟、二人の妹がいて、家が楽でないことぐらい分かっているだろう。お前は一刻も早く家に入って、商売を広げて家族皆の暮らしを支える立場だ。俺はお前を自分のことしか考えない人間に育てた覚えはない」
謙造は最初の無表情とは打って変わり、眉をつり上げて、厳しい眼差しで謙一を見つめながら断定的に言った。
「大学へ行くことなど絶対に許さん」
結局、杉井は静岡商業を卒業した昭和十一年四月、杉井謙造商店の社員となった。半年の間、謙造の厳しい指導の下で、緑茶の品定めに始まって、経理から使用人の扱いに至るまで、商人たるためのノウハウをたたき込まれた。
もともと何についても飲み込みは早い方であり、また幼少から謙造の仕事ぶりを見ながら育ったこともあって、一人前の茶商人となるのに左程の困難はなかった。夏が過ぎた頃からは、外に出かけて行っての茶の買いつけも任されるようになり、東京及び関東一円の小売商に対するセールスにも出かけるようになった。
そんな杉井の働きぶりは、謙造の気持ちを充足させるには十分なものだった。しかしながら、家業への従事は謙造がはたで見ているほど、杉井自身に幸福感をもたらしてくれるものではなかった。
杉井は大学進学への未練を明確に感じたことはなかった。一方で、父親には大学を出ても家は継ぐと明言したものの、大学進学も含めた自身の歩み方次第で、より自分に幸福を与えてくれる世界が広がっていく可能性があったのではないかという漠然とした思いが心の底に存在していたのも事実だった。
それは今後どのような方向に向かっていくか必ずしも明確でない日本という国家の姿に、杉井自身が自己の人生を無意識のうちに投影させていたからかも知れなかった。