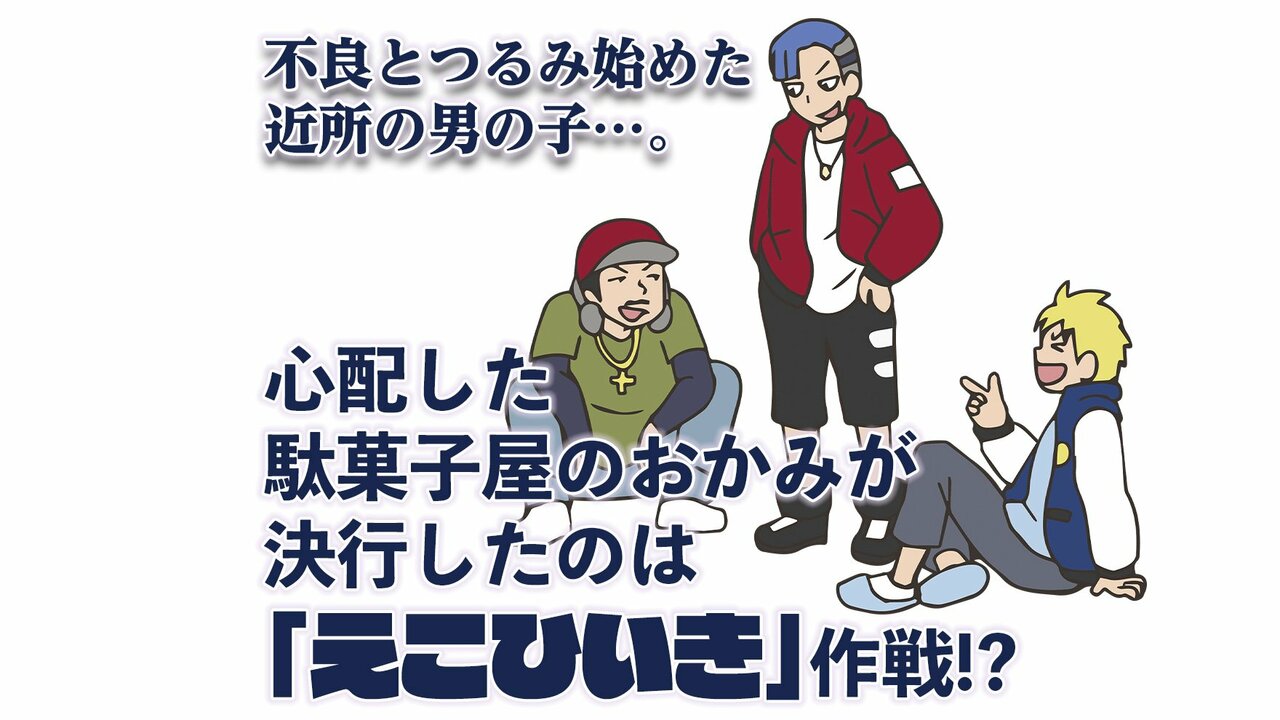ある時水道の蛇口からムカデが落ちてきて母が肝をつぶしたことがある。寂しいところなのにイエネズミは至るところに顔を出し、どこの家にも殺鼠剤(さっそざい)を仕掛けた金網製ネズミ取りがあった。
当時日本海側は裏日本と呼ばれ、鶴前はその典型的な裏日本式気候の土地柄だった。〝弁当は忘れても雨傘を忘れるな〟とは土地の古い言い伝えだった。
大陸からの湿った空気のせいで、一年を通して湿気が高く空気はじめじめしていた。梅雨時の雨は半端ではなかった。春に田んぼの畔(あぜ)に見かけた灰色の湿った綿の塊のようなカエルの卵が孵化して、通学路に無数の青ガエルがぴょんぴょんと跳ねていたのを思い出す。
夏はむし暑く、その暑さは不快で耐え難い。蚊の大群が押し寄せるが、古い日本家屋は気密性がなく、網戸もなかったから僕たちは蚊帳(かや)を吊って寝ていた。蚊帳とすだれと団扇(うちわ)がさながら夏の〝三種の神器〟だった。
一方冬は暗くて寒かった。雪が積もり、それも湿った重い雪で我々の日々の活動を妨げる。十一月から三月初めまでは一・三~一・五メートルの積雪があった。
雪は母にとっては災難以外の何物でもなかったが、子供には刺激的で愉快なものだった。ある朝起きてみたら一面が雪景色になっている。一晩で降り積もった銀世界の風景は美しく、しんと静かで不思議な感動を覚えた。
僕らの家は川沿いの道から外れていたので雪搔きをしないと道はない。僕はそのまま学校に行かず一日中雪を眺めていてもいい気分だったが、父がシャベルで雪を掘り、僕にも手伝うように命じたのでしぶしぶ従うより他はなかった。
暖房は練炭火鉢と炭団(たどん)だが、どちらも一酸化中毒のもととなって時には人の命を奪った。僕の家はそれだけでは寒さを防げないのでダルマストーブなるものを使っていた。毎年冬が近づくと父が名前の通りのダルマの形をしたストーブを物置から出してきて、ブリキの筒をつないで高窓から煙を外に逃がす。
ストーブは紙屑でも木の切れ端でも石炭でも何でも食べる食欲旺盛な奴だった。寝る時にはブリキ製の湯たんぽか、こたつを布団に入れておく。我が家は湯たんぽ派で、朝になると家族全員、洗面器に丁度いい温度になった湯を空けて、顔を洗うのが常だった。
学校の暖房は教壇の横に置かれたダルマストーブだったが、これだけではとても暖かくはならなかった。子供たちは手足によくあかぎれをこしらえていたがこれはとても痛いものだった。手にしもやけを作っている子も沢山いた。それでも雪合戦をしたり、雪だるまをこしらえたり、雪国ならではの楽しみもあった。