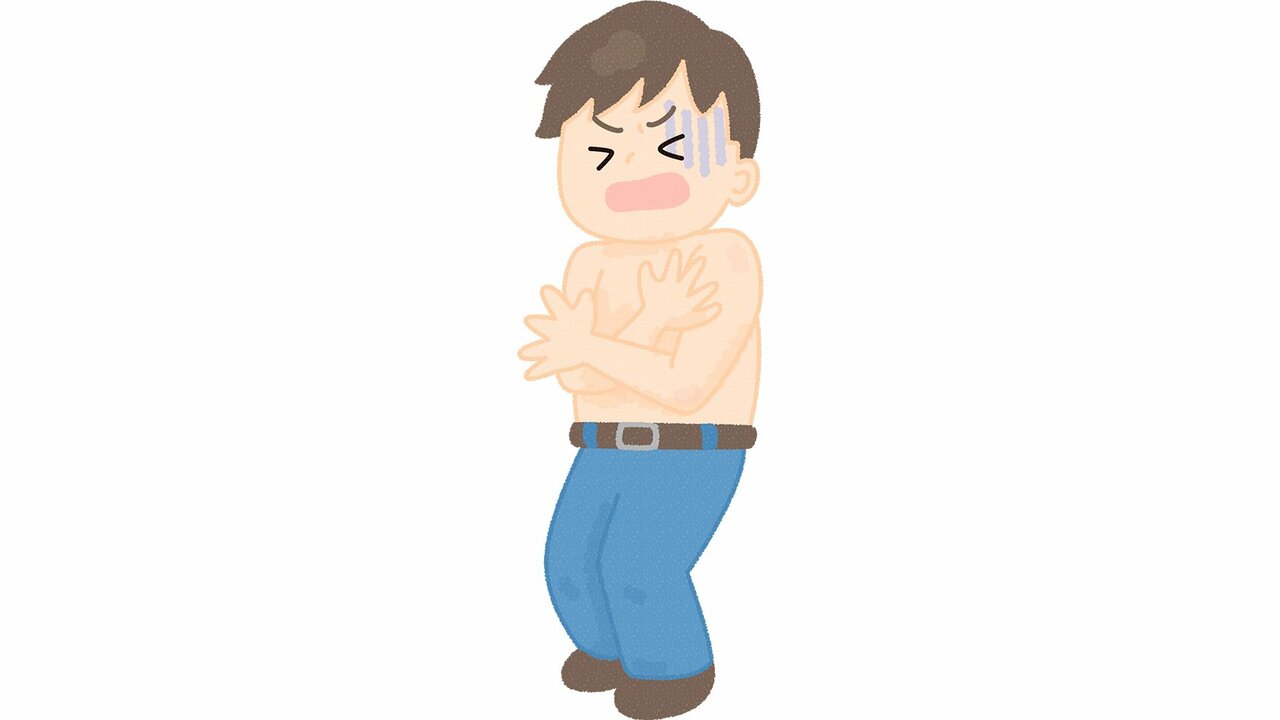第1章 幼い日の思い出
3 小学校時代
左ぎっちょ
「あれっ! 朝子ちゃんは左ぎっちょかいな」
そう言ってお隣のおじさんが、わざとすっとぼけて私をからかう度に、私はそっと左の手を後ろへ隠したものだ。(今では差別用語になっているようだが)
左ぎっちょとは、左利きのことだ。 私より五歳下のお隣の秋子ちゃんは一人っ子で、私が遊びに行くと、家業の手仕事をしているおじさんも、おばさんも大歓迎してくれた。
私たちが切り紙などして遊んでいると、おじさんは私の左利きをよく知っていながら、私が左手ではさみを使っているのを見つけると毎回、さも初めて知ったかのように、冒頭に書いたように大仰に驚いてみせるのだ。
小学生の私が左の手をそっと後ろへ隠す仕草が、大人の目にはおかしかったのかもしれない。自分でも「ぎっちょ」と言われるのは恥ずかしかった。
父は私に、箸と鉛筆だけは右手で持てるようにと、幼い頃からきびしい仕付けをした。大きくなってから人前で恥ずかしい思いをしないようにという親心であった。おかげで箸とペンだけは、かえって右の方が得手となった。
そのほか、大概は左右どちらも使えるようになったのに、いまだにどうしても右手で使えないものに刃物がある。下手をすると怪我をする、という脅迫観念からだ。
その後、成人して結婚した私のもとに、
「こんなものがあった」
と言って、夫が堺の刃物屋で、左利き用の包丁を買ってきてくれた。それまでは右利き用か、両面に刃の付いたステンレスの包丁しかなかったので、その両方を長年の間使い続けていた私は、
「左ぎっちょも、市民権を得る時代になったんやなァ」と、感慨もひとしおで、
「この包丁やと、今までのより、ずっと使いやすいに違いない」と期待をかけた。
ところが、使ってみると何か使い勝手がおかしいのだ。例えば、りんごを真ん中から半分に切る時、二等分するはずの包丁の刃が、途中から横にそれて、二つに切ったりんごに大小ができてしまうのだ。
野菜を切る時も同じだった。何べんやってもうまくいかないので、とうとうあきらめて、折角の左利き用の包丁はお蔵入りとなってしまった。
慣れとはえらいもので、長い間に、右利き用の包丁をも、左手でうまく使いこなすようになっていたのだ。環境に順応していく生き物の機能を、わが身に見た思いがした。