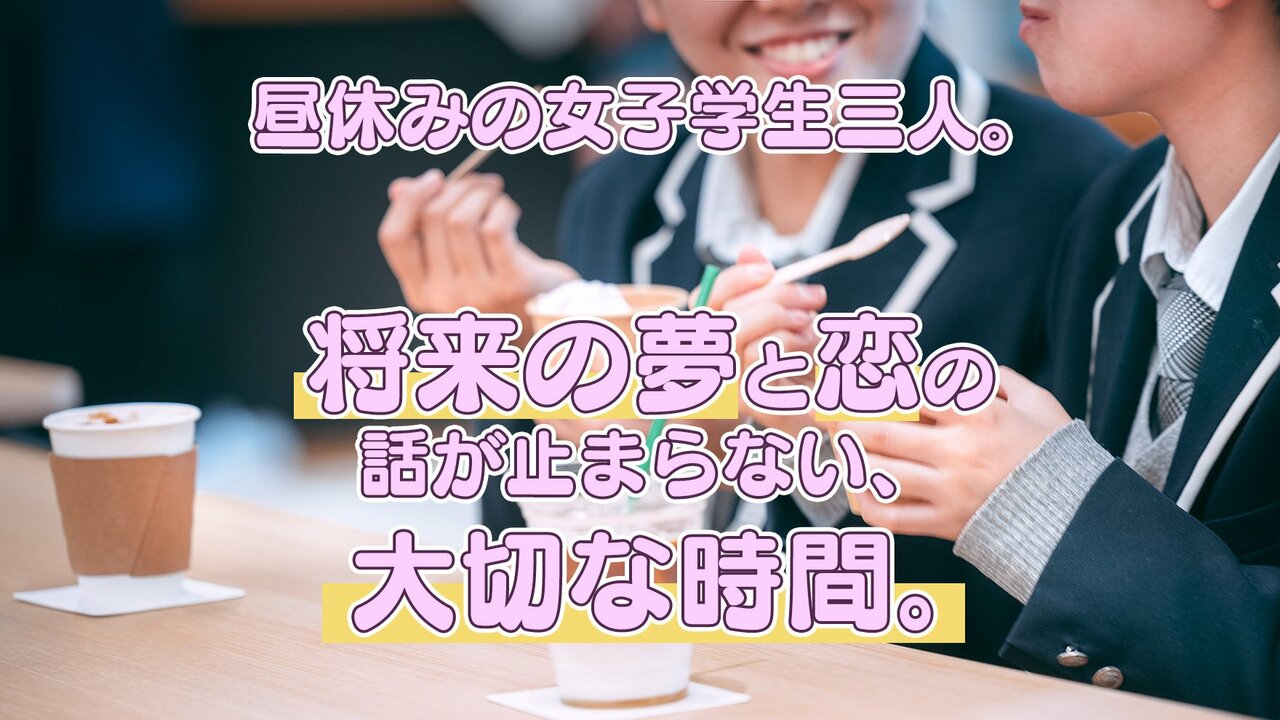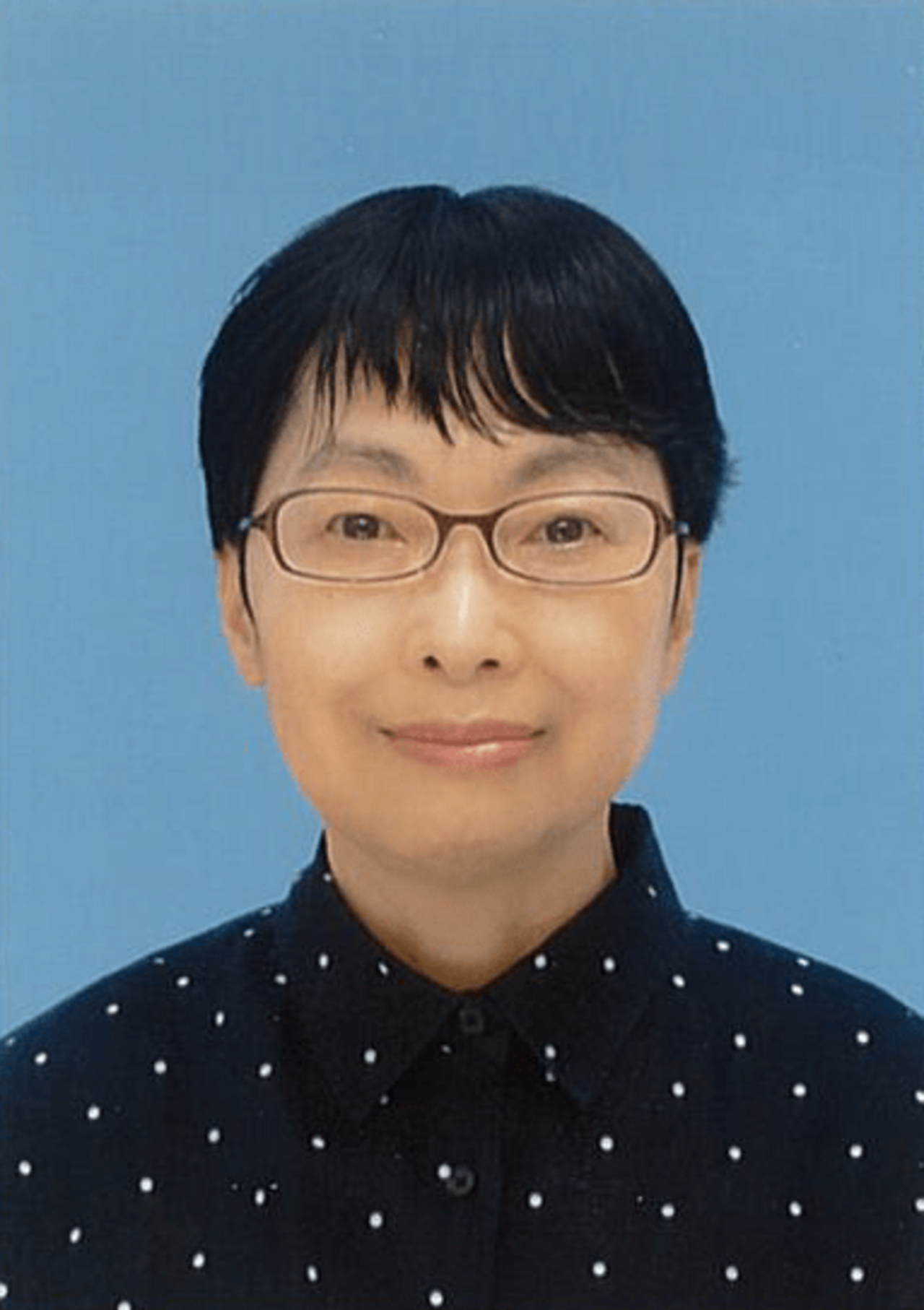私たちの春
十月になって季節は秋になった。私たち三人は、それぞれ受験勉強に、毎日の日常生活に、仲の良い友情に時間を費やしていた。私たちは、いつものように三人でお弁当を食べていた。
「二人とも聞いて。私、昨日、青空文芸社に、小説の原稿を送ったの」
「ホントに?」
「小説、三年生になっても書き続けていたの?」私は聞いた。
「ええ。受験勉強の合間を縫って書き続けていたの。青空文芸社で新人発掘のための文芸コンテストがあって、それに応募したの。もしコンテストで一番に選ばれれば、電子書籍化してくれるのよ」
「そうか。ユミは、コツコツと夢を追い続けていたのね」私は言った。
ユミの両親は本屋を経営していた。ユミの両親は本が好きなのだ。その影響でユミも子どもの頃から読書をするのが好きだった。そして、いつしか自分も小説家になることを夢見るようになったのだ。
「コンテストで一番になれるといいね」私は言った。
「ええ。私、いつか自分の書いたものが書籍化されたらいいなと思っているの」
「どんな内容のものを書いたの?」私は質問した。
「高校三年生の女子学生の友情についてよ」
「えっ。それってまるで私たち三人のことみたいじゃない」リエが言った。
「そうよ。私たち三人のことについて書いたの」
「素材は、すぐ近くにあるというわけか」私は言った。
「そして、それは、ハッピーエンドなの?」リエが質問した。
「そうね。ハッピーエンドね。最後の場面は、卒業してそれぞれの人生を歩んでいくというものよ」
「それぞれの人生を歩んでいくのか」私は言った。
「別れは、新しい人生の始まりという内容で最後を締めくくったの」
「それには、私の恋愛ストーリーも盛り込まれているの?」
「ええ。登場人物の一人は恋もするのよ」
「ところでリエの恋物語は順調に行っているの?」
私は質問した。