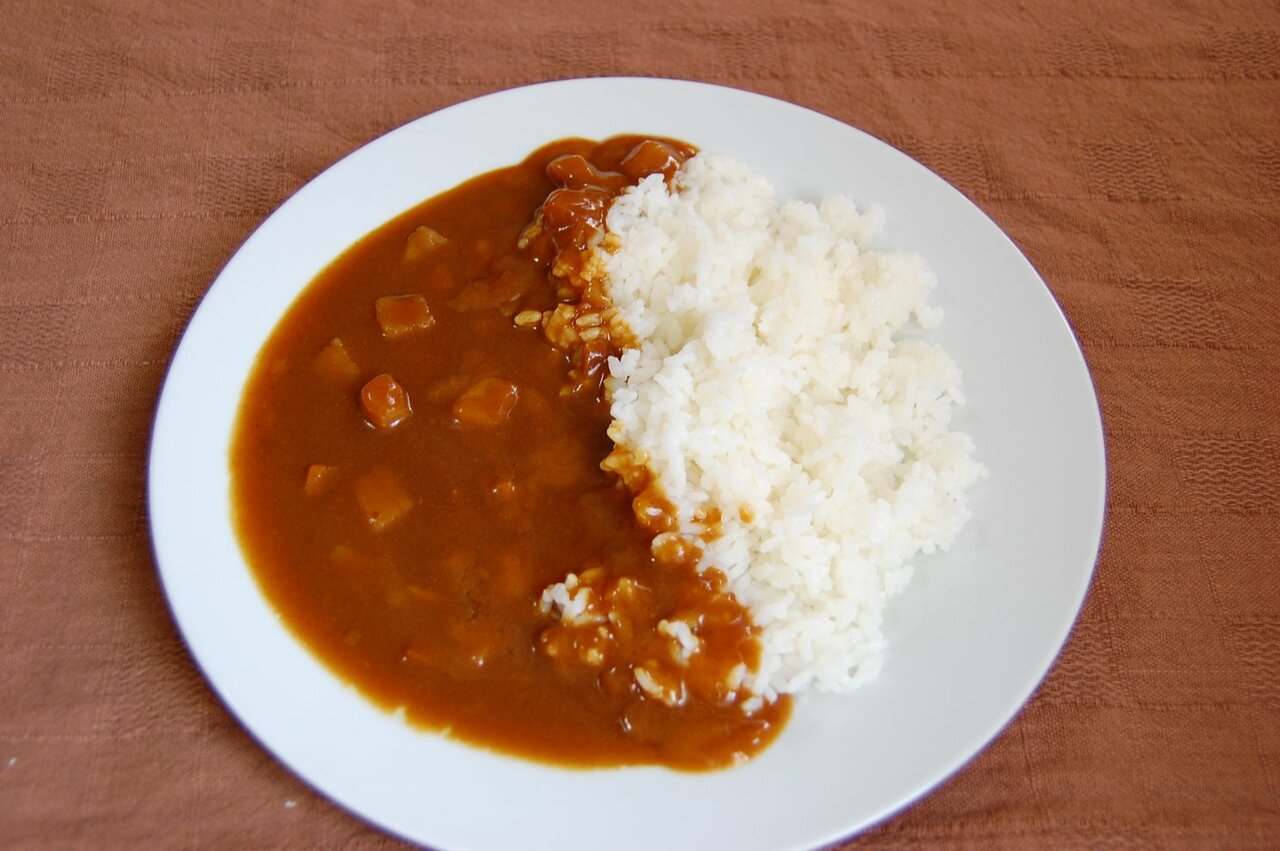【人気記事】「非行」に走った青年時代…医者になった私が当時を思い出すと『腐ったみかんが医者になった日』
第3章 貧困に耐えた中学時代
バラック小屋を後に
坂の途中にあったバラック小家での生活は一年位でした。その坂道を下り坂下(現在の城東)と言う所に古い空き家がありました。麦藁屋根の農家仕立ての家で、そこが新しい我が家になりました。近所の親切な方が、お世話をして下さったようです。
広い十畳程の土間があり、上がり口の板の間がとても広く、そこに囲炉裏が切ってありました。八畳程の座敷の部屋が二間あり、その奥に三畳の小さな部屋もありました。次兄は家にいる時は、その小さな部屋にいることが多く、昔買って貰ったカメラを大切にして楽しんでいました。
私が中学二年生になると、次兄は高校生に弟は小学五年生、妹は小学二年生になりました。
幸いなことに弟と妹は身体が丈夫で、病気一つしませんでした。父は「小遣いが欲しい」とか「自転車が無い」とか、独り言を言っていました。また父は土いじりが得意のようで広い庭に小さな畑を作り、楽しんでいました。
危うく命を拾う
母が家に帰って来るのは月に一度位で、二日位家にいると、また忙しく仕事に出かけて行くのです。母が仕事に行く時は、必ず妹と私はバス停まで見送りに行きました。私は母がバスに乗り、お互いに手を振って別れる時がとても寂しくて嫌でした。でも幼い妹には少しの時間でも、母の傍にいさせてあげたかったのです。
ある日、母を見送った帰り道の事でした。妹はいつものように、私の小指をギッチリ握ってトボトボ歩きながら、
「お姉ちゃん……」
「お母さんって、どういう意味なの?」
「何をする人?」
とケロッと言ったのです。
私はギクッとしました。妹の口をついて出た言葉の意味もさることながら、私の胸は別の思いに責められていました。それは、妹の発した言葉通りの現実を受け入れざるを得なかったことです。確かに幼い妹には、母と家族としての温もりを感じる充分な時間さえ無かったのです。
妹は末っ子で父や母に、一番可愛いがられて育ったはずなのです。それなのに、幼い頃の父の膝の温もりやいつも母の傍で甘えていた事は、どこかに消えてしまったようでした。今の生活で私がいれば事が足りていたからでしょうか? 私を親のように思っていたのかも知れません。
私は母が家族のために必死に働いている事を考えると、妹の言葉でなおさら寂しさが募り胸が一杯になりました。歩きながら悲しさが込み上げてくるのを必死で耐えたのでした。自分の気持ちの整理がつかない中、私は妹に何と答えたのか、思い出そうとしても思い出せないのです。
母が帰って来ると、私は何故か度々熱を出し寝込みました。ところが、いつも母が出かける日には不思議に元気になっているのです。そして母がいずとも、朝が来て昼が過ぎ夜になり、一日一日が何とか回っていました。