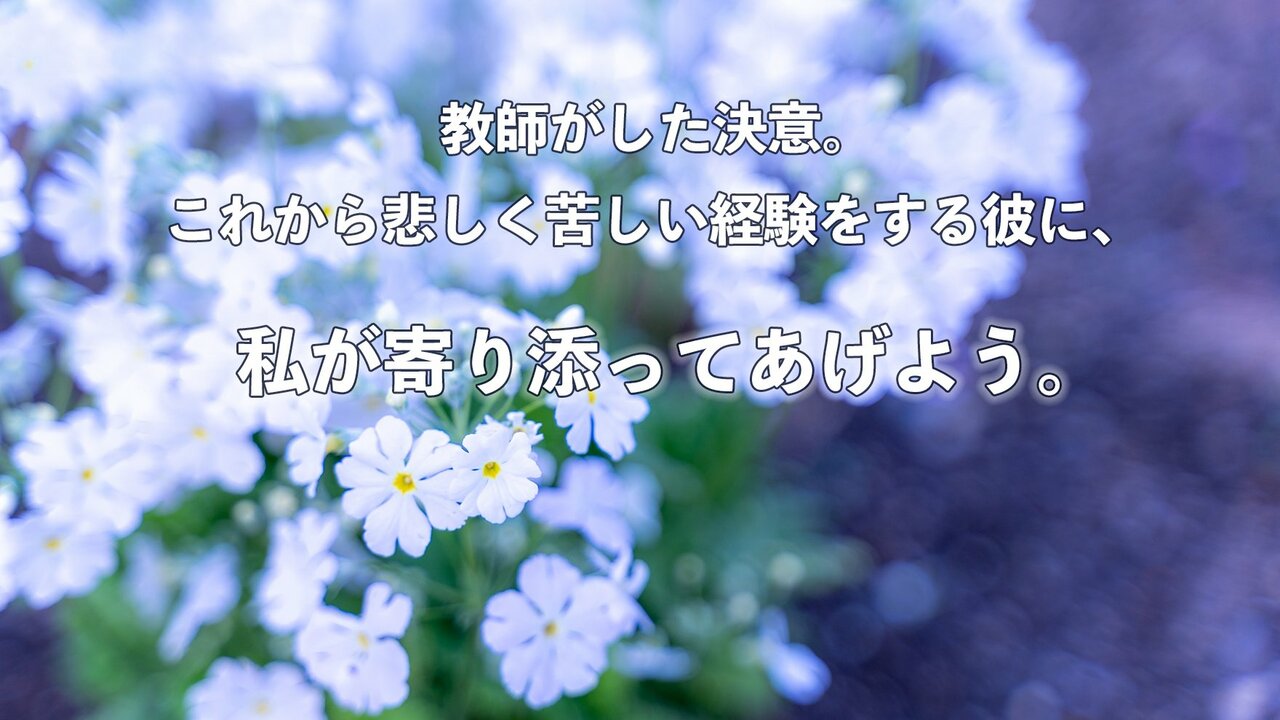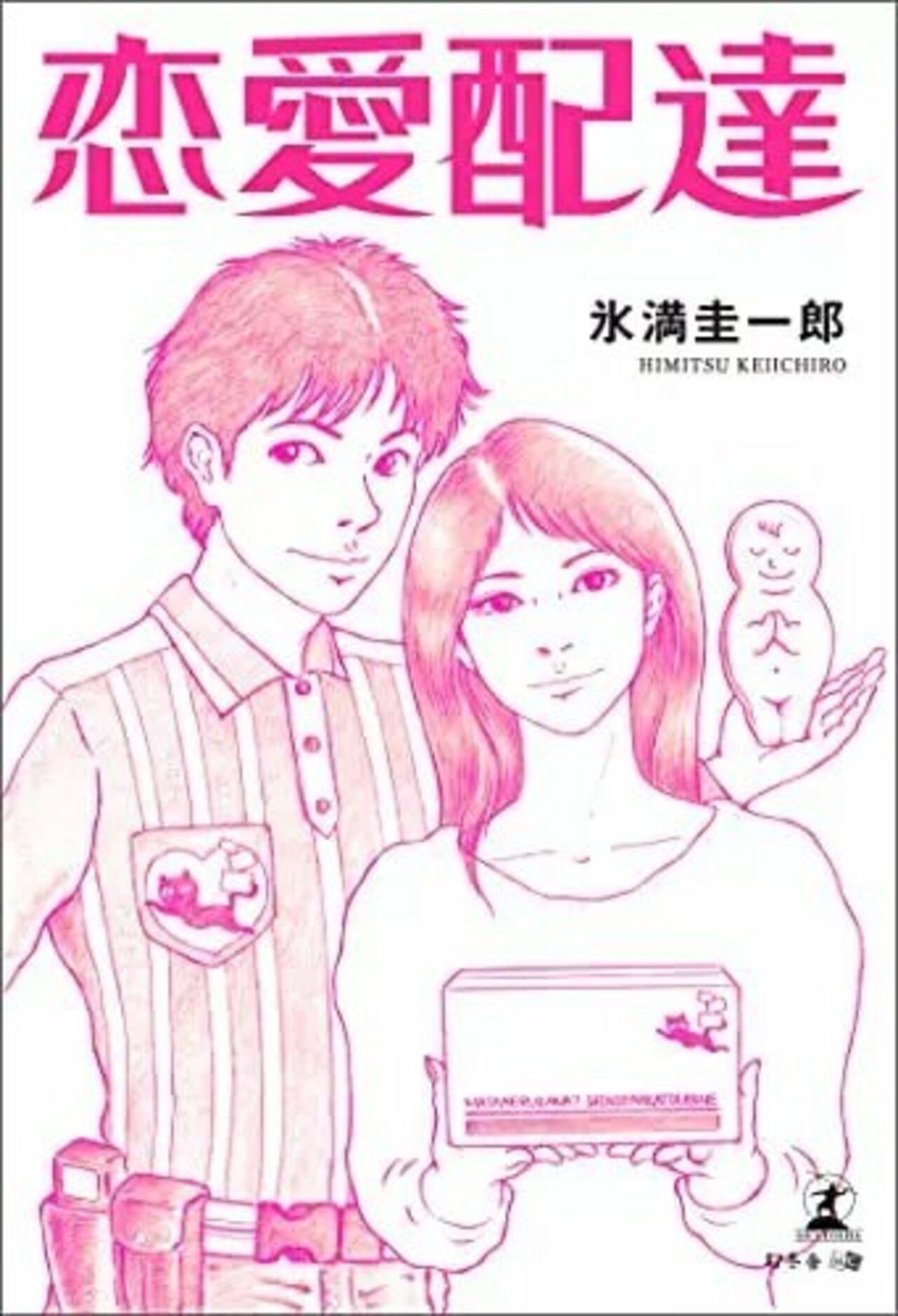第二 雑歌の章その二
誰そ彼
不思議なくらい僕の心は落ち着いている。もしかしたら二人ともセノーテの中に沈んでしまったのかと思うぐらいの静けさの中にいる。そういえばさっきから音が聞こえない。
車の音も鳥の鳴き声も生徒たちのざわめきも何も聞こえない静寂の中で心だけが鋭く研ぎ澄まされている。ずっとこの二人だけの幸せな時間が続いて欲しいと僕は願う。
彼女はまだ自分を優しい瞳で見つめていて、あたかも自分の中にいる別の人と話を続けその人から僕が口にできない言葉の続きを直接聞いているかのように思える。
だが、うんうんと彼女が頷いた瞬間に花の露は雫となり彼女の瞳から零れ落ちていく。
自分の目の前でスローモーションのようにゆっくりと……重力に逆らうことなく。
彼女が長い時をかけて紡いできた涙の糸はとうとう切れてしまった。
それは残念ながら現実の世界に戻ったことを意味していた。
それを見て諦めた僕は彼女に、「先生……橘先生」とゆっくり声をかける。
突然、名前を呼ばれた橘は我に返った。
「ごめんなさい。私、夢見ていたみたい」と彼との距離の近さに驚き、慌てて離れると背を向けハンカチを取り出し目頭を押さえる。先生と生徒の関係に戻らなければならない時がきてしまったと橘は思ったが、もう少しこのままでいたかったとも思っていた。
担任となるクラスの名簿を見て彼の名前に気がついた。久しぶりに会う懐かしさで彼と目を合わせたつもりでいたが、自分の心は別の想いを生んでしまった。心にさざ波が立ち、それが心臓の拍動と共にどんどん大きくなり自分に向かい押し寄せてくるのがわかった。
その理由は拡張型心筋症で失った初恋の相手のまなざしを彼の瞳の中に見つけたからだ。
あの時に想い人と一緒に止まったまま動けない自分の心は再び脈を打ち始めてしまった。
いけない私は教師で彼は生徒なのだから、しっかりしないと……と言いきかせて自分の心をどうにか落ちつかせた。
想い人を失った後も花壇に通い詰めた彼女を優しく慰めてくれたのが彼の母親の優海だった。