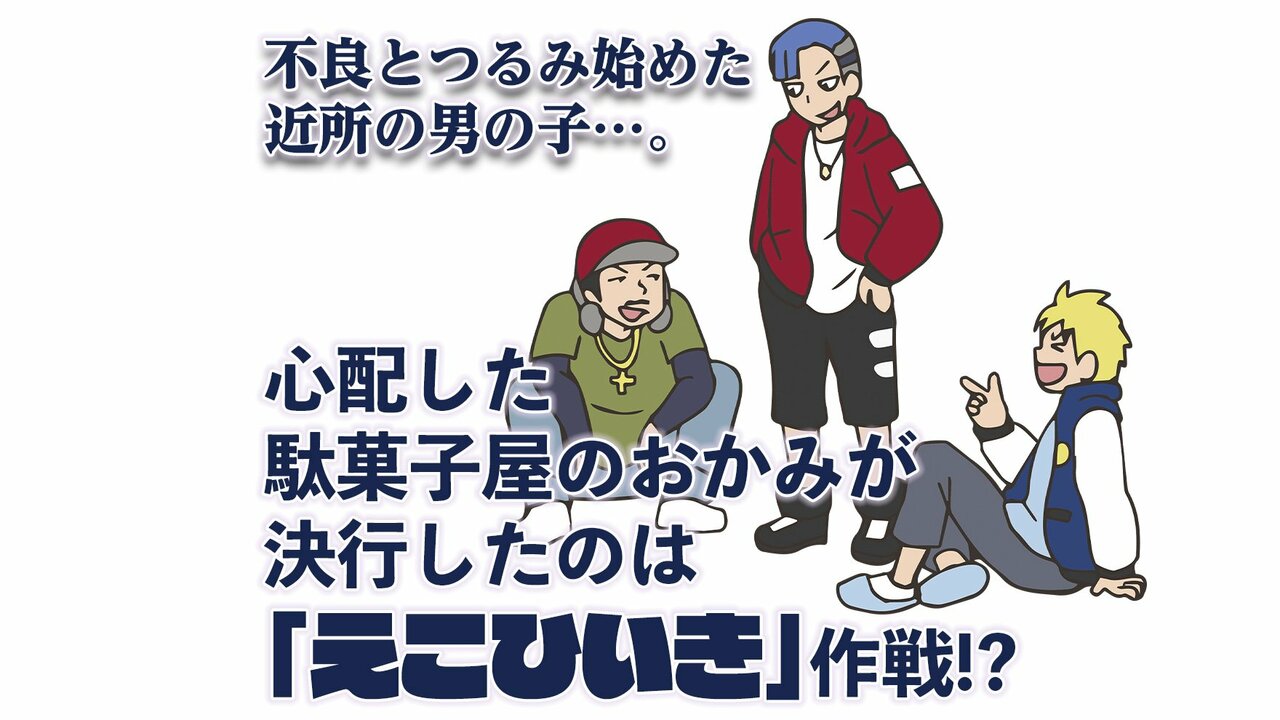すると春彦は隣席から拝借したメニューを、郁子の前に広げてみせた。
「ここにもパフェとケーキがたくさんあるよ。好きなだけ食べるといいよ」
郁子は途端に目をキラキラと輝かせた。亜希子がそれに口を挟もうとするのを制止するためか、春彦はまたもや咳払いをしてみせた。
「任せてください。先輩はドリンク代だけお願いします」
亜希子は少し考えているようだったが、意外にもあっさりとその話に応じた。なんと対照的な姉妹なのだろうか。何事にも素直に反応してみせる郁子に、何とも言えない新鮮さを春彦は感じていた。
「お姉ちゃんはどれぐらい?」
ケーキを取り分ける段になり、春彦ばかりか亜希子までもが味見程度を要求したものだから、たちまちふくれっ面になってしまった郁子は、間髪入れずに目の前に置かれたパフェを見て、あっという間に上機嫌になっていた。
あまおうのパフェには大粒の苺がこれでもかというほど積み上がっていたし、洋ナシとオレンジのパフェにもベルギー産のチョコシロップが惜しげもなく掛けられていた。そのことが余程嬉しいのか、郁子は度々春彦を見ては目をウルウルとさせていた。それにニヤッと笑い返した春彦は、そのパフェの大きさに驚いていた。
二粒分けてもらった苺もやけに大きくて、その内の一粒を亜希子に手渡した。
「全部食べられそうかな?」
当然無理だろうと少し揶揄うようにして言った春彦に、郁子はあっさり「うん」と頷いてみせた。郁子の食べるペースは、実に淡々としたものだった。時に顔を上げて「美味しい」と満面の笑みで言う郁子は、ダージリンティーのお代わりを交えつつも、先ほどのケーキと合わせてそのパフェもきれいに平らげてしまった。
「お姉ちゃん、あまおうの下はレアチーズケーキだったの。クリームチーズとマスカルポーネチーズの二パターンで、どっちもあまおうのクラッシュしたのと、酸味の強いミカン果汁が入っていたよ。今度作ってあげる」
姉妹の相変わらずのやり取りを微笑ましく眺めながら、春彦は考えたのだった。次に郁子を連れて行くとしたら、どんな店がいいだろうか、と。