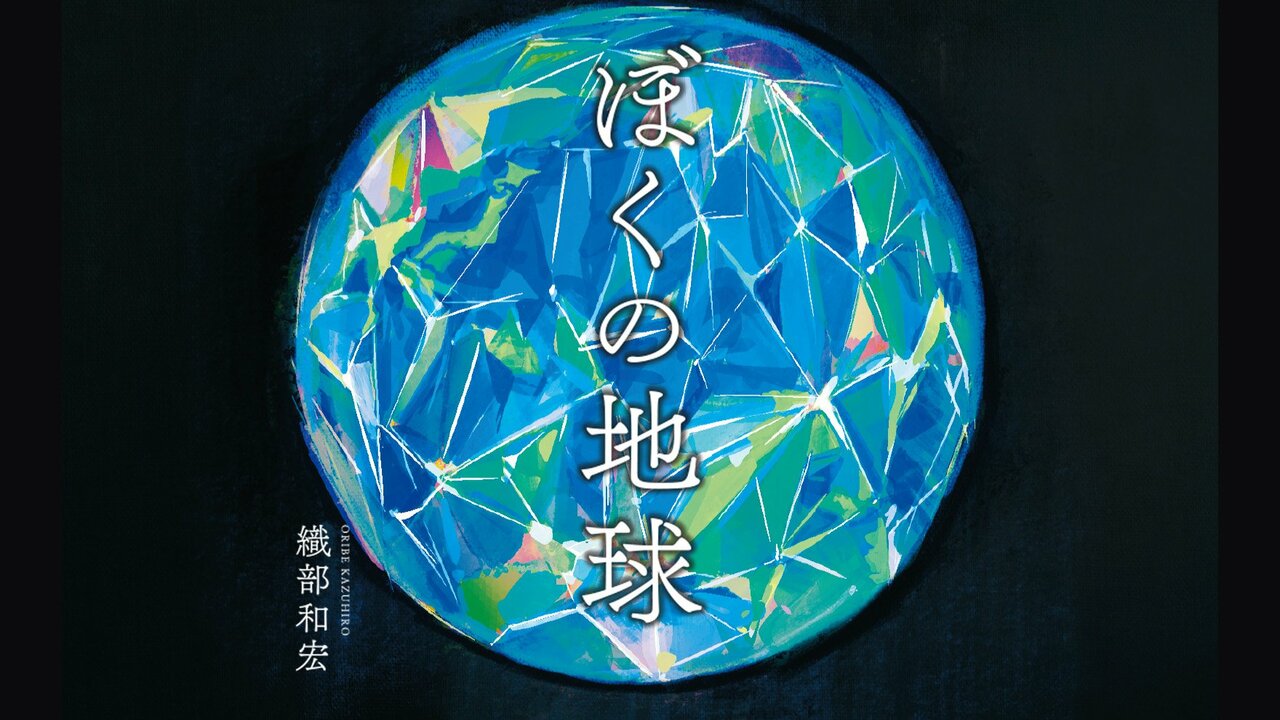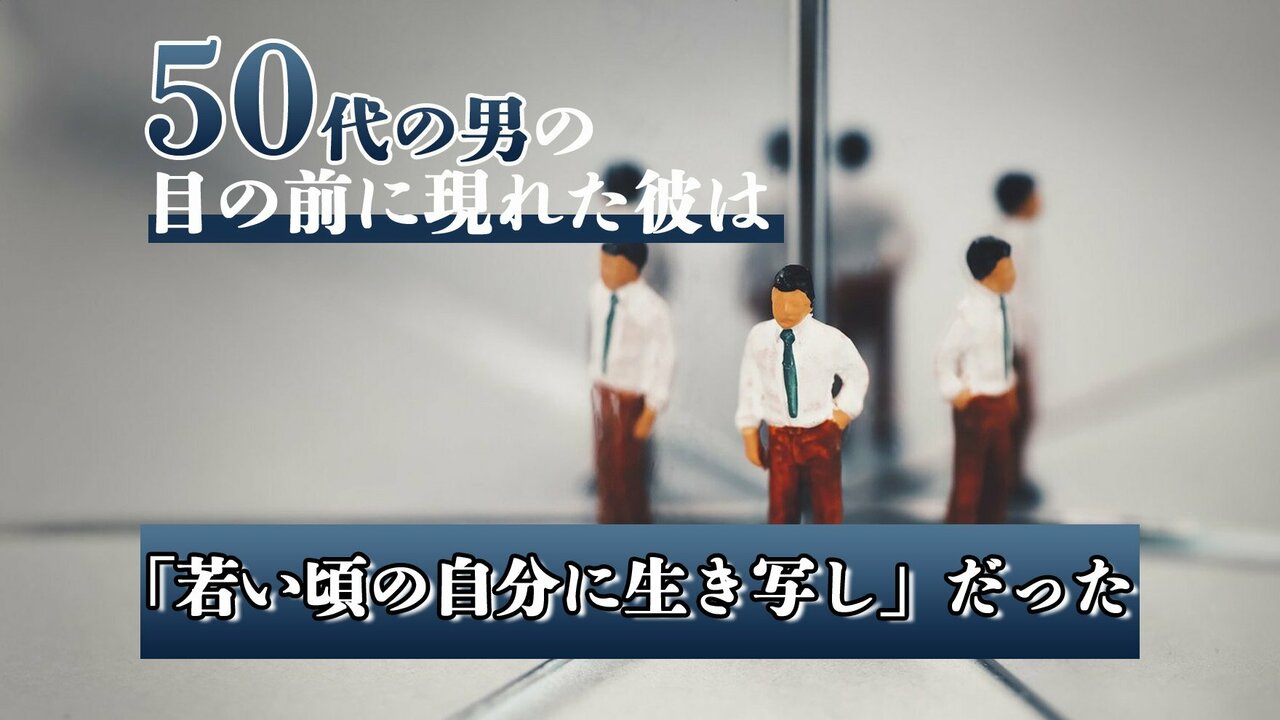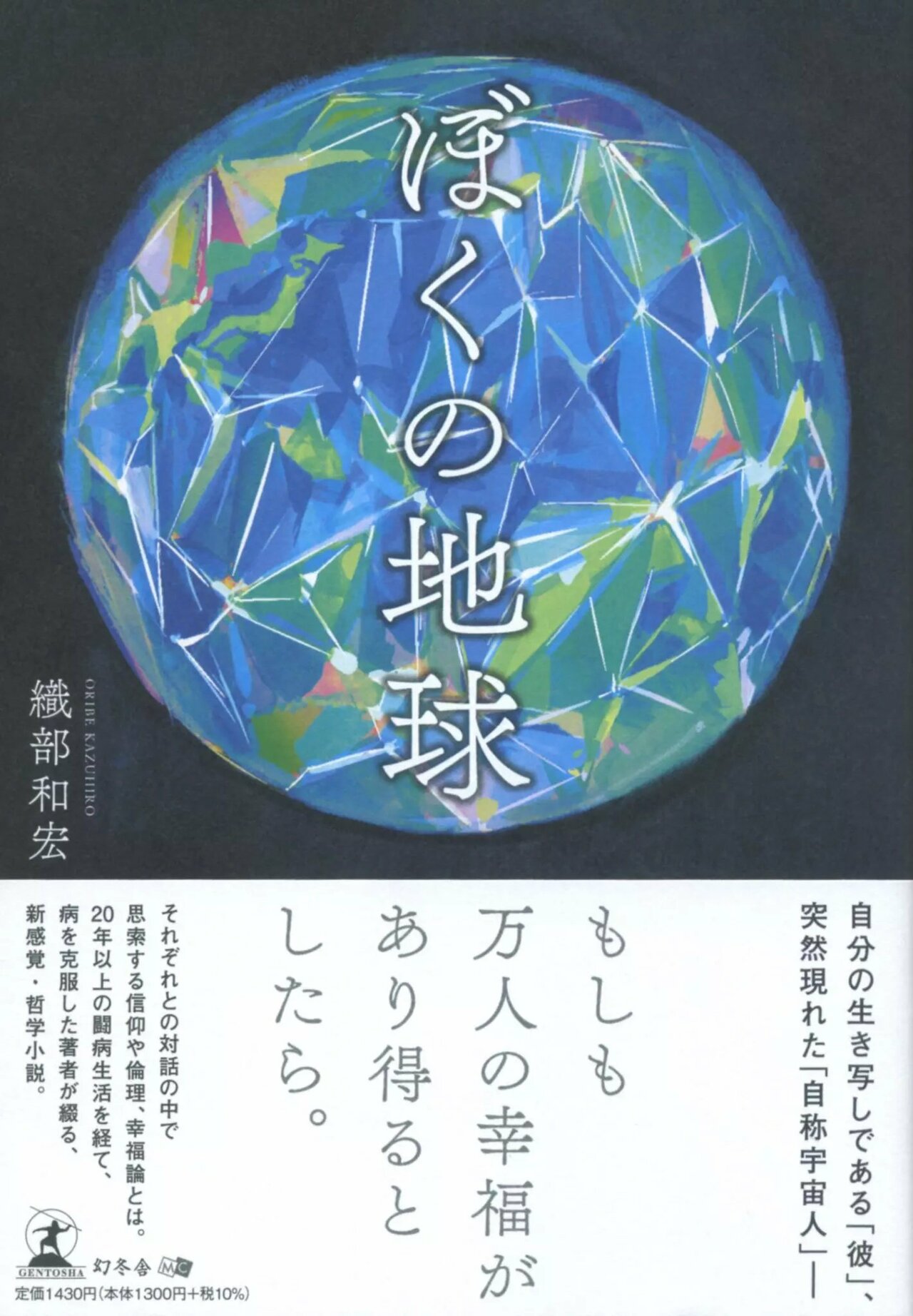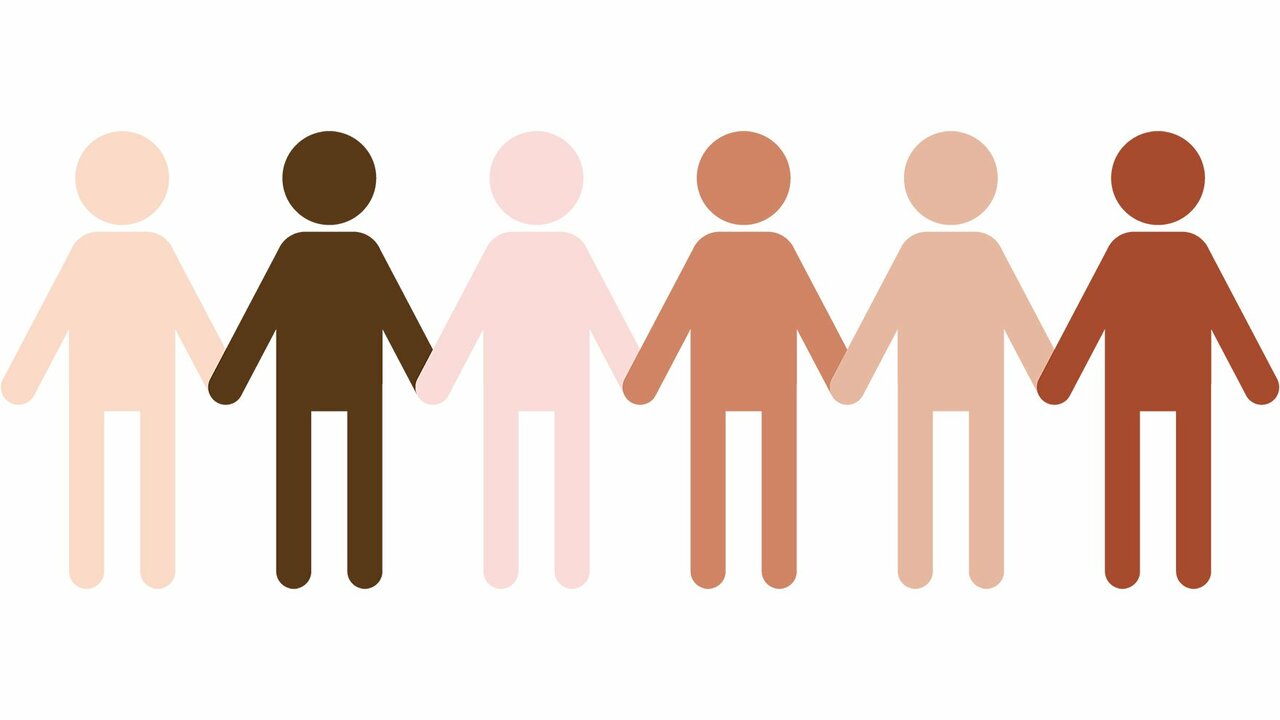ぼくの地球
はじめに
ここに記す文章は私と私に強い印象を放って去っていったある若者との会話や行動を基に、その大まかなあらすじを独自の考察により理論的にまとめたものである。
彼は、私が五十代に突入し「老い」というものが人生において如何なる意味を持つのかについて考え始めた矢先に突然現れた。「老い」というものは概ね否定的な意味を伴って人々に捉えられがちだが、しかし、私がそこに何らかの希望にも通じるヒントのようなものを見出した瞬間、彼は私の眼前に登場したのだ。
あり得ないことだが、彼は私に生き写しだった。正確に言えば若い頃の私にそっくりだった。だからこそ、私は彼に興味を覚え、彼との会話とその印象を正確に記録しようと考えたのだ。
私は彼が発した最初の言葉を鮮明に覚えている。なぜならば、その言葉はきっと私の脳裏におそらくは数十年前にはすでにあったにもかかわらず、そしてしばしばその意味について自問しながらも、ついに一歩を踏み出せないままに終わっていた言葉に違いなかったからだ。
そしてその言葉は、私が見た彼の最初の動作と実に象徴的に調和していた。彼は明らかに、私が老いに突入する以前には到達し得なかった境地にすでに十分すぎるほど入り込み、そしてそこにある雰囲気を見事なまでに体現していた。
私は彼を初めて見た瞬間、二次元的なものが三次元的なものに変化するのを感じた。そこではモノクロームであるはずのものが、時間を飛び越えることによって多色化し、触れることのできなかった感覚が具体的な形を伴って、私の掌に生の温もりさえ帯びながら、極めてポジティヴなメッセージを発しようとしていた。
この驚くべき現象は、しかしその非現実性にもかかわらず、私の中で日々増幅し、想像上の産物でしかないものが、特に青春を生きる者にとって、いつしか日常における掛け替えのない存在となっていくように、この五十歳を過ぎた私の一縷の希望として、私にこのような書を記させようとするその動機となっている。
彼は明らかに、私の中で何かを補う存在としてその役割を果たしている。きっとそれは誰にでも起こり得る事象であり、故にこれを単に私個人の身の上に起きたある一つの出来事として割り切ることはできないように思う。
甚だ僭越ながら、ここに記されるべき内容のすべては、おおよそその人生を幸福の名において定義しようと試みるすべての人に、何らかの重要なインスピレーションを喚起し得るものであり、また同時に理想と現実との、そして結果と過程とのはざまで日々苦悶する人にとっても、「実践のための何か」を得る、その一つのきっかけとなり得るものなのである。