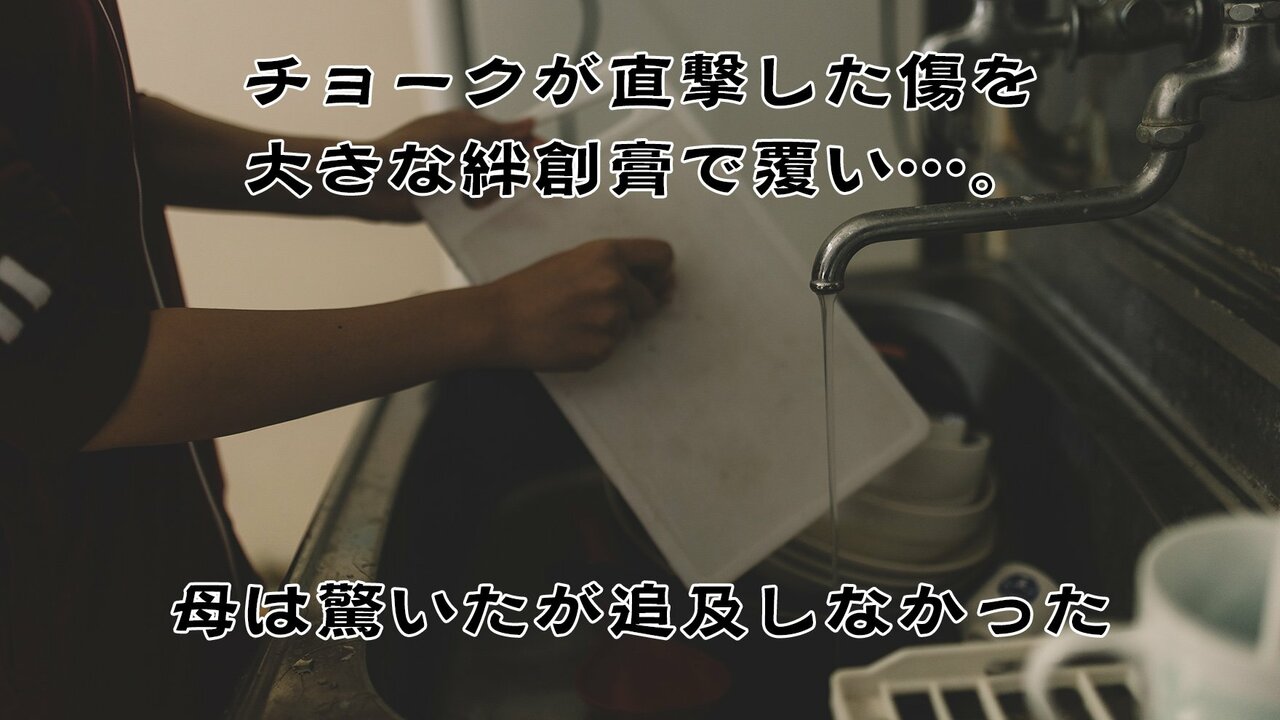成長という木
しばらく便器に座ったが腹の調子は治ったようだった。ここから出る時が問題だ。中からじっと外の気配を窺った。何人かの話し声は聞こえるが幸いな事に気になる奴らの声はなかった。ゆっくりトイレのドアノブを回すと同時に外から勢い良くドアノブが引っ張られた。まるで隠されていた宝か何かを見つけたように周りで歓声が起こった。
「こいつ、ウンコ便所から出てきたぞ」
笑いがトイレに満ちた。
「くっせーなあー」
「ケツにクソが付いてないか調べてやるよ」
アキラだった。
「い、良いよ」
小さな上ずった声が周りにいる生徒たちの爆笑を誘った。
「遠慮すんなよ」
孝輔が俺のベルトに手をかけた。こういう時、決してアキラは自分から手を下さないし、命令もしない。じっと誰かが手を出すのを待つ。仲間がその流れで実行する。そして、一緒に笑い、悪ふざけを楽しむ。アキラはクラスの一員でただの仲間なのだというスタイルを通している。
アキラはたまに小さな行動は起こす。椅子を引いて転ばしたり、弁当のおかずを盗み食いしたり。些細ないたずらで済む事だ。彼は特定の人たちだけでつるむ事はないが、最近では仲間が固まりつつあった。成績も良く、先生からも信頼されているという、特異な集団である。そのリーダーはアキラだという事が誰でも分かってきた。成績はトップクラスだが嫌味がなく、好かれていた。
アキラは不思議な力を持っていた。
始業のチャイムが鳴った。数学だ。担当教師の井上は五十代半ばの男性教師で、いつも始業のチャイムが鳴りやむと同時に教室に入ってくる。井上はベル着をモットーとしている古いタイプの教師だ。自分が教室に入っていく時には全員が席に着いている事を当たり前としていた。
アキラたちは急いで教室に向かった。純太はゆっくりベルトを締め直し、手を洗って一年B組の教室に向かった。今、この災難から逃れられた事の幸運に浸っていたかった。次に起こるだろう災難はこの幸運に比べたら取るに足りない事のように感じられた。教室に入ると井上と目が合った。
「トイレに行っていました」
と言うと何人かがクスクスと笑った。二年生の事件で興奮していた空気は直ぐには収まらない。ちょっとしたキッカケで再び熱を発する。そんな動きを敏感に捉えていたベテラン教師は
「何が可笑しい」
と水を差した。身長百八十センチの長身と剣道で鍛えたというしなやかな体を持つ井上の声は太く教室中に響いた。額や頬に刻まれた皺はくっきり深く、銀ぶち眼鏡の奥で光る眼が余計に井上を近寄りがたい存在にしていた。実際、言い訳は通じない頑固さがあった。