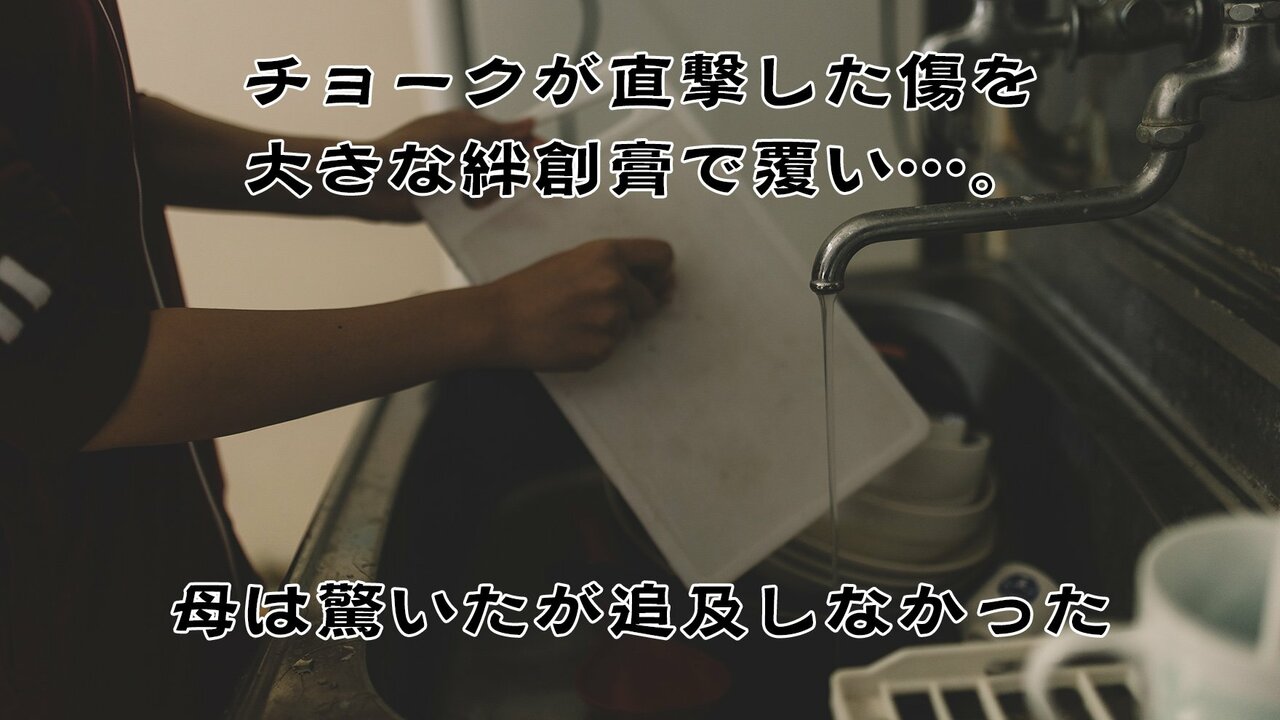成長という木
ひっくり返った弁当箱の中身をどうやって回収したらいいのかと考えた。ひっくり返った弁当の中身をそのまま元に戻すのはみじめだ。だが、そこで反撃しようものなら、冗談の分からない奴だと思われ笑い声は冷たい非難となって自分に突き刺さる。
純太は床に四つん這いになった。四角いご飯に顔をうずめて犬のように食った。顔を上げると、顔中白いご飯粒がついていた。「あははは」教室中に狂ったような笑いが起こった。
純太は黙って顔中にこびりついた米粒のひとつひとつを指で取っては口に放り込んだ。テレビで見る罰ゲームか何かのような感覚でその場を楽しんでいる奴らを見て、純太も笑った。
純太はチラリとアキラを盗み見た。アキラの顔には笑いがなく、冷たい視線を純太に送っていた。何を仕掛けても歯向かわない負け犬としてアキラたちに映ってくれれば良いのだ。こいつはもう使えない、そう思ってくれたら良いのに、それだけを祈った。
それにしても何故、アキラたちは純太にだけ嫌がらせを仕掛けてくるのか。純太の無言の問いかけに納得できる答はない。
初めのうち、純太はクラスの男子全員からの嫌がらせかと思った。それが日を追うごとにアキラの存在が大きくクローズアップされてきた。他の生徒たちは、いろいろな生徒とくっついたり離れたりしていたが、アキラは常に一人で、アキラの周りに生徒が集まってくる。
「あいつホント、ダサいな」
とアキラが言えば、生徒たちはアキラの言葉に納得する。
純太が笑ってひっくり返った弁当の始末をしていたから安心したに違いない。何事もなかったかのようにそれぞれの会話の続きに戻っていた。中には季節外れの蠅のようにしつこく純太を構ってくる奴もいた。それは面白くもなく、ただうざかった。