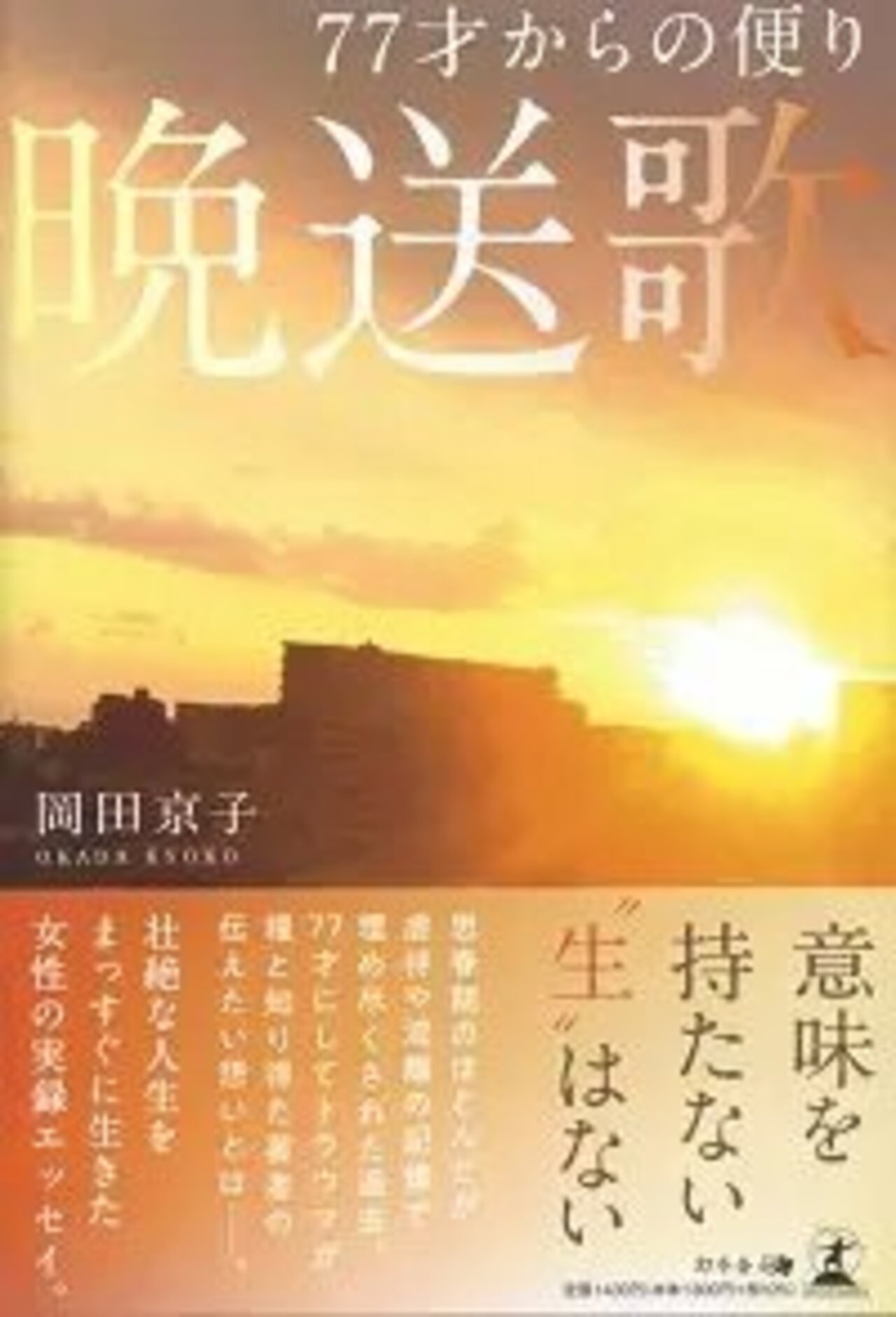第三章 終炎
又、引っ越し。6年になる春休み。何故こんなに引っ越すのか……。今は102才になる養母に聞く術すべは無い。たとえその当時であっても私に訳を話すことなど、彼女の中では露程も必要性を持たなかったろう。
或る日教室での休み時間、クラスの男子が突然大声で“うちのお父ちゃん浮気してんねん、不倫しとんねん!”と。“このクラスの親やねん”と私の顔を見る。男子の苗字はN君、養母の愛人の苗字もN、すぐに察した。只幸い回りの子達には悟られず……男子もそれ以上は立ち入らなかった。
重い石が心に当たった。
その一方で11才から12才半ばまでの刻は別段変わりなく過ぎ去り(男の悪戯以外は)、変わり無いの訳は養母は私のことに関心を示さず。私はと云えば、只彼女の目にふれぬ様に狭い部屋の影で息を潜めてさえ居れば心は傷付かずに済んだ。
未だ彼と縁がつながっていた養母は人並みの幸せを忍ばせ、言い換えれば女として只ひたむきに、一生懸命、生きていたのだ。ただひとつ予期せぬ出来事、初潮を迎える。
養母は赤飯などを振る舞い、見せることの無い笑顔を見せた。私の知らない初めての彼女だった。
その後、程なくして養母に変化が現れる。
この3年程は私さえ大人しく此処に居ないが如くしていれば私の存在も忘れられがちで、それはある意味では平穏を与えてくれていた、のに再び魂が波立つことの蘇りだった。
それは突然飛んでくる“お前なんか貰わんかったら良かった、お前のせいで苦労するんや!”と。誰かかれかに“貰い子だけはするもんちゃうで”云々。
私ももう12才、言葉の意味が理解できる年頃と承知しての言動なのか、否、Nが来なくなったのだ。彼女の苦しみの吐け口というべきか。
今思うにクラスの男子の云ったことは養母の存在が知れてしまったと云うことだろう。
或る日、下校すると玄関に入るなり“阪神の野田まで行って来き !”と肩を押される。行く道筋と片道だけのお金を持たされ……駅に一人立つ私。小学6年になった12才の夏の頃。
片道切符だけの私を彼は連れ帰る。それは幾度か成功し、半年近く続いたろうか。
そして私は中学生に……セーラー服姿の写真が2枚、衣を変えただけの変わらぬう私。表情も無く。