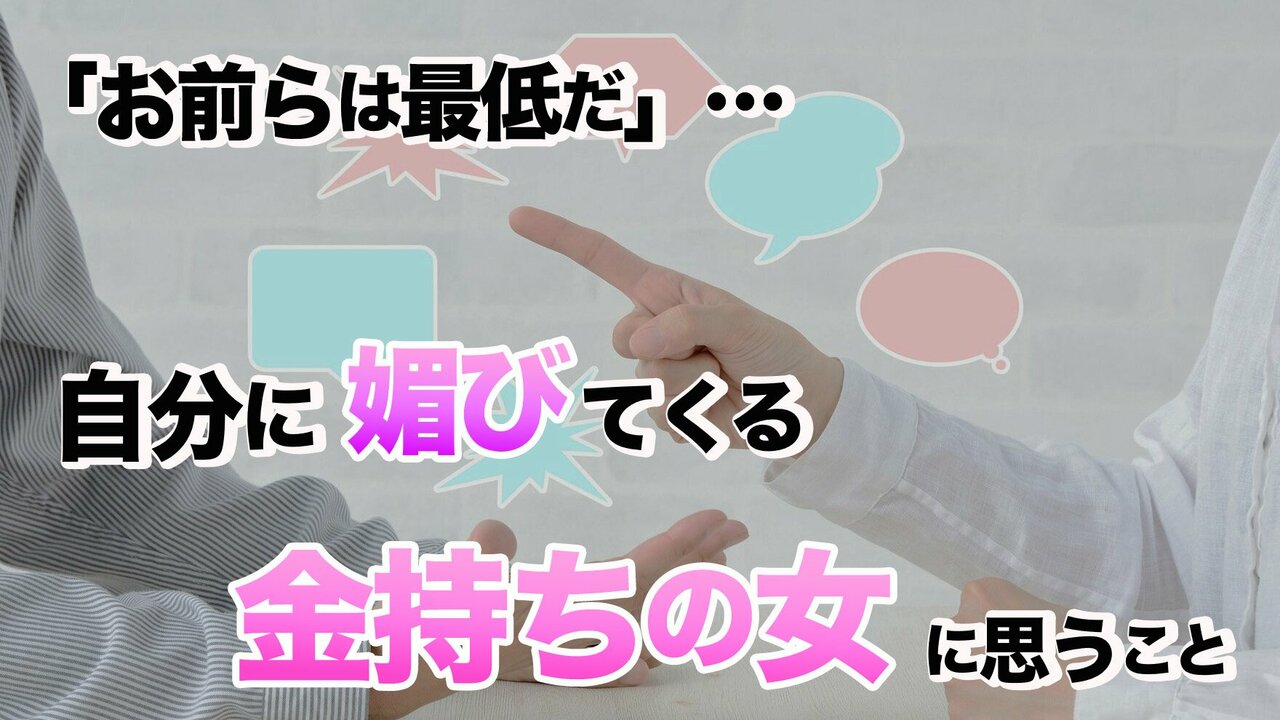酒を手酌でついで新村が笑いながら、またお義理のようにピーナツを一粒、ビールで流し込んだ。居酒屋から出るとふいに夜に囲まれる。新村が前を行く長身の男に声をかけた。整った顔立ちの若い男だ。
「珍しいとこで会うな。こんなとこに用でもあるのか、あ、これが、さっき話してたシナリオ教室の相棒の高城だ」
「いえ、相棒なんてとんでもありません。山下先生ですよね。ご高名はかねがね」
と高城と呼ばれた男が媚びた笑顔を見せた。
「山下にも一、二回、教室、手伝って貰おうと思ってな、今、口説いてたとこだ」
「いや、引き受けるかも分からない。私は人前で話すのは苦手ですから」
「心強いです。ぜひお願いします。僕もご指導願いたいくらいです」
と愛想良く頭を下げ、すみません、これからちょっと用があるものですからと、急ぎ足で通りのほうへ行った。
「イケメンだろ。俺の若い時には負けるがな。テレビ局に勤めてるんだが、この間、賞取ってな。ゆくゆくは一本立ちしたいから手伝いたいって言われたんだ。まあ、確かに若い感性ってのも必要だしな、爺より読み手としてはいいだろ。賞取ったばかりだから、コツみたいなのも教えられるからな、それも売りの一つにしてる」
「いろいろ考えるな」
「お前が考えないだけだ」
踏切の遮断機が下り、警報が鳴り始めた。音はなかなか鳴りやまない。やっと来た電車がその音の中をごとごとと、のんびり通り過ぎた。
「これは逆方向だな。うん、大丈夫、まだまだ俺は酔ってないぞ。これで電車の中で酔いを醒ませば、女房にどつかれないで済むよな」
笑いながら、新村がふらついた足取りで、改札に入って行った。ホームで新村がいつものように大きく手を振った。いい歳をして臆面もなく手を振る新村は、子供のまま大人になったようなところがある。また警報が鳴り、入って来た電車がその新村を飲み込むようにホームから消した。周りの深い闇の中で、明るいホームは主役をなくした舞台のようだ。