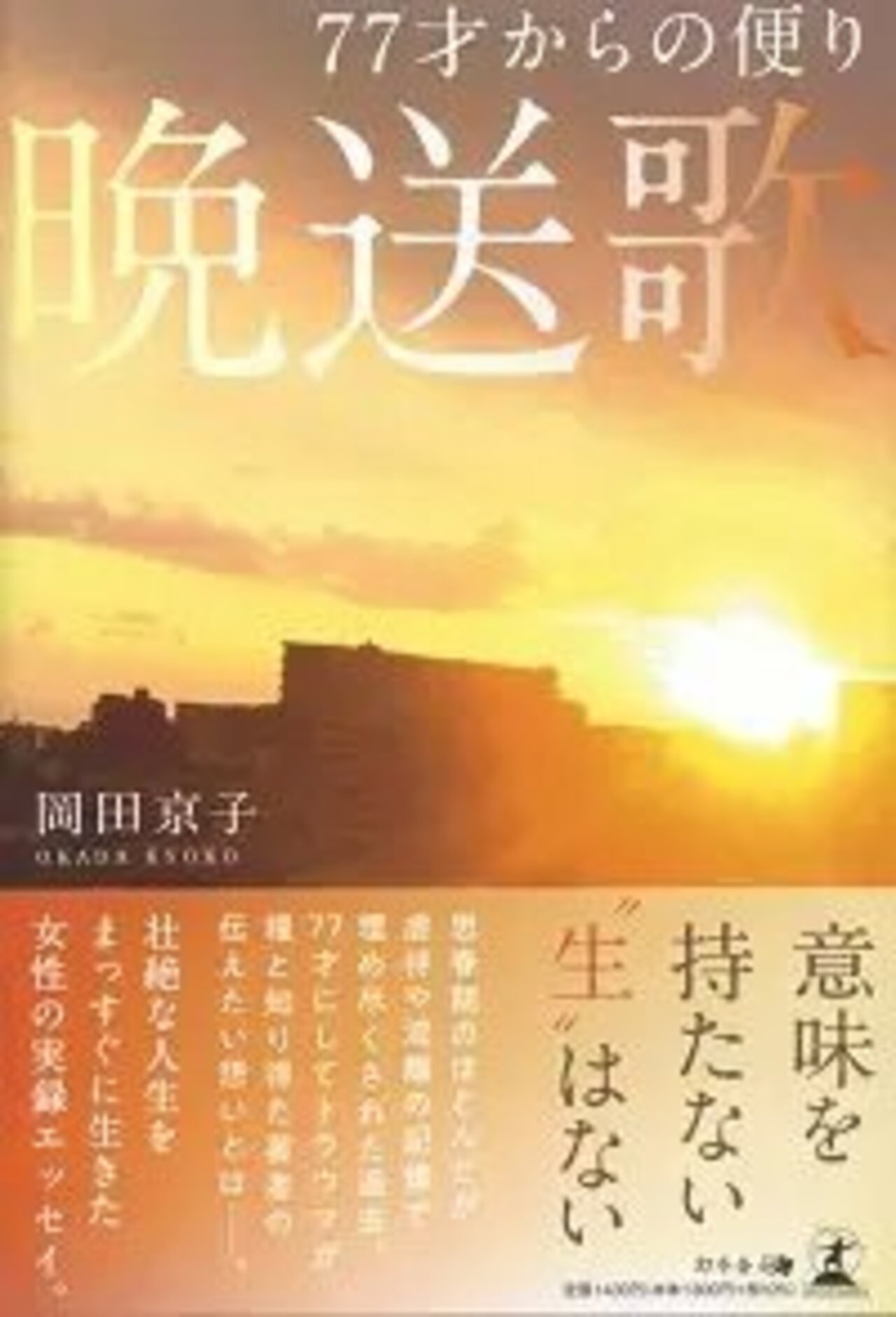引き裂かれる心。
宝塚の山の上にあるアパート、母曰くある人の好意で部屋が空いてるからと無償の仮住居(後に養母より聞く)。季節、寒い冬、窓ガラスが2枚割れている。差し入れの布団で二人かじかんで寝た。気持ちは落ち着かず窓ガラスの震える音、ヒューヒューと鳴る風の音、それでもお母ちゃんと二人で肩寄せ合って寝られる。そのことが他のことなど外界の又、外、それが幸せの形。流れ着いた二人の巣、色褪せた畳、土色の襖紙、風の舞い込むきしんだ窓、使い古された布団、これも情けのナベカマ、今の二人には充分な恵みの部屋と思えた。
しかし何を食べ何を糧として日々命をつないでいたのか。ほどなくして母の姿が日中見えなくなる。そして貧しくとも食事ができる、二人の夕食。その頃は釜から炊けたご飯を小さな桶の様なものに移し替え、母はその上にきれいなフキンをかけ蓋をし、二人で大切に頂く。
暫くは同じ様な日々が続く。時に遠慮のかたまりのご飯が底に1人分にも満たず残る、
”美夜子ご飯いれたろ”
と母は云う。私はそのご飯を見つめ心の中で声が聞こえた(お母ちゃんは毎日働いているんや、私よりもっとお腹がすいてるにきまってる)と。
”お母ちゃん、私もうお腹いっぱい、お母ちゃん食べて”
と、本当はその1杯でも足らないぐらいなのに。
今も思う、なぜ私はそんなに優しく? できる子供だったのかと。なぜ素直に”ウン”と云わない子だったのかと。
何日に1度か紙芝居が来る。私はお金を持たない観客。シッシッと追われ柱の陰で覗き見です。1、2度くらいかな、母が口ばかり大きな財布を開いてくれた。子供の私にも丸見え、その財布にはお札など入ってなく底にこびりつくように小銭がみえる。母は底ざらいするように、自分の左手に全て出し右手の指でよりわけ私に持たせてくれた。
今日の暮らしのことなど何も解らず、私は踊るようなステップで、そして堂々と紙芝居のおじさんの前に行き大きなあめ玉を1つ買い、追い払われることなく他の子供達と混ざり心おきなく見物ができるのだ。おじさんの”今日はどうした”の顔は、たかがあめ玉1つでも”どーや”の気分だった。
でも部屋に戻るとおもむろに紙を敷きその大きなあめ玉を上に置きカナヅチで割る。何度か慎重に約7つ程に、それは私の一週間分の宝、小さなカケラから最後は大きなカケラ。それは、今思えば信子の家のガラス瓶の中の黄金と同じ価値だったのか。一日ひとかけごとに大切に口にする。